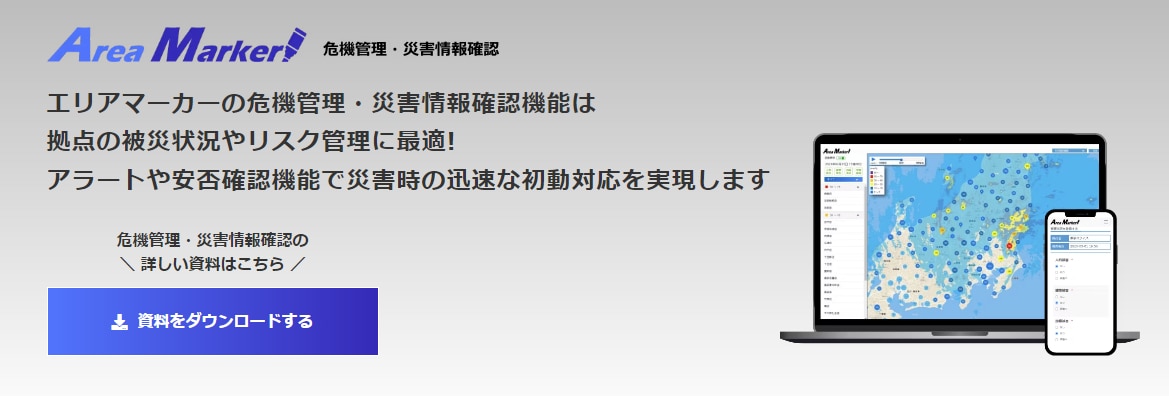BCP(事業継続計画)とは?必要性や策定の流れをわかりやすく解説!
企業が事業を存続させるためには、BCPの策定が必要です。
BCPとは事業継続計画のことで、災害や火災・テロや感染症等によって事業の継続が難しくなった際の対策を定めています。
BCPを策定しておくと、緊急事態に陥った際にスムーズな対応ができるため、従業員も安心して働けるでしょう。
そのため、災害時の被害緩和と従業員の安心を獲得するために、自社に合ったBCPを策定してください。
この記事では、BCPの必要性や策定の流れ等を詳しく解説します。
もしもの事態に備えてBCPを策定してみましょう。
✓チェックリスト付でよく分かる! 「BCP策定のポイントとDX化」 資料、配布中
⇒無料で資料をダウンロードする
目次[非表示]
- 1.BCP(事業継続計画)とは
- 2.BCPと類似の用語の違いを整理
- 2.1.BCM(事業継続マネジメント)
- 2.2.BCS(事業継続戦略)
- 2.3.企業防災
- 2.4.業務継続計画
- 2.5.DCP
- 3.BCPの必要性
- 3.1.災害発生時に被害を緩和できる
- 3.2.従業員が安心して働ける
- 3.3.社会的信用が得られる
- 4.BCP対策は企業の義務?
- 5.BCPの策定状況は企業規模による偏りがみられる
- 6.BCP策定の流れ
- 6.1.①BCPの基本方針を決める
- 6.2.②体制を考える
- 6.3.③事業を選定する
- 6.4.④リスク分析・戦略・対策を考案する
- 6.5.⑤計画書を作成する
- 7.BCPを作成・運用する際の6つのポイント
- 7.1.①BCPのサンプルやガイドラインを参照する
- 7.2.②重要な事業に的を絞る
- 7.3.③自社の実態に合う実現可能性の高い内容にする
- 7.4.④行動の指示をより具体化しておく
- 7.5.⑤継続的な見直しと改善を行う
- 7.6.⑥社内でのBCPを周知・教育する
- 8.BCPの策定にはゼンリンデータコムのArea Marker「危機管理・災害情報確認機能」が活用できる
- 9.まとめ:もしもの災害時のために、自社内のBCPを策定しておこう!
- 10.災害時に役立つゼンリンデータコムの「Area Marker」もご活用ください!
BCP(事業継続計画)とは

BCPとは「Business Continuity Plan」の略称で、事業継続計画の意味合いを持ちます。
地震や台風等の自然災害、火災やテロといった事故・事件等、緊急事態に備えた事業計画がBCPです。
電力不足による計画停電、世界的に影響を及ぼした新型コロナウイルス蔓延等、通常業務を停滞させる要因はさまざまあります。
平常時にBCPを策定しておけば、万が一の事態に慌てることなく適切な対応が可能です。
企業の長期的な継続のため、また従業員を守るためにも、BCPを策定しておきましょう。
■自社店舗、倉庫、取引先などの災害リスクは把握していますか?
「Area Marker」は多拠点情報を地図上に可視化・災害時に自動でアラート発報!
⇒「Area Marker」の資料を見てみる
BCPと類似の用語の違いを整理

BCPには、似た用語が存在します。
それぞれを間違って認識しないためにも、類似用語の違いを整理していきましょう。
BCM(事業継続マネジメント)
BCMは、Business Continuity Managementの頭文字を略した単語です。
日本語に訳すと「事業継続マネジメント」となります。
BCPは計画を立ててまとめるまでを指しますが、BCMは事業継続全体を管理し、運営を行うマネジメントまでを指す言葉です。
事業を継続するためにはBCPを定期的に研修内容として盛り込み、組織や事業内容の変更があった際には内容を更新しなければいけません。
時代に応じた変化も必要で、見直しや改善を繰り返すものがBCMとなり、そのための計画がBCPです。
BCS(事業継続戦略)
BCSはBusiness Continuity Strategyの頭文字をとった用語で、日本語では「事業継続戦略」と訳します。
BCPの中でも組織の中核となる事業を続けるための具体的な手立てとなり、最終的な目標に到達するための方針です。
自然災害やテロといった事故や事件が起きた際でも、応急処置となる復旧やその後も重要な業務を遂行するためにBCSが必要になります。
BCPの中でも重要な要素として覚えておきましょう。
企業防災
企業が災害に備える取り組みが企業防災です。
BCPは、災害時の事業継続、早期復旧を目的としていますが、従業員や顧客を災害や事故から守るために安全を確保するほか、企業の設備に対する被害を最小限に抑えるための対策を実施することが目的となります。
企業防災の代表的な例としては、安否確認システムの導入や災害対策本部の設置、復旧作業マニュアルの策定等です。
★関連記事
業務継続計画
業務継続計画は事業継続計画と同じように使用されている用語ですが、対象となる機関が異なります。
BCP(事業継続計画)は、主に民間企業を対象にして使われていますが、業務継続計画は行政や介護業界が対象です。
行政が被災したとしても業務を適切に行うため、優先的に行うべき業務を特定し、執行体制や対応手順、継続するために必要となる資材の確保等を前もって定めるための計画を指します。
DCP
DCPは、District Continuity Planの頭文字をとった略語です。
日本語では地域継続計画と訳されます。
災害が発生し、電力や水道、ガスや交通等のインフラが停止する可能性もあり、生活にも大きな影響を与えるでしょう。
その際に、自治体や地域企業が連携して実施する防災対策がDCPです。
優先的に復旧する施設設備をあらかじめ決定しておき、有事の際には計画どおりに復旧を実施していきます。
BCPの必要性

BCPは必要性が高い事業計画といえます。
BCPを策定すると、次のようなメリットを得られるでしょう。
それぞれのBCPの必要性を確認して、BCPを策定すべきか社内で協議してみましょう。
災害発生時に被害を緩和できる
BCPを策定しておくと、災害発生時に被害を緩和できます。
地震やテロ等の緊急事態によって事業を継続できなくなり、企業に損害が加わると最悪の場合は倒産するかもしれません。
緊急事態が発生した際には、迅速な対応によってできるだけ早く事業を復旧させることが大切です。
BCPを策定して緊急事態発生時の対応をアナウンスしておくと、スムーズな対応ができ、被害を最小限に抑えられます。
万が一の事態でも企業を存続させるには、BCPの策定は必要といえるでしょう。
従業員が安心して働ける
BCPを策定している企業では、従業員が安心して働けます。
緊急事態発生時の対策を何も講じていない企業では、地震や火災が起きた際に従業員はどのような行動をとればよいかわからず、混乱してしまうでしょう。
BCPを策定しておくことにより、緊急事態発生時にどのような対応をすればよいか事前に把握できるため、従業員も安心できます。
このように、BCPは従業員の安心にもつながるため、定着率の向上が期待できます。
社会的信用が得られる
緊急事態発生時には、どの企業も事業が停止してしまう可能性があり、業務に支障をきたしてしまいます。
取引先や顧客にとっては、事業が停止してしまう企業より緊急事態時でも迅速に対応できる企業の方が安心感は高くなるでしょう。
そのため、BPCを策定しておけば、競合他社よりいち早く事業を復旧して、通常業務を再開できる可能性が高くなるため、社会的信用が得られます。
緊急事態にいち早く事業を継続できた企業は、リスクマネジメントを徹底していると好印象を与えることもできるでしょう。
万が一の事態に迅速な対応ができるよう、BCPを社内で共有しておきましょう。
★関連記事
災害時のリスクマネジメントとは? BCP作成のポイントも紹介
BCP対策は企業の義務?

内閣府は「事業継続ガイドライン」を策定し、関連制度の整備や社会の変化等を踏まえ定期的に改訂を行ってきました。
企業が災害などの危機的状況を乗り越えるためにも、政府はBCP(事業継続計画)の策定を推奨しています。
万が一の際でも、策定したBCPどおりに対処をすれば迅速に対応できます。
しかし、企業として「絶対に策定しなければいけない事案なのか」と考える方もいるはずです。
「義務でなければ無理に策定しなくてもよい」と考える企業もいますが、実際には策定しないことによるリスクもあります。
直接の義務ではないが安全配慮義務と密接に関わる
BCPを策定する企業は徐々に増えています。
政府も推奨しているため、策定しなければ違反になると考える方もいますが、実際には法律で定められた対策ではありません。
BCPは法的に義務付けられているものではないので罰金が科せられるといった心配もないので安心してください。
ただし、BCPは安全配慮義務と密接に関わる対策でもあるので注意が必要です。
労働契約法第5条では、“使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。”と記載されています。
BCPには防災に関する要素が含まれているため、安全配慮義務にもつながりがあると推測できるでしょう。
そのため、企業で何も対策をしないまま災害や事故が発生した際には、安全配慮義務に違反したとみなされる可能性があるので注意が必要です。
BCPは決して義務ではありませんが、労働契約法の安全配慮義務に対しては影響がある点をあらかじめ理解しておきましょう。
また、リスク管理の低さが露呈するため、信用度にも影響を与える可能性があります。
介護事業者では2024年からBCP策定が義務化
2021年4月の介護報酬改定で、介護施設に対して2024年4月までにBCPの策定を義務付けています。
策定の義務化は、感染症や災害時の対応力を強化することが狙いです。
介護は、要介護者だけではなく、その家族が安心安全に過ごすために必要不可欠です。
災害や感染症が流行したとしても、安定的にサービスを提供することが何よりも大切となっています。
しかし、災害時と感染症の発生時では業務継続において対応の仕方には大きな違いがあるため、BCPの計画は「自然災害」と「感染症」を想定し、2種類のパターンを用意しなければいけません。
自然災害 |
正確な情報収集ができる体制を作る |
事前対策と被災時の対策に分けて準備を行う | |
業務の優先順位を考える | |
従業員数や利用者数に応じた備蓄を実施する | |
計画を適切に行えるよう研修や訓練を実施する | |
有事の際には避難所としての機能を果たせるように体制を整える | |
感染症 |
施設や事業所内の関係者とで情報の共有方法と役割分担を決めて素早い判断ができるよう体制を整える |
感染者が発生した際の対応方法を決める | |
対応できる職員を確保できる体制を整える | |
業務の優先順位を考え | |
計画を適切に遂行できるよう、研修や訓練を実施する |
BCPの策定状況は企業規模による偏りがみられる

企業によってBCPの策定状況には偏りがあります。
状況の詳細をみていきましょう。
大企業・中堅企業では70.8%が策定済み
内閣府では、BCPの策定状況に関する調査を行っています。
2022年1月7日から2月14日に実施された調査では、大企業の70.8%がBCPを策定済みと回答し、策定中と回答した14.3%を合わせると8割を超える大企業でBCPが策定されていることがわかりました。
BCPを策定したきっかけに関する調査では、「リスクマネジメントの一環として」と回答した企業が多いという調査結果がでています。
前年度と比較をしても増加傾向にあり、多くの企業で自発的にBCPを策定したことが予想できるでしょう。
参考:令和3年度 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査
BCP策定済みの中小企業・小規模事業者は少ない
大企業以外の中小企業や小規模事業者においては、「2022年版中小企業白書・小規模企業白書」を確認すると、BCPの策定状況がわかります。
調査によると、2021年の段階でBCPを策定している企業は15%という結果でした。
策定中の7%や策定を検討している24%をプラスしても、46%ほどの企業しか策定に取り掛かっていないことがわかります。
大企業と比較するとBCP策定は進んでおらず、有事に直面した場合には大きなリスクが伴うことが予想できるので、BCPのメリットを伝え、事業継続性を強化していくことが重要です。
BCP策定の流れ

BCPの策定は、大きく分けて次の流れで進めます。
①BCPの基本方針を決める
②体制を考える
③事業を選定する
④リスク分析・戦略・対策を考案する
⑤計画書を作成する
それぞれの流れを確認して、緊急事態に備えておきましょう。
①BCPの基本方針を決める
BCPを策定する際には、まず基本方針を決めましょう。
社内で緊急事態発生時に、「何を優先的に対応すべきか」方針を定めておけば、従業員一人ひとりが適切な判断をしやすくなります。
緊急事態発生時に考えられるリスクをリストアップし、優先順位を定めてBCPの基本方針を固めましょう。
基本方針の例は以下のとおりです。
- 従業員の安否確認・安全確保を最優先する
- メイン商品の製造ラインが停止した場合は、ほかの製造ラインを一時的にメインに振り分ける
- 自社の事業に大きな影響がない場合は、地域の復興や被災者援助に協力する
等。
ポイントは自社の基本方針や経営方針に基づいたBCPの基本方針を決めることです。
②体制を考える
BCP策定のためには、社内で体制を整えなければなりません。
各部署の責任者や経営者を含めたBCP戦略の責任者を選定しましょう。
BCPを策定する際には、社内に共有・調整できる体制を考えておくことも大切です。
BCP策定時には各部署の関係者を集めて、具体的な対応策を協議します。
その後、社内全体にBCPを共有するためには、各部署に共有できる人材を任命し、体制を整えておくことが大切です。
緊急事態でも迅速な対応ができるように、各部署の責任者を選定して、事前にBCPを社内全体に周知させておきましょう。
③事業を選定する
災害等の緊急事態が発生した際に、真っ先に復旧させる事業を選定しておくことも重要です。
すべての事業が停止した際に、まずは「何を優先的に復旧させるべきか」優先順位を定めていないと対応が遅れてしまいます。
BCPは企業の存続に関わるため、売り上げや取引先との関係性をふまえて、優先的に復旧させる事業を選定しておきましょう。
④リスク分析・戦略・対策を考案する
BCP策定のために、リスク分析を行い戦略を練った後、対策案を考案します。
まずは、BIA(事業影響度分析)を行ってリスク分析を行いましょう。
BIAとは「Business Impact Analysis」の略称で、災害や事件が発生した際にどのような影響が生じるのかのリスク分析です。
企業への損失や事業復旧までにかかる所要時間が判明すれば、リスクを解消するための戦略を考案できます。
優先的に復旧させるべき事業から順に、戦略を考案して緊急事態の対策を練りましょう。
ポイントは想定されるリスクをすべて書きだし、具体的な戦略・対策を考案しておくことです。
万が一の事態を想定してBIAを行っておくことで、効果的なBCP対策を策定できます。
⑤計画書を作成する
BCP策定の最終ステップとして、計画書を作成します。
BCPの計画書は、事前対策の計画書・教育や訓練の計画書・改善のための計画書等さまざまです。
BCPは各部署で行えますが、最終的には企業全体で取り組まなければいけません。
そのため、BCPによる費用対効果を分析して事業継続計画書を作成してください。
事業継続計画書を経営陣に提出して、改善点や課題点がないか判断を仰ぎます。
企業として取り組むべきBCP計画書を作成し、各部署に周知できれば、BCPの策定は完了です。
BCPを作成・運用する際の6つのポイント
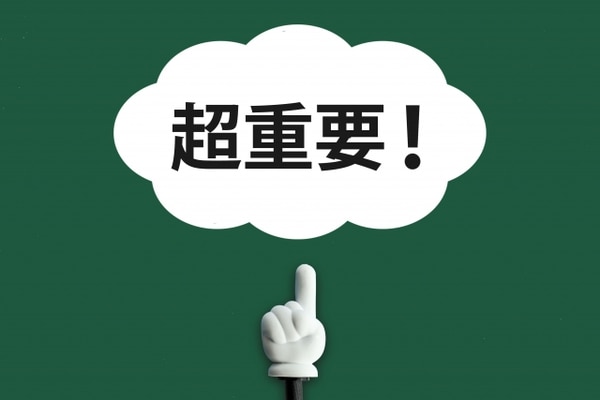
BCPは作成して終わりではありません。BCPを作成した後は、社内で共有し適切な運用をしましょう。
また、BCPは継続的な見直しによる改善で、より効果的な事業継続計画を策定できます。
BCPを作成して運用する際には、6つのポイントを意識してください。
それぞれのポイントを確認して、万が一の事態に備えたBCPを作成しましょう。
■✓チェックリスト付でよく分かる! 「BCP策定のポイントとDX化」 資料、配布中
⇒無料で資料をダウンロードする
①BCPのサンプルやガイドラインを参照する
BCPを初めて策定する場合、どのようなフォーマットの計画書が自社に適しているか、BCPのサンプルやガイドラインを参照してください。
中小企業庁がBCPの運用指針や必須項目を記載したサンプルを公開していますので、参考にするとBCPを作成しやすいです。
他にも内閣府の防災情報ページを参照すると、ガイドラインが記載されています。
BCPのガイドラインは経済産業省・中小企業庁にも公開されているので、BCP作成に不安がある場合は参照してください。
②重要な事業に的を絞る
BCPはすべての事業に向けて対策を考案できればよいですが、緊急事態発生時には余裕がない可能性も高いです。
そのため、優先的に対応する事業を絞らなければなりません。
緊急事態の対策は、企業の存続に関わる重要な事業を中心に、中核事業を復旧させるBCPを作成してください。
また、重要な事業に的を絞る際には、各部署の担当者だけでは適切な判断ができません。
BCPを作成する際には経営陣と相談して、優先すべき事業を選定しておきましょう。
③自社の実態に合う実現可能性の高い内容にする
BCPは、自社の実態に合う実現可能性の高い内容にしましょう。
現実的ではない方法を策定してしまうと、万が一の際に運用できない危険性があります。
無理な計画は働く社員のモチベーションを下げてしまう可能性もあり、トラブルにつながるケースもあるので危険です。
確実に実施できる範囲の計画を立てることが重要となります。
④行動の指示をより具体化しておく
BCPを作成して満足してしまっては意味がありません。
万が一の事態に備えて、BCPで定めた行動の指示をより具体化しておきましょう。
具体的な行動の例は以下のとおりです。
- 自身の安全確保が完了すれば、安否確認システムで自身の安否を企業に伝える
- 就業中に災害が発生した場合の避難場所の指定
等。
また、緊急事態に従業員が適切な行動をとれるように、各部署からBCPの内容を共有しておくことや、訓練を行っておくことも大切です。
災害等の緊急事態が発生した際には、冷静な判断ができずパニックに陥る可能性があります。
そのため、事前に行動の指示を具体化して、どのような対応をとるべきか全従業員に共有できていると、緊急事態時でも慌てずに最適な行動をとれるでしょう。
非常事態でもBCPに沿った行動ができるよう、指示をより具体化しておく必要があります。
⑤継続的な見直しと改善を行う
BCPは作成して終わりではなく、継続的な見直しと改善を行わなければなりません。
各部署の担当者の異動や方針変更があった際には、変化に応じてBCPを改善する必要があります。
継続的にBCPを見直して、常に緊急事態を想定した対策へと改善していくことが重要です。
また、BCPに携わる担当者が異動・退任した際に、引き継ぎが適切に行われていないと非常事態時に対応が遅れてしまう可能性もあります。
担当者が変わる際にはBCP関連の引き継ぎを徹底し、いつ緊急事態が発生しても適切な対応をとれるよう準備しておきましょう。
⑥社内でのBCPを周知・教育する
BCPを作成しても、事前に社内への共有が行き届いていないと緊急事態時に対応ができません。
社内でのBCPを周知して教育を行うことが、緊急事態時の備えとなります。
まずは、各部署から全従業員へBCPを共有して、周知させておきましょう。
なお、何も説明なしにBCPを共有しても、従業員のモチベーションが低く、しっかりと理解を得られない可能性があります。
そのため、「なぜBCPを作成したのか」目的と理由を明確にして、従業員への理解を得ましょう。
また、万が一の事態を想定して、従業員にわかりやすいBCPマニュアルを配ることも大切です。
マニュアルを配布して教育を行っておけば、緊急事態でも適切な行動をとれる可能性が上がります。
全従業員がBCPへの理解を深めて最善の行動をとれるようになったときに、初めてBCPの効果を発揮できるでしょう。
BCPの策定にはゼンリンデータコムのArea Marker「危機管理・災害情報確認機能」が活用できる
BCPを策定する際にはツールの活用もご検討ください。
ゼンリンデータコムの「Area Marker」であれば、事前のリスク管理や従業員の安否確認機能が搭載されているので、有事の際に活用できます。
機能や特徴についてご紹介しますので、ぜひ導入をご検討ください。
機能や特徴
Area Markerは、企業向けのビジネスソリューションで複数の拠点でお店やオフィスを構えている企業におすすめのツールです。
自然災害が発生した際には自然災害の情報を地図画面でチェックでき、被害状況を集約できます。
複数の拠点に店舗やオフィスを構えている場合でも、災害懸念のある拠点を自動で抽出し、被害状況確認のメールも発信してくれるため、迅速な意思決定に役立つ機能です。
また、地震や台風、大雨といった災害が発生した際には、従業員の安否確認はもちろん、被害にあった拠点が事業継続可能な状態なのかについても確認が可能です。
報告は管理者画面で一覧を確認できるので便利です。
また、訓練メール機能も搭載されているので、災害に備えての訓練もArea Marker内で行えます。
さらに詳しい機能を知りたい場合は、資料請求やお問い合わせフォームにてご相談ください。
■1分で完了! 資料請求:https://www.zenrin-datacom.net/solution/areamarker/service/bcp/dl
導入事例と効果
エニタイムフィットネスを展開する株式会社Fast Fitness Japan様は全国47都道府県に店舗が点在しています。
災害が発生した際でも被災状況や安否確認を迅速に行えるよう、Area Markerを導入していただきました。
エニタイムフィットネスは直営店だけでも170店舗あり、フランチャイズを含めると1,100店舗以上を展開しています。※2023年10月時点の店舗数
これまでも別の安否確認システムをご利用になっていたそうですが、災害発生時に各店舗の状況が即座に確認できなかったり、従業員の転勤が多いため店舗との紐づけが難しい、安価に社員の安否確認と店舗の被災状況の両方を確認したいなどいくつも課題をお持ちでした。
そんな中でArea Markerの存在を知り、これまでと同様のコストで上記課題を解決できる点にメリットを感じたといいます。
詳しい導入事例に関しては、以下のリンクをチェックし、詳細をご確認ください。
まとめ:もしもの災害時のために、自社内のBCPを策定しておこう!
もしもの災害のために、自社内のBCPを作成しておきましょう。
災害や事故・事件等によって通常業務を遂行できなくなった際には、事業が停滞してしまいます。
いち早く事業を復旧させるためには、もしもの事態に備えたBCPの策定が必要です。
BCPを策定しておけば、優先して復旧させるべき事業や従業員がとるべき適切な行動を周知させられます。
BCPの作成は、事業の復旧スピードだけでなく、従業員の安心や企業の社会的信用を守ることにつながるため非常に重要です。
万が一の事態に備えてBCPを作成して、社内で周知させましょう。
災害時に役立つゼンリンデータコムの「Area Marker」もご活用ください!
全国各地に拠点をお持ちの企業様、拠点毎の災害リスクや安否確認等をまとめて管理できるゼンリンデータコムの「Area Marker」の活用もご検討ください。
「Area Marker」の危機管理・災害情報確認機能は、被災状況やリスクをリアルタイムに把握できるため、災害時の迅速かつ合理的な意思決定に役立てられます。
災害時には地図上で各拠点の被害状況を可視化することにより、拠点や従業員の安否を確認でき、迅速な状況判断が可能です。
BCP策定と共に「Area Marker」を活用して、従業員の安全確保と企業利益を守りましょう。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/