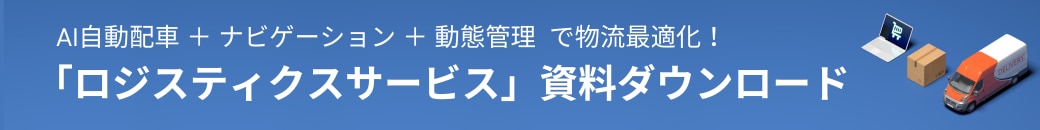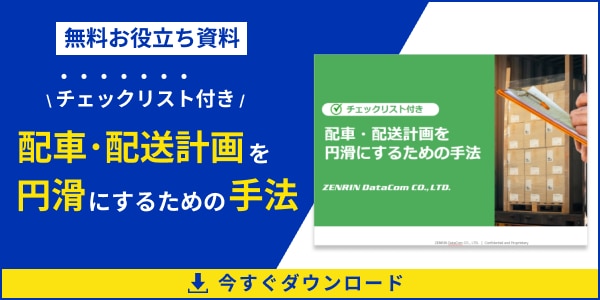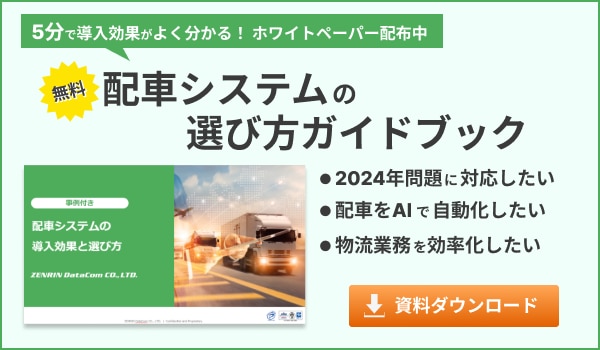物流DXとは?導入のメリットや課題、成功事例までわかりやすく解説
今後の物流業界を変革する手段として物流DXが注目されています。
2024年問題や働き方改革の推進等、深刻化する人手不足を課題に持つ物流業界において、物流DXは今後の物流業界にとって、なくてはならない施策です。
この記事では物流DX導入の背景や実際の施策について解説します。
物流の2024年問題にお困りですか?
「ロジスティクスサービス」ならAIによる自動配車で業務効率化!
⇒ロジスティクスサービスの資料を見てみたい
目次[非表示]
- 1.物流DXとは?
- 2.物流業界が抱えている課題
- 2.1.人手不足
- 2.2.環境問題
- 2.3.テクノロジーの導入
- 2.4.セキュリティの確保
- 2.5.2024年問題の対応
- 3.物流DXによって改善される点とは?
- 4.物流業界のDX推進において実施すべき取り組みとは?
- 4.1.IoTを活用したデータ収集と解析
- 4.2.ロボットやドローン技術の導入
- 4.3.AIによる配送ルート最適化
- 4.4.ブロックチェーン技術の活用
- 4.5.デジタルマーケティングの活用
- 5.物流DXを導入する3つのメリット
- 5.1.生産性向上による人手不足の解消
- 5.2.業務効率化によるコスト削減の実現
- 5.3.輸送品質と顧客満足度の向上
- 6.物流DX導入のデメリットと注意点
- 6.1.多額の初期費用と運用コストの発生
- 6.2.デジタル人材の不足と社内教育
- 6.3.システム導入に伴う一時的な業務の混乱
- 7.【企業別】物流DXの成功事例を紹介
- 8.物流DXの推進に活用できる補助金
- 8.1.中小企業省力化投資補助金
- 8.2.IT導入補助金
- 9.まとめ:物流DXによって物流業界に変革をもたらそう!
- 10.AIによる配送ルートの最適化なら「ロジスティクスサービス」がおすすめ!
物流DXとは?

物流DXとは、物流におけるDX化の施策のことをいいます。
DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略称です。
AIやIoT(Internet of Things)、ビッグデータ等のデジタル技術を用いた企業の業務改善や、ロボティクス技術、機械導入による効率化のことをいいます。
企業風土や業界における競争優位性に変革をもたらす取り組みともいえるでしょう。
DXは、機械化やデジタル化によりビジネスモデルの変革を図るという意味であるため、機械化・デジタル化・効率化と混同しないことが大切です。
機械化・デジタル化・効率化はあくまでDXの手段であることを認識しておく必要があります。
物流業界が抱えている課題

物流業界は今、さまざまな課題に直面しています。
人々の生活や企業のビジネスに必要不可欠な物流を、今後も安定して稼働させるためには物流企業だけではなく、物流を依頼する荷主企業側も課題に向き合い、対処する姿勢が必要です。
ここでは、物流業界が抱える主な課題を紹介します。
荷量の増加やドライバー不足にお困りではありませんか?
「ロジスティクスサービス」で物流物流DXを実現!
⇒資料のダウンロードはこちらから
人手不足
物流業界は人手不足が深刻化しています。
原因のひとつとしては、EC市場の成長による物流の多頻度化があげられるでしょう。
これまで店舗への手配で済んでいた物流が、一個人への手配に変わることで梱包や出荷作業の件数が増加し、輸配送の回数もルートも複雑化して人手が多く取られるからです。
もうひとつの理由としては、少子高齢化が進み、産業全体として働き手が不足していることです。
中でも物流業界の人手不足は深刻です。
全産業比で労働時間が2割近く長いことや、収入が約1割低いという就業環境も災いし、新たな働き手の確保が難航しているのです。
参考:厚生労働省|参考資料2 改善基準告示見直しについて(参考資料)
国土交通省|トラック運送業の現状等について
公益社団法人鉄道貨物協会によると、2028年度には約27.8万人のトラックドライバーの不足が予測されています。
参考:公益社団法人鉄道貨物協会|平成 30 年度 本部委員会報告書
環境問題
物流業界は環境問題にも配慮せねばなりません。
CO2の削減やカーボンニュートラル等、持続可能な社会の実現のためには、クリーンな物流を可能にする取り組みが必要になります。
とくに環境負荷が大きいのはトラック輸送です。
日本の物流を支えるトラック輸送ですが、未来に向けた取り組みとして、環境に配慮した車両導入という方法があります。
環境に配慮した車両とは、電気自動車や天然ガス車です。
ただし、導入費用のインパクトが大きいため、全体の99%を中小企業が担うトラック運送業にとって、一斉に導入を進めることは現実的ではありません。
また、物流はトラック輸送だけではなく、倉庫作業や荷役作業等も含みます。
そのため、トラックの積載率向上による輸送回数の削減や、鉄道や船舶へのモーダルシフト等、物流を広域に捉えた取り組みが必要です。
テクノロジーの導入
物流業界のテクノロジーの導入は進んでいるとはいえません。
物流業界において、テクノロジーは主にマテリアルハンドリング機器(マテハン:商品を管理・移動させる際に使う機器全般)に導入されます。
ITやテクノロジーの進化が著しい昨今ですが、物流のマテハン機器はまだまだ技術上の制約が多いのが現状です。
たとえば、
- 決まったレールの上でしか稼働しない無人搬送車
- 特定の倉庫でしか機能しない在庫管理システム
- 旧式のサーバーが残りデータの移行が困難
といった現場環境が挙げられます。
IT技術の進歩と相反して、アナログ管理に頼る物流現場では積極的なテクノロジーの導入に消極的といえるでしょう。
セキュリティの確保
物流は生活に欠かせないインフラです。
その性質上、安定的かつ持続的な維持が必要となります。
物流機能の管理や維持には「サプライチェーンマネジメント」が必要です。
サプライチェーンマネジメントは企業の生産活動において、調達から消費までの工程を一連管理する手法です。
このサプライチェーンマネジメントには情報管理が欠かせません。
生産量や在庫数、配達先等物流は情報を幅広く扱います。
これらの情報がIT障害等によって正しく機能しなかったり、サイバー攻撃等によって金銭の搾取や個人情報の抜き取り等の詐欺犯罪を助長したりすることのないよう、セキュリティーの確保が必要です。
物流業界はアナログでのデータ管理も多いことから、セキュリティの確保には課題が残っています。
2024年問題の対応
2024年から、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に設定され、トラックドライバーの働き方が変わります。
この制限によって発生するさまざまな問題が2024年問題です。
物流業界は全産業比で労働時間が約2割長く、賃金が約1割~2割低いといわれています。
新たな労働力確保のためには、働く環境の整備が必要です。
しかし、時間外労働時間の上限設定により、取り扱う物量が減少することが予想されるでしょう。
物流会社にとって、取り扱い物量の減少は売り上げや利益の減少につながります。
減少分の補填として、荷主企業は物流会社の変更や商品価格の値上げ等、対応方法を検討しなくてはなりません。
★関連記事
物流DXによって改善される点とは?

物流業界が抱える課題の解決策として注目されているのが、物流DXです。
このセクションでは、物流DXの取り組みや改善される点について解説します。
在庫管理の効率化
物流業務において在庫管理は欠かせません。
この在庫管理業務は、物流DXによっての効率化が期待できます。
これまでの在庫管理では、
- 人員工数がかかる
- 発注元ごとに管理方法が異なる
- 管理方法が担当者に属人化してしまう
といった課題がありました。
これらの課題の共通点は「アナログ管理」であることです。
人によって作業スピードや正確性が異なるアナログ管理をデジタル管理にすることで、在庫管理の効率化が図れるでしょう。
たとえば、これまでのバーコード管理から、電波などを用いた非接触型のRFIDタグを用いることで、ひとつひとつの商品をバーコードスキャナーに通すことなく在庫を一元管理することが可能になります。
また、特性の異なる商品を複数拠点で在庫管理する場合は、クラウドの導入が効果的です。
商品ごとに異なる在庫管理のルールを登録し、複数拠点で統一のシステムで管理することで、出荷都度の在庫管理を可能とします。
これらの取り組みによって、在庫管理をより正確に、かつ迅速に行うことが可能になるのです。
配送ルートの最適化
物流DXは配送ルートを最適化する効果もあります。
EC市場が急速に拡大する一方、トラックドライバーは不足しています。
限られたドライバー人数と就業時間の中、決められた時間帯に確実に商品を輸配送するためには、効率的な配送ルートの設計が必要でしょう。
物流DXにより輸配送データ(ビッグデータ)の活用やデジタル化することで、これまでアナログで管理していた配送ルートを最適化することが可能です。
また、物流センターや倉庫の在庫管理データと連携してトラック1台あたりの積載効率をあげることで、ムダのない配送ルートの設計が可能です。
倉庫内の自動化
物流DXによって、倉庫や物流センター内の自動化を実現できます。
倉庫や物流センターは「長時間労働・肉体労働・低賃金」という物流業界のイメージにより、人手の確保が難航しているのです。
しかし、物流DXによって倉庫内の自動化を実現できれば、働き方は大きく変わるでしょう。
たとえば、自動棚搬送ロボットの導入はピッキング作業の負担を軽減します。
また、自動仕分け機を出荷作業に導入することで、大量の貨物を迅速かつ正確に仕分けることが可能になるのです。
物流の品質強化
物流DXは物流業務の品質強化につながるでしょう。
物流の高度化や各工程の最適化を図るあらゆる戦略のことを、ロジスティクスと呼びます。
ロジスティクスは、企業の経営戦略のひとつともいわれています。
つまり、企業の経営戦略と物流戦略は一致している必要があるのです。
企業にとって、物流戦略に必要な要素のひとつといえるのが物流の品質強化でしょう。
物流の品質強化とは、物流の活動における質の高さのことです。
企業によって物流に求めるニーズは異なります。(例:コスト重視・スピード重視・荷物の取り扱い重視等)
ニーズに合わせた新技術の導入やデジタルの活用で、自社の戦略に合った物流の品質強化を図れるのです。
★関連記事
顧客との接点の強化
物流DXは、荷主企業である顧客と物流企業の接点を変えることができるといえるでしょう。
物流DXは物流企業だけではなく、顧客にも大きな影響を与えます。
物流DXは物流企業だけで成せる取り組みではなく、顧客の理解や協力も必要です。
また、人手不足や2024年問題は物流企業だけではなく社会全体の課題でもあります。
顧客にとって、運賃や物流作業費の値上げは自社の売り上げや利益を左右するのです。
一方、デジタル技術を活用した物流DXは、これまでの仕組みや習慣を見直すきっかけになります。
物流DXの推進は、物流をコストとして捉えるのではなく、物流を企業の成長戦略に位置づけ、顧客と物流企業の接点強化による事業推進も期待できるでしょう。
データ連携による情報管理の一元化
物流のプロセスには、荷主、物流事業者、配送先など多くの関係者が存在し、それぞれが個別のシステムで情報を管理していることが少なくありません。
物流DXは、これらのバラバラな情報をデジタル技術によって連携させ、一元管理を可能にします。
例えば、トラック予約受付システムを導入すれば、倉庫側とドライバー側でバース(トラックを停車させる場所)の空き情報を共有でき、長時間の待機問題を解消できます。
また、IoTセンサーを活用して輸送中の荷物の温度や衝撃をリアルタイムで監視し、トレーサビリティを確保することも可能です。
物流業界のDX推進において実施すべき取り組みとは?

テクノロジーの進化や新たな技術の台頭の中、物流業界のDXはどのように推進していけばいいのでしょうか。
このセクションでは、物流DXで実施すべき取り組みを紹介します。
ぜひ、今後の物流DX施策の参考にしてみてください。
IoTを活用したデータ収集と解析
IoTは、モノのインターネット化の略称です。
さまざまなモノがインターネットで接続され、それぞれが合理的かつ整合的に制御する仕組みのことをいいます。
このIoTによって、物流DXの取り組みを推進できます。
今や、多くの倉庫や物流センターで導入されているWMS(Wholehouse Management System)も、IoTの力であり、入出荷のデータや在庫データを商品に貼られたJANコードなどでデータ管理することで、モノを適切に管理できる技術です。
また、リアルタイムの交通情報やトラックの積載量、配送ルート等を解析したTMS(Transport Management System)もIoTのひとつといえるでしょう。
その日走行予定のトラックの車両データと配達予定時間を登録すれば自動的に配車業務を行うことが可能となり、トラックの機動性を高められるのです。
ロボットやドローン技術の導入
物流DXの取り組みとして、ロボットやドローンの活用もあります。
ロボットやドローンの活用は、物流業界の人手不足解消が期待されているのです。
物流業界では商品を届ける配送ロボットをはじめ、倉庫内で決められた商品を棚からピックアップするピッキングロボットや、段ボールを組み立て封入する梱包ロボットがあります。
これらのロボットをうまく活用することで、人がより高度かつ必要な業務に専念することが可能です。
また、ドローンは新しい配達手法として注目されています。
とくに、過疎化が進む地域や離島、山岳地帯といった道路交通網にハンディキャップのある地域への配達に、ドローンの活用が検討されているのです。
大手宅配企業での実証実験も進んでおり、本格的な導入が期待されています。
AIによる配送ルート最適化
配送ルートの最適化には、配車担当者の適切な采配が必要です。
これまでの配送ルートの設計や配車業務は、配車担当者の経験による判断力に委ねられていました。
配車には、顧客の繁忙期や閑散期の把握、商品の特徴理解、土地勘等あらゆる情報が必要です。
これらの情報と判断基準をAIに読み込ませ、システム上でプログラム化することにより、届け先の指定時間やトラックの空き時間等を合理的に組み合わせてムダのない配送を実現しています。
他にも、家庭の電力メーターの波動をAIに解析させ、解析データから在宅・不在を判断し、在宅中の家から配達に向かうことで不在配送を削減する取り組みも行われているのです。
■AI自動配車なら「ロジスティクスサービス」にお任せください!
⇒まずは資料を見てみる
ブロックチェーン技術の活用
ブロックチェーンとは各工程で管理していた情報を一連の情報として管理することを意味しており、仮想通貨に用いられている技術です。
この技術は煩雑で複雑な物流管理をスムーズにすることが期待されています。
サプライチェーンでいうと、原材料の調達、製造、在庫管理、配送、販売、消費といった工程がありますが、従来、それぞれの情報は各工程を担う企業しか扱えませんでした。
これではリアルタイムの情報交換ができず、数の整合性や配送状況の確認をスムーズに行えません。
これらの情報をブロックチェーンにのせることで、企業の垣根を越えてリアルタイムでモノの動きを把握することができ、一連の工程をスムーズに管理できるのです。
この技術は宅配ロボットのサービスにも使われています。
デジタルマーケティングの活用
デジタルマーケティングとは、デジタル媒体上のデータを用いた顧客との関係構築手法のことです。
物流にはデジタルマーケティングに活用できる多くのデータが蓄積されています。
たとえば、物流倉庫の在庫データや出荷データがあげられるでしょう。
荷主である企業にとって、多くの在庫を抱えない生産活動は魅力的です。
また、商品の特性に合わせた生産ラインの確率や入出荷体制を構築できれば、必要以上に人を雇用する必要もなくなります。
荷主企業が自ら持っている生産や販売のデータに、物流企業が持つ在庫や出荷のデータをかけ合わせれば、企業のサプライチェーン全体がデータ化されるのです。
導き出したデータを活用し、エンドユーザーの傾向に合わせたロジスティクスを構築することで、これまでのムダを省き、新たな販路の拡大やビジネスモデルの構築に役立てられるでしょう。
近年では物を運ぶだけではなく、データを用いたデジタルマーケティングで企業の物流をコンサルティングする物流企業も増えています。
物流DXを導入する3つのメリット

物流DXの導入は、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。
生産性向上による人手不足の解消
ロボットやマテハン機器(マテリアルハンドリング機器)の導入による作業の自動化、AIによる業務計画の最適化は、業務全体の生産性を飛躍的に向上させます。
これにより、少ない人数でも従来以上の業務量をこなすことが可能になり、深刻化する人手不足問題の解消に直接的に貢献します。
また、これまで人手に頼らざるを得なかった単純作業や力仕事から従業員を解放し、より付加価値の高い業務へ配置転換することも可能になります。
業務効率化によるコスト削減の実現
物流DXによる業務効率化は、様々な側面からコスト削減に繋がります。
配送ルートの最適化は走行距離を短縮し、燃料費を削減します。AIによる高精度な需要予測は、過剰在庫や欠品を防ぎ、在庫保管コストや機会損失を低減させます。
さらに、伝票のペーパーレス化は、用紙代や印刷代、保管スペースのコストを削減するだけでなく、入力作業や管理の手間も省きます。
改善される業務 |
コスト削減効果 |
配送業務 |
最適なルート算出による燃料費の削減 |
在庫管理 |
適正在庫の維持による保管コストや廃棄ロスの削減 |
事務作業 |
ペーパーレス化による消耗品費や人件費の削減 |
倉庫内作業 |
自動化による人件費の削減と作業ミスの防止 |
輸送品質と顧客満足度の向上
物流DXは、コストや効率だけでなく、サービスの品質向上にも大きく寄与します。
IoTセンサーなどで輸送状況をリアルタイムに追跡できるようにすることで、荷物が今どこにあるのか、いつ届くのかといった情報を顧客に正確に提供できます。
また、倉庫内でのピッキングミスや配送遅延が減少することで、誤出荷や納期遅れといったトラブルを防ぎ、安定したサービスを提供できるようになります。
こうした輸送品質の向上は、顧客からの信頼を高め、結果として顧客満足度の向上に繋がります。
物流DX導入のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、物流DXの導入には注意すべき点もあります。
事前にデメリットを理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。
多額の初期費用と運用コストの発生
物流DXを推進するためには、新しいシステムやロボット、センサーなどの導入が必要となり、多額の初期投資が伴います。
また、導入後もシステムの利用料やメンテナンス費用、アップデート費用といったランニングコストが継続的に発生します。
これらのコストを事前に正確に見積もり、投資対効果(ROI)を慎重に評価することが重要です。
補助金や助成金を活用することも、コスト負担を軽減する有効な手段となります。
デジタル人材の不足と社内教育
導入したデジタルツールやシステムを効果的に運用するためには、それを使いこなせる人材が不可欠です。
しかし、多くの企業ではITに精通した人材が不足しているのが現状です。
単にシステムを導入するだけでなく、従業員がスムーズに利用できるよう、研修やマニュアル整備といった社内教育の体制を整える必要があります。
操作が直感的で分かりやすいシステムを選んだり、導入後のサポートが手厚いベンダーを選定したりすることも重要です。
システム導入に伴う一時的な業務の混乱
新しいシステムの導入期には、操作に慣れていないことによる業務の停滞や、既存の業務フローとの連携がうまくいかないというような混乱が生じる可能性があります。
最悪の場合、一時的に生産性が低下したり、現場から反発が起きたりすることも考えられます。
こうした混乱を最小限に抑えるためには、導入の目的やメリットを従業員に丁寧に説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。
また、一部の部門からスモールスタートで導入し、課題を洗い出しながら段階的に対象範囲を広げていくアプローチも有効です。
【企業別】物流DXの成功事例を紹介
物流DXにおける企業の成功事例を紹介します。
物流企業における配送最適化システムの導入効果
物流業界において、配送効率化とコスト削減を実現するZENRIN ロジスティクスサービスの導入が進んでいます。
食料品店舗配送を行う企業では、配車計画システムの導入により22台から20台への車両削減を実現し、最適な配送ルートの自動計算が可能になりました。
また、雑貨の個人宅配を行う企業では、従来の属人化した配車作業から脱却し、システムが効率的なルートを計算することで車両台数を10台から7台に削減しています。
これらの事例では、配車計画の負荷軽減と正確な地図情報による配送精度向上が同時に実現され、物流業界のDX推進において大きな成果を上げています。
★関連記事
CBcloud株式会社におけるラストワンマイル配送の業務効率化
CBcloud株式会社では、軽貨物配送車マッチングプラットフォーム「PickGo」において、Google Maps PlatformとZNET TOWN mobileAPIを活用した配送業務のDX化を推進しています。
従来、配送ドライバーは紙の住宅地図にピンを書いて感覚と経験でルートを作成していましたが、同社の「SmaRyu Post」では自動ルート最適化により出発前の工程を数十分まで短縮することに成功しました。
さらに、住宅地図APIの導入により、配送先の近くからドアまでの細かい情報を提供し、ラストワンマイルの配送効率を大幅に向上させています。
こうしたITによる物流業界の変革により、配送を「コストセンター」から事業を後押しする「パワー」へと転換する取り組みが実現されています。
★関連記事
物流DXの推進に活用できる補助金
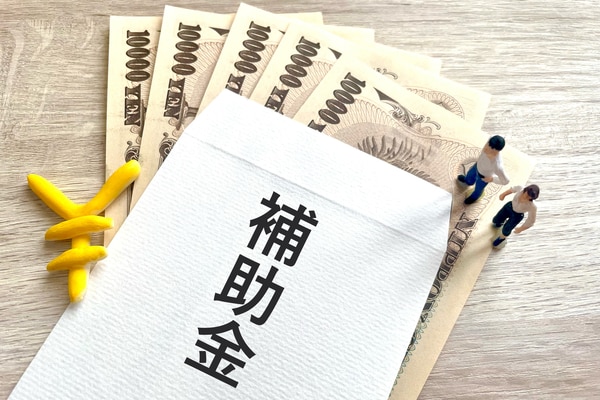
物流DXの導入にはコストがかかりますが、国や地方自治体が提供する補助金を活用することで、その負担を軽減できます。
ここでは代表的な補助金を紹介します。
中小企業省力化投資補助金
人手不足に悩む中小企業等に対し、IoTやロボット等の省力化設備の導入を支援する補助金です。
カタログに掲載された製品から選ぶ「カタログ注文型」と、個別の設備投資を支援する「一般型」があります。
カタログ注文型の補助額は従業員数によって異なり、最大1,000万円(従業員数21人以上の場合)となります。
なお、大幅な賃上げを行う場合は特例として最大1,500万円まで引き上げられます。一般型では最大1億円の補助が受けられる可能性があります。
物流分野では、自動倉庫、配送ロボット、検品・仕分けシステムなどの設備導入に活用でき、DXによる業務の自動化・効率化を目指す際に非常に有効です。
参考:
トップページ(一般型)|中小企業省力化投資補助金
カタログ注文型とは|中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービスなど)を導入する経費の一部を補助する制度です。
WMSやTMSといった物流管理システムの導入などに活用できます。
通常枠では最大450万円(補助率1/2)の補助が受けられますが、最低賃金近傍の従業員を全従業員の30%以上雇用している場合は補助率が2/3に引き上げられます。
このほか、インボイス枠や複数社連携IT導入枠など複数の申請枠があり、それぞれ補助額や補助率が異なります。
実際に複数のWMSやTMSがIT導入補助金の対象ツールとして認定されており、業務効率化やデータ活用を目的としたツール導入の際に利用を検討すべき補助金です。
※補助金の情報は変更される可能性があるため、必ず公募要領等の公式情報を確認してください。
参考:
サービス等生産性向上IT導入支援事業 『IT導入補助金2025』の概要
通常枠 | IT導入補助金2025
トップページ | IT導入補助金2025
まとめ:物流DXによって物流業界に変革をもたらそう!
物流業界ではまだまだDX化が進んでおらず、デジタルや新技術の導入による改善が必要です。
言い換えると、物流DXの推進により、改善や改革ができる領域やサービスは沢山あり、実現すれば物流業界の働き方だけではなく、人々の生活もより利便性が高まります。
物流DXは、物流のすべてを機械化、デジタル化するわけではありません。
現在、アナログで行っている業務も、必要な場合は残していきましょう。
アナログに頼り過ぎず、デジタルと融合することで、より正確かつ効率的な物流を実現できるのです。
AIによる配送ルートの最適化なら「ロジスティクスサービス」がおすすめ!
ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」は、企業の物流DXを後押しします。
「ロジスティクスサービス」では、高い技術力で設計されたナビゲーションシステムや、地図活用によるソリューション提供といったノウハウを用いて、お客様の物流課題を解決に導くことが可能です。
- AIによる複雑な配車業務の最適化
- 輸配送ルートの最適化を図るナビゲーションアプリ
- 車両の位置や走行距離の管理を可能とする車両動態管理システム
物流の効率化を実現するツールとノウハウの提供が可能です。
ぜひ、「ロジスティクスサービス」を物流DXの推進と物流のさらなる効率化にお役立てください。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/