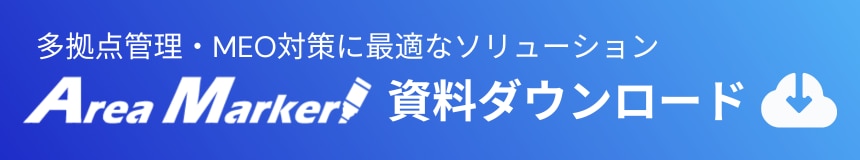災害時のリスクマネジメントとは? BCP作成のポイントも紹介
「災害が起きた際のリスクヘッジをしたい」
「災害時の対策は何をするべき?」
など、災害時のリスクマネジメントで悩んでいませんか?
地震大国と言われる日本ですが、近年台風や豪雨などの自然災害に見舞われるケースも増加し、より一層企業による災害時のリスクマネジメントが必要になっています。
企業の業績や従業員の安全を確保するために、災害が発生したときの対処法をあらかじめ考慮しておくことが大切です。
この記事では、災害時のリスクマネジメントについて、詳しく解説します。
BCP作成ポイントもあわせて紹介しますので、最後まで読んで参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.災害時のリスクマネジメントが必要な理由
- 1.1.風水害によるリスクが大きいため
- 1.2.震災によるリスクが大きいため
- 1.3.業務を運営できなくなる可能性があるため
- 1.4.従業員が被災するリスクがあるため
- 2.災害により生じる可能性のあるリスクを分析
- 2.1.設備・機器の損傷・水没
- 2.2.インフラの供給停止
- 2.3.指揮系統の低迷
- 2.4.従業員の被災による人員不足
- 2.5.取引先が被災
- 3.災害に備えた具体的な対策
- 3.1.避難場所・危険区域を周知させる
- 3.2.備蓄品を確保する
- 3.3.機材や設備に転倒防止処置を施す
- 3.4.データのバックアップを取る
- 3.5.BCP・防災マニュアルの作成
- 4.災害リスクマネジメントにBCPが必要な理由とは?
- 5.BCP作成のポイント
- 5.1.基本方針を定める
- 5.2.リスクと被害を想定する
- 5.3.社内に周知・訓練させる
- 6.まとめ:BCPを作成して災害時のリスクマネジメントを行おう
- 7.企業の危機管理にゼンリンデータコムの「Area Marker」をご活用ください!
災害時のリスクマネジメントが必要な理由

「災害時のリスクマネジメントは、必要なのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
企業が活動を続ける上で、災害時のリスクマネジメントは必要不可欠です。
「なぜリスクマネジメントを行うのか?」という問いに対して、リスクマネジメントが必要な理由を詳しく解説します。
風水害によるリスクが大きいため
周囲を海に囲まれた島国である日本では、津波や台風による風水害が多く発生します。
とくに毎年発生する台風被害は大きく、対策を講じなければ危険です。
海辺近くの事業所や店舗では浸水リスクもあり、台風・津波発生時のリスクマネジメントが求められます。
万が一、事業所や店舗が浸水した場合は、機材やデータの破損、商品が水浸しになり販売できなくなるリスクが高くなります。
また事業所や店舗が復旧するまでの期間、業務が停止するため業績悪化につながりかねません。
震災によるリスクが大きいため
今後も南海トラフ巨大地震が起きると予想されており、万が一の事態に備えて耐震性能の強化や震災時の対応を講じておかなければいけません。
震災が起きたときの状況を考慮して、避難訓練や物資の調達・連絡手段の共有を徹底しておくことが重要です。
いつ大震災が起きても対応できるよう、震災時のリスクマネジメントを強化しましょう。
業務を運営できなくなる可能性があるため
風水害や震災など災害が発生すると、建物や機材が破損して通常業務を遂行できなくなる可能性があります。
また、災害により従業員の私生活に被害が生じると、出勤ができなくなり通常業務を行う人材が不足します。
自社の事業所や従業員に影響が出なくても、取引先や顧客に被害が生じれば、通常通りの業務が行えません。
災害は業務停止のリスクが生じることを考慮して、リスクマネジメントを徹底する必要があります。
従業員が被災するリスクがあるため
従業員の業務中や通勤中に災害が発生するリスクも考慮しておかなければなりません。
震災や風水害が発生した時に備えて、避難訓練や備品の補充・連絡手段の共有などを行っておきましょう。
従業員が被災すれば、業務を行うことができず、場合によっては貴重な人材を失う事態に発展する可能性があります。
災害時のリスクマネジメントを強化して、従業員の身の安全を守る対策を講じておきましょう。
災害により生じる可能性のあるリスクを分析

リスクマネジメントを強化するためには、災害時のリスク分析が重要です。
「災害が発生することにより、どのような被害が生じるのか?」リスクを分析しなければ対策を講じられません。
災害により生じる可能性があるリスクを分析して、対策をしておきましょう。
設備・機器の損傷・水没
震災や水害が起きることで、設備や機材が損傷したり商品が水没したりするリスクが生じます。
地震が起きた際には、物の落下や建物崩壊などによる設備や機器の損傷が生じる可能性もあります。
また、大雨や津波で事業所や設備が水没すると、漏電やデータ破損のリスクも発生します。
設備や機器の損傷による火災の発生や水没によるデータの破損など二次災害も防止しなければいけません。
そのため、災害時のリスクマネジメントとして、日頃から震災対策・浸水対策を徹底しておくことが大切です。
インフラの供給停止
災害によって電気・ガス・水道などのインフラが供給されなくなることでも、業務が停止して生産がストップしてしまいます。
また、従業員の私生活にも影響を及ぼすため、仕事どころではなくなり出勤できなくなる方も現れるでしょう。
電車通勤をしている従業員は、交通インフラが停止すると出勤ができません。
無理に徒歩や自転車で通勤すると、二次災害に巻き込まれるリスクがあるため、自宅待機を命じなければいけなくなるでしょう。
中には業務中に被災してしまい、会社から動けなくなってしまう従業員も現れることも想定されます。
万が一の事態に備えて、予備電力や貯水タンクなどを準備し最低限のインフラを確保しておきましょう。
指揮系統の低迷
災害が起きると、指揮系統が低迷して連携が取りづらくなります。
風水害や震災が起きてインフラが停止すると、連絡を取れず安否確認が難しい状況に陥ります。
上司からの連絡が途切れて「仕事を放っておいていいのか?」「誰が指揮を執るべきか?」など、指揮系統が崩壊すれば混乱が生じて危険です。
このような事態に備えて「災害時にはどのポジションの人が指揮を執るべきか」「災害時の連絡手段をどうするか」を社内で共有して周知させましょう。
連絡が取れなくなった際の対処法として、安否確認システムの充実は大切です。
従業員の被災による人員不足
災害が発生すると、従業員が被災して人材不足に陥ることが考えられます。
設備や機器が無事でも、従業員が被災すると業務が円滑に進みません。
人材不足に陥った企業は、生産性が低下して業績が悪化してしまいます。
災害時のリスクマネジメントとして、従業員の身の安全を第一に考えることが重要です。
避難経路を充実させ、災害に備えた設備の強化が求められます。
従業員を被災させないためにも、職場内のリスクマネジメントが必要です。
取引先が被災
災害による影響は社内だけに留まりません。
社内の設備や従業員が無事でも、取引先が被災し仕入れが止まる、取引先の被害状況がそもそも分からないなど業務に支障が出るケースがあります。。
取引先が被災するという可能性に備えて、有事の情報連携の確認や代替えの仕入れ先の選定を行っておくなど、業務を停滞させない対策を講じましょう。
災害発生時には自社だけでなく、取引先や顧客が受ける被害についてもリスクを考慮することが必要です。
災害に備えた具体的な対策

災害が発生した際に、具体的にどのような対策を行うべきか対策案を充実させましょう。
対策案を講じるだけでなく、社内で共有することも重要です。
万が一、災害が発生した際に従業員一人ひとりが自分で対策を行えるよう、具体的な対策案を周知させましょう。
避難場所・危険区域を周知させる
災害が起きた時に備えて、避難場所・危険区域を周知させてください。
ハザードマップを活用して、震災発生時や水害時の危険区域を事前に把握しておく必要があります。
避難場所として、危険区域を回避できる安全区域を指定して、従業員に周知させることも大切です。
業務中に災害が起きた場合、従業員それぞれが避難場所に来られるよう定期的に避難訓練を実施しましょう。
避難訓練を徹底して、災害時の行動をマニュアル化しておくと、従業員の安全を確保するのに役立つ可能性があります。
備蓄品を確保する
リスクマネジメントとして災害発生時に備えた備蓄品を確保しておきましょう。
備蓄品には蓄電池やガスボンベ、貯水タンクなどの予備インフラをはじめ、水や食料などの物資、毛布など暖を取れるものを揃えておくことが大切です。
大地震が発生し事業所で避難することを想定して、数日間生活できる備蓄品を確保できていれば安心です。
備蓄品の補充は定期的に行い、管理場所を従業員に周知させておくと、災害時にスムーズな対応ができます。
機材や設備に転倒防止処置を施す
機材や設備の転倒防止処置を施しておくと、リスクマネジメントとになります。
機材や設備が転倒すると、破損や故障のリスクだけでなく従業員が怪我をする可能性があります。
また、高額な機材が破損すれば損害が大きく、復旧まで業務を停止せざるをえません。
浸水リスクが高いエリアでは、同様に水害対策も施しておくと安心です。
データのバックアップを取る
災害が発生すると機材や設備が損壊・浸水して、重要なデータが破損する可能性があります。
データが破損すれば、顧客データや企業データなどの重要な情報を失います。
万が一、災害が発生した時に備えて、データのバックアップや保管場所について検討しておきましょう。
書面のデータは失う可能性が高い有限資材なので、Webデータに移行して持ち運べる状態にしておくことが重要です。
ASPやクラウドなどのオンライン上にデータを保管しておけば、どこからでもバックアップデータを引き出せるため安心です。
バックアップは定期的に取り、いつ災害が発生してもデータを保護できる状態にしておいてください。
BCP・防災マニュアルの作成
災害が発生した時の対応や連携を周知させるため、BCP・防災マニュアルを作成しましょう。
BCPとは「事業継続計画」を指し、災害発生時に企業の損害を最小限に抑える計画書のことです。
災害が起きた際に事業を存続させるマニュアルを作成し、「中核事業」や「有事の対応」について社内に周知させることがリスクマネジメントで求められます。
事業を存続させるBCPと共に防災マニュアルを作成して、災害時の対策法を視覚化しておきましょう。
BCP・防災マニュアルは従業員が常に確認できるよう、また有事にどこからでも確認できるようwebデータとして保管・共有しておくことが大切です。
災害リスクマネジメントにBCPが必要な理由とは?

災害リスクマネジメントを考案する際に、BCPの作成が求められます。
BCPを作成する際には「なぜBCPが必要になるのか?」という作成理由を明確化しておくことが重要です。
理由も分からずにBCPを作成しても、形だけのマニュアルとなり効果が弱くなります。
災害リスクマネジメントに必要なBCPの作成理由を把握して、被害を最小限に抑えましょう。
従業員を守るため
BCP作成の理由は、従業員の身の安全を守るためです。
BCPには企業の事業計画存続以外にも、避難経路の確保や従業員の連絡手段を計画するなど、従業員の安全を考慮したプログラムが組み込まれます。
企業の発展・存続は従業員あってのものなので、まずは従業員の身の安全を確保することが最優先事項です。
BCPを作成して、従業員の身の安全を守ることができれば、事業をいち早く復旧させ存続させられます。
企業を守るため
BCPの目的は、あくまで「災害時に事業を存続させて企業の業績を守る」ことです。
災害の影響を受け、事業が存続できなくなれば最悪の場合倒産してしまいます。
BCPを作成しておかなければ、万が一災害が起きた事態に対して、対応ができません。
逆に、BCPを作成しておくことで、災害時の社内対応や取引先との連携手順が明確になり、早急な事業復旧を可能にします。
企業を守るために、BCPを作成して業績低下を未然に防ぎましょう。
二次被害を防ぐため
災害が発生すると漏電による火災や、設備破損による業務停止など二次被害が発生します。
BCPを作成しておくと、従業員の安全を確保して事業の早期復旧が期待できるため、二次被害を防げます。
BCP作成のポイント

BCPを作成する際には、次の3つのポイントが重要になります。
それぞれのポイントを抑えて、災害リスクマネジメントを徹底してください。
基本方針を定める
BCPを作成する際には、基本方針を定めることが重要です。
「いつまでにどの程度復旧させるのか」「何を重要項目としてBCPを作成するのか」という基本方針を定めなければ、BCPを作成できません。
作成する目的と目標、優先順位を社内で協議してBCPの基本方針を定めましょう。
またBCPの基本方針には、社内だけでなく顧客や取引先への影響を考慮しなければいけません。
顧客や取引先に影響を及ぼさない早期復旧が企業には求められます。
しかし、災害時には希望通りの復旧が難しい場合もあるので、復旧が遅れるケースも想定してBCPを作成しなければいけません。
BCPを作成する前に、目標と目的を考慮した基本方針を定めましょう。
リスクと被害を想定する
BCPを作成する際には、リスクと被害を想定しなければいけません。
震災や風水害・火災など、災害によって生じる被害はさまざまです。
リスクと被害を想定して、どのような対策が必要なのか具体策を考案しましょう。
災害時に想定されるリスク・被害は、次のようなものが考えられます。
- 地震や風水害など自然災害
- 火災被害
- ウイルスによる社内の集団感染
- 機械の操作ミスや通信障害などオペレーションリスク
- 重要情報や個人情報の紛失・漏洩など情報セキュリティリスク
災害の種類によって、考案すべき対策は異なります。
どのような災害が発生しても従業員と企業を守れるよう、リスク・被害の想定をしておきましょう。
社内に周知・訓練させる
どれだけ優れたBCPを作成しても、社内の従業員が認知していなければ意味がありません。
社内に周知させるだけでなく、マニュアル化して可視化できることも大切です。
また、マニュアルを熟読するだけでなく避難経路やBCPを用いた対策訓練を行い、災害発生時の対応を教育しましょう。
定期的な訓練を行うことで、災害が発生した際にスムーズに対応ができますし、問題点の発見や対策の抜け漏れに気づくことができます。
BCPは作成するだけでなく、社内に周知・訓練させ、ブラッシュアップしていくことが重要なのです。
まとめ:BCPを作成して災害時のリスクマネジメントを行おう
災害時のリスクマネジメントには、BCPを作成して社内で周知させましょう。
BCPは従業員と企業を守るために必要な、災害発生時の対策マニュアルです。
地震や風水害が多い日本では、企業を存続させるためのリスクマネジメントが重要になります。
万が一、災害が起きた際にいち早く復旧できるようBCPの作成は欠かせません。
災害時に柔軟な対応ができるようリスクマネジメントを行うことが、企業存続につながります。
企業の危機管理にゼンリンデータコムの「Area Marker」をご活用ください!
ゼンリンデータコムの企業情報一元管理サービス「Area Marker」にはBCPに特化した機能がございます。
ゼンリングループならではの高精度な地図データを活かして、気象情報や自然災害の情報を重畳させ全国各地に散らばる拠点や店舗毎にアラートの発報や災害状況の可視化が可能です。
また洪水ハザードマップを活用すれば、あらかじめ危険区域を確認して自社店舗の災害リスクを把握することも可能。
アラート発報の基準も定めることができるため、拠点ごとに判断することなく対応を統一化できます。
複数拠点をお持ちで危機管理ツールをお探しの企業様は、ぜひ「Area Marker」の活用をご検討ください。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/