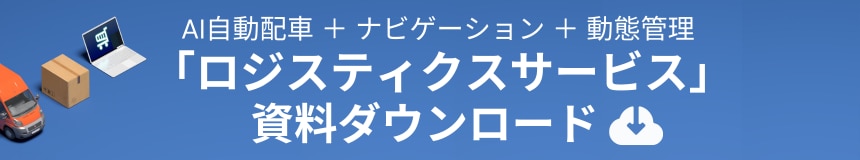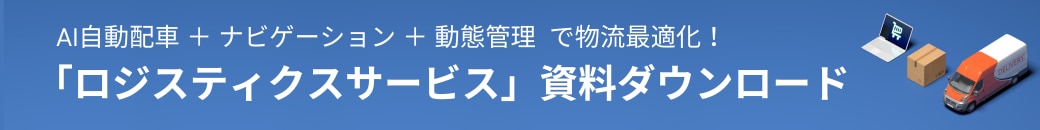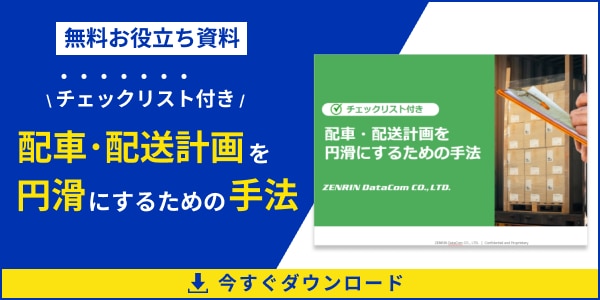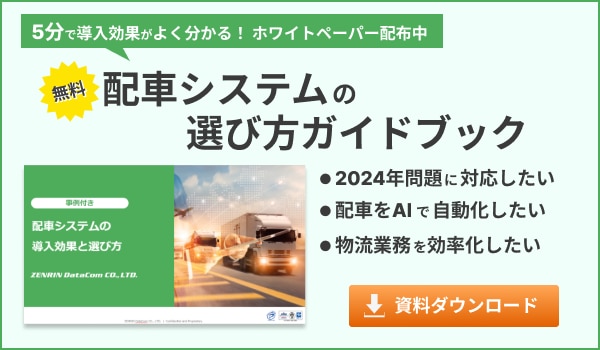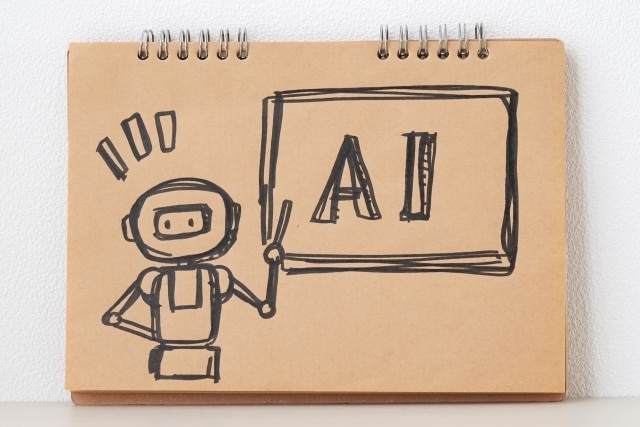
物流システムとは?種類や導入するメリット・注意点を解説!
人手不足や高齢化等の課題が顕著な物流業界。
一方、ロボット技術の進歩や、IT化・DX化等により、急速なデジタル化が進んでいることもまた事実です。
この記事では、物流の各工程を最適化するあらゆる物流システムについて解説します。
■物流システムの導入にお悩みですか?
ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」が物流業務を改善します。
⇒ 資料を見てみる
目次[非表示]
- 1.物流システムとは
- 2.物流システムの種類と改善できる業務内容
- 2.1.運行管理システム
- 2.1.1.改善できる具体的な業務内容
- 2.2.配送管理システム(TMS)
- 2.2.1.改善できる具体的な業務内容
- 2.3.倉庫管理システム(WMS)
- 2.3.1.改善できる具体的な業務内容
- 2.4.貨物追跡システム
- 2.4.1.改善できる具体的な業務内容
- 2.5.電子データ交換(EDI)
- 2.5.1.改善できる具体的な業務内容
- 2.6.物流ロボットシステム
- 2.6.1.改善できる具体的な業務内容
- 2.7.ピッキングシステム
- 2.7.1.改善できる具体的な業務内容
- 3.物流システムを導入する4つのメリット
- 3.1.業務の効率化やコスト削減が可能
- 3.2.リアルタイムに在庫状況や車両状況を管理できる
- 3.3.人為的ミスを防げる
- 3.4.顧客満足度の向上につながる
- 4.物流システムを導入する際の3つの注意点
- 4.1.導入には時間やコストがかかる
- 4.2.導入して改善したい課題をはっきりさせておく
- 4.3.既存システムとの適合性を確認しておく
- 5.物流システムを選ぶ際の6つのポイント
- 5.1.改善したい課題に応じて選ぶ
- 5.2.物流システムの導入タイプで選ぶ
- 5.3.使いやすいものを選ぶ
- 5.4.自社の業界で選ぶ
- 5.5.拡張性の高いものを選ぶ
- 5.6.既存システムとの連携性で選ぶ
- 5.7.セキュリティや信頼性で選ぶ
- 6.物流システム導入による成功事例
- 6.1.成功事例① 属人化と赤字運行の防止
- 6.2.成功事例② ラストワンマイルの効率化
- 7.まとめ:自社の悩みにマッチした物流システムを導入し、業務効率を改善しよう!
- 8.物流業務の改善に! ロジスティクスサービス
物流システムとは

物流システムとは、製品や資材の移動、保管、荷役、包装、流通加工といった一連の物流工程を効率的に管理するための仕組みです。
このシステムは、製品が製造者から消費者までスムーズに移動することを可能にし、企業の効率と生産性を向上させます。
具体的には、輸送ルートの最適化、在庫管理、データ分析等を行い、正確な配送を確保しながらコストを削減することが可能です。
物流業務の最適化には物流システムの導入がおすすめ
今や物流は、経営戦略の一部ともいわれています。
物流を制する者はビジネスを制す、という言葉もあるほど、物流のあり方次第で企業の売り上げや利益は大きく変動するのです。
物流システムの導入は、輸送・保管・荷役・梱包・流通加工の各機能の最適化に活用できます。
アナログ管理から脱却し、デジタルの力で効率的かつ効果的な物流管理を実現しましょう。
■AI自動配車やナビゲーションアプリなどで、物流業務を改善しませんか?
⇒「ロジスティクスサービス」の 資料を見てみる
物流システムの種類と改善できる業務内容

物流システムは、さまざまな工程で用いることが可能です。
物流の最適化や戦略的なサプライチェーンマネジメントを実現している企業は、あらゆる場面で物流システムを導入しています。
以下で物流システムの種類と活用できるシーンを記載していますので、自社の物流課題に合わせて、導入を検討してみてください。
運行管理システム
輸配送に関わる車両を管理する物流システムを「運行管理システム」といいます。
物流の要である運送や輸送において、運行管理システムの導入が有効です。
ドライバー不足や燃料費高騰の影響により、今後、更なる効率化を図らねばならないと感じている運送業者や物流会社も多いのではないでしょうか。
運送管理の工程に運行管理システムを導入することで、効率的な輸配送の実現だけではなく、ドライバーの働く環境整備や、ムダな工程を省き就業時間を最大限使うことも期待できます。
運送管理でシステムを導入することで改善できる具体的な業務内容は、以下のとおりです。
改善できる具体的な業務内容
運行管理システムは輸配送を指揮する本部と、実際に現場で輸配送を担うトラックドライバーや車両をつなぎ合わせるシステムです。
具体的な機能として、GPSの位置情報を用いて渋滞を考慮したルートの最適化や、リアルタイムで車両の位置を把握することにより、集荷や納品の往来を円滑に行い、車両の稼働率を向上させることが可能です。
また、運行管理システムの導入により、ドライバーの安全も守れます。
法定速度を始めとする交通ルールの遵守をしているかチェックしたり、車両データを分析することで、急発進や急加速等、事故につながりかねない運転を可視化し、ドライバーにフィードバックしたりすることで、ドライバーの品質向上にも寄与できるのです。
ほかにも、運転管理簿等、帳票の作成も自動化できるシステムもあり、ドライバーの業務負担軽減が図れます。
配送管理システム(TMS)
配送管理システムは、出荷から配送までの工程を管理するためのシステムで、トラックの配車に役立てられます。
自社の貴重な戦力であるトラックドライバーやトラック車両の効率的な活用は、2024年問題の影響とその対策が急務である運送会社や物流会社にとって、最優先に取り組むべきテーマといえるでしょう。
関連記事:物流業界に迫る「2024年問題」|問題の焦点と乗り切る手段とは? | 株式会社ゼンリンデータコム (zenrin-datacom.net)
配送管理システムができる具体的な業務内容は以下のとおりです。
改善できる具体的な業務内容
配送と一言にいっても、商品の特徴によって運び方や用意すべき車両のタイプ、道路交通法上のルール等、制約はさまざまです。
そんな場合でも、配送管理システムを導入すれば、商品の特徴に合わせて、品質を損なうことなく最適な配車を行うことが可能です。
とくに、取り扱いがセンシティブな商品の配送に効果があります。
たとえば、食品や薬品は運送時も温度管理が必要です。
配送管理システムの導入により、輸送に要する時間を想定し、受け手側と連携することでコールドチェーン※を途絶えさせることなく、輸送と保管を接続させられます。
また、運行管理システムと重複しますが、トラックの空き状況や位置情報をリアルタイムで共有することにより、配車の手間を削減することも可能です。
納品予定時刻や、休憩のタイミング等も把握できるため、より確実な配車が行えるでしょう。
※コールドチェーンとは生産、輸送、販売、消費までの過程で適切な低温(冷蔵、冷凍など)に保ったまま流通させる物流方式のことを指す
倉庫管理システム(WMS)
倉庫の在庫管理業務も、物流システムの力なくしては成立しません。
代表的なシステムがWMS(Warehouse Management System)です。
物流会社が顧客のニーズや商品の特徴に応じて提供しているため、種類は多岐に渡ります。
WMSの導入で効率化できる業務内容は以下のとおりです。
改善できる具体的な業務内容
倉庫管理、在庫管理業務を担うにあたり、最重要のポイントは「リアルタイムでの在庫管理」です。
ECビジネスを始めとする無店舗型の購買形態が増えたこと、トレンドの移り変わりが速いこと等から、商品を供給する企業は物流の多頻度化・小ロット化が加速しており、物流企業は対応に迫られています。
それら市場のニーズに的確に応えるためには、適切な在庫管理により商品供給の基盤を整えなければなりません。
また、在庫=企業の資産 になります。
適切な在庫量や在庫の回転率等をシステムで把握することは、企業資産を適切に扱うことにつながります。
倉庫や物流センターといった物流現場のみで管理するのではなく、本社機能と連動させることで、自社のサプライチェーン最適化に大きく貢献できるでしょう。
貨物追跡システム
貨物追跡システムは出荷した貨物の状況をトラッキングし、貨物の所在や状況を伝えるシステムです。
遅延や紛失といった物流リスクの軽減だけではなく、顧客満足度を高める重要な物流システムのひとつです。
貨物追跡システムの導入でできることの例を以下で紹介します。
改善できる具体的な業務内容
貨物追跡システムを導入して送り状に貨物固有の番号を付与すれば、その番号を読み取ることで貨物情報を追跡することが可能です。
元来、貨物追跡システムは物流業・運送業の業務品質向上のために導入されたものですが、現在では購入者や委託元の商品の適切な管理や、物流改善のひとつとして扱われています。
さらに貨物追跡は顧客の満足度向上にも影響するシステムです。
ECサイトで商品を購入した際、消費者は少なからず「いつ到着するのか」という不安を感じます。
それに対し、発送→輸送→配送→到着と確実なトレースができ、購入者が荷物が今どこにあるのか確認することができれば、安心して荷物を待つことができるでしょう。
海外からの越境ECも注目されている時代なので、海外からも追跡ができる様な物流システムを構築し、自社の販売ビジネスと連動させることができれば、顧客である消費者の満足度向上にもつながり、リピーター戦略にも良い影響を及ぼすはずです。
電子データ交換(EDI)
EDIとはElectronic Data Interchangeの略称です。
日本語では、電子データ交換を意味します。
企業間での契約書や納品書等の帳票類を電子化する物流システムです。
物流改善にどの様な効果をもたらすか、以下で説明します。
改善できる具体的な業務内容
アナログの物流管理には在庫表や納品書、委託元と物流会社との契約書等、紙の帳票管理がつきものです。
しかし、紙面の管理場所の問題、紛失の懸念、契約の交付にかかる時間等、紙ならではの注意点がありました。
デジタル技術が進む昨今、物流管理においても諸業務が電子化しています。
契約書も電子契約に切り替えることで、セキュリティに配慮しつつ、システム上で管理できることにより契約更新の漏れ等リスクヘッジが可能になるのです。
また、EDIはデータを自動送信できるという特徴もあります。
そのため、帳票の入出力も自動化でき、業務の効率化につながるでしょう。
物流ロボットシステム
人手不足が課題とされる物流業界で注目されているのが物流ロボットシステムです。
物流ロボットとは、物流における簡単な業務、例えば「ピッキング業務」や「仕分け業務」を自動で行うことができるロボットです。
人ではなくロボットに作業担当者を置き換えることで期待できる効果を説明します。
改善できる具体的な業務内容
物流センターや倉庫といった物流現場では、商品の棚入れやピッキング(棚から取り出す作業)が発生します。
従来、この作業に多くの人を要し、倉庫内には多くの作業者が必要でした。
人ならではの作業の丁寧さ等のメリットがある一方、「作業者によって早さが異なる」「人為的ミスが免れない」等、業務品質面での課題や注意点が課題だったのも事実です。
そんな中、近年では、物流作業を人の力とロボット技術の融合で最適化する流れが本格化しています。
AGV(Automated Guided Vehicle)は、商品棚まで自走し、作業者が商品を取ってから出荷場まで搬送してくれますし、GTP(Goods To Person)は商品棚そのものが作業者の元まで移動し、対象の商品の出荷作業をサポートしてくれます。
ほかにも、自動梱包機の技術も発展してきており、作業者の人数削減や、倉庫内での歩行距離減による疲労軽減、担当作業の軽減による集中力の維持等、職場環境の最適化にも期待が持てるでしょう。
ピッキングシステム
物流作業の中で欠かせないのがピッキング(商品を棚から探し集める作業)です。
人為的なミスが発生しやすく、小さなミスが大きな業務事故につながるケースもあるので、管理者側も作業者側も十分な注意が必要な作業です。
その作業にピッキングシステムを導入することで、改善できる業務内容例を紹介します。
改善できる具体的な業務内容
ピッキングシステムの導入に効果的な現場のひとつとして、工場物流が挙げられます。
製品の部品を保管し、ラインに沿って組み立てが行なわれる工場物流ですが、手作業でのピッキングでは、長時間の単純作業による疲労の影響で人為的なミスが発生しやすく、納期遅れや最悪の場合商品のリコール等、企業の経営に直結する悪影響を与える可能性があります。
そんな場合にピッキングシステムを導入することで、ピッキングする商品の陳列棚の位置が簡単にわかったり、システムによってはピッキング自体を自動で行ってくれたりするため、業務の効率化が可能です。
また、作業者の負担を軽減するだけではなく、人が担うべき業務に労働力を集中させることにより、生産性の向上や業務品質の向上も図れます。
これら作業一つひとつの品質の安定化は、その商品を手にする顧客の満足度向上にもつながります。
物流システムを導入する4つのメリット

物流システムの導入には、主に4つのメリットがあります。
業務の効率化やコスト削減が可能
物流システムは、業務の効率化やコスト削減を実現します。
元来、人が担っていた業務の中でも単純作業(棚入れやピッキング等)や低作業領域は、デジタルの力に頼る方が品質が高く、かつ所要時間も短縮できるケースが多いとされます。
そのため、システムを導入することで、人員の最適化や倉庫稼働時間の短縮等、コスト削減にもつながるでしょう。
リアルタイムに在庫状況や車両状況を管理できる
物流システムの導入により、リアルタイムの物流状況を管理できます。
商品を最少ロットで必要な現場に供給することで在庫の最適化を図ったり、トラックやトラックドライバーの位置情報を用いて効率的に配送設計を計画したりすることは、貴重な輸送リソースを最大限有効に活用するための手だてとなります。
人為的ミスを防げる
物流システムの導入は、人ならではのミスを防ぐことにもつながります。
連続して同じ作業をすることで起きてしまう集中力の低下や、在庫を探し回って倉庫内を歩くことで発生する疲労等、物流作業における人為的ミスの要因はいたるところに散見されます。
これらの作業の一部を物流システムに置き換えることで、人為的ミスのリスク軽減になるのです。
顧客満足度の向上につながる
顧客満足度の向上につながる点も、物流システムを導入するメリットです。
世の中の商品は、消費者である顧客の手に渡って初めて価値を生みます。
また、手に渡った時の状態や、手に渡るまでの早さ、時間の融通、届け方等、さまざまな物流の要素が商品自体に付加価値を与えることはいうまでもありません。
物流システムの導入で物流品質を向上させることは、商品自体の価値を最大限に引き出すことを意味します。
商品の価値最大化は顧客の満足度を高め、リピーターの獲得や新市場の開拓等、企業の経営を後押しすることにつながるでしょう。
物流システムを導入する際の3つの注意点

一方、物流システムの導入には注意点もあります。
自社の状況に鑑みて、導入の必要性を見極めましょう。
導入には時間やコストがかかる
物流システムの導入には、時間とコストがかかります。
軽微なシステムの場合、導入自体に時間はかかりませんが、作業を担う担当者への周知には入念な説明が必要です。
さらに、従来の方法からの変更をスムーズに受け入れられる方ばかりではないことも、頭に入れておかなければなりません。
また、導入費用や、自社専用にカスタマイズする場合の改修費用等、導入にあたっての初期費用は避けることはできないため注意が必要です。
導入して改善したい課題をはっきりさせておく
物流システムは、導入するだけで効果が出るものではありません。
そのため、事前に導入することで解消したい課題や期待する効果を想定しておくことが大切です。
システム導入には費用や導入時間といったコストがかかります。
費用対効果を高めるためには、物流課題の抽出や、課題の優先順位づけ、導入シミュレーション等、事前の準備が必須です。
また、物流システム導入後も、効果検証や定期的なシステムメンテナンス等を行い、課題解決に取り組みましょう。
既存システムとの適合性を確認しておく
物流システムを導入する際には、既存システムとの適合性を確認しておくことが大切です。
既存システムには、倉庫等の物流施設で使用しているシステムはもちろんのこと、社内の請求や諸申請・手続き等を行う基幹システムも含みます。
また、一企業の物流管理においても、エリアや拠点が異なったり、自社運営の物流か外部委託の物流かによって、異なるシステムを使用していたりするケースがあります。
どのシステムに合わせるのか、物流だけではなく会社全体を最適化する観点で物流システムの選定、導入を検討し、推進していくことが大切です。
物流システムを選ぶ際の6つのポイント

ここからは、効果的な物流システムの導入のために意識すべき6つのポイントを解説します。
改善したい課題に応じて選ぶ
物流システムは、改善したい物流課題に沿ったサービス内容で選ぶようにしましょう。
頭痛がするのに咳止めの薬を飲んでも症状が良くならない理論と同じく、物流システムも、解消したい課題に対して適切な機能をもつシステムを導入しなければ効果を発揮しません。
複数の物流課題がある場合は課題に優先順位をつけ、ボトルネックとなっている課題の解消が図れる物流システムの導入が理想的です。
また、物流は一連の流れで成立しているため、一部の課題を解消することで他の領域や行程にも好影響が出るケースもあります。
導入効果を最大限に発揮するためにも、解決すべき課題の検討は入念に行いましょう。
物流システムの導入タイプで選ぶ
物流システムは、システムのタイプで選ぶことも大切です。
例えばとにかく手軽に導入したいという場合は、開発が不要なSaaSのサービスを利用するのがおすすめです。
開発コストがかからないほか、サービス提供会社側で機能のアップデートなどが実施されるため常に最新のサービスを利用することができるのがメリットです。
また、規模が大きな企業では自社システムを利用しているケースが多く見受けられます。
その場合はSaaSなどパッケ―ジサービスではなく、必要な機能を自社システムに組み込み・開発を行う方が現実的でしょう。
使いやすいものを選ぶ
物流システムは、使いやすいものを選ぶことも大切です。
というのも、物流システムの使用者の多くは、システム開発担当者やバックオフィサーではなく、倉庫等の物流施設で働く作業者やスタッフだからです。
優れたシステムであったとしても、実際に操作する人にとってわかりづらいと物流現場に混乱が生じ、物流品質を損なうことになります。
物流システムの導入時は、操作をする作業者やスタッフに対して導入の目的・意図を説明するとともに、できる限りわかりやすい仕様のものを選定し、混乱が生じないようにマニュアルを完備する等、万全の体制で稼働させましょう。
自社の業界で選ぶ
自社の商品やビジネスの特徴に合っているかどうかも、物流システムを選ぶ際の重要なポイントです。
工業製品と食品では物流の管理方法が異なりますし、食品の中でも温度管理が必要か否かで物流の留意点は異なります。
たとえば、飲料の物流を管理しようとする場合、ロボットの導入は慎重に検討した方が良いでしょう。
というのも、ロボットを初めとするデジタル機器は水に弱いという特徴があります。
また、耐荷重にも気をつけなければならず、重量オーバーの商品を扱って商品が破損し、システムを痛めてしまうと、効率化どころか物流自体を止めてしまうことにもつながりかねません。
そのため、自社の商品の特性と相性の良い物流システムを導入することが大切です。
拡張性の高いものを選ぶ
物流システムは、長く使うことを前提に導入することが理想です。
初期費用はもちろんのこと、システム利用料等のランニングコストも発生するため、できる限りの効果を出し、減価償却を図っていくことが求められます。
そのために必要な要素は拡張性の高さです。
企業の物流は、システムを導入した後、そのまま変わらずに使いつづけるとは限りません。
新商品が大ヒットしたり、新型コロナウィルスの際のマスクやワクチン等、緊急性を要する物流設計が突然必要になったりするケースもあります。
そのような時に、融通が利かない物流システムだと継続的な利用は難しいかもしれません。
臨機応変にカスタマイズやオプションの追加等が自在にできる拡張性の高いシステムを選びましょう。
既存システムとの連携性で選ぶ
物流システムは、物流管理の課題解決だけではなく、本社や営業との連携等、全社的な最適化を視野に入れた導入が理想的です。
タイムリーかつリアルタイムな在庫管理が必要とされる企業も多い中、物流現場が整えた在庫データを活かすのは本社の発注担当や、企画担当であることも珍しくありません。
また、在庫の状況に応じて、商品を販売する営業担当のアプローチ先が変わることもあるでしょう。
物流システムの選定は、これら社内の各関係部署とスムーズに連携が可能かという視点も必要です。
社内の請求システムや基幹システムとのデータ連携が可能かどうかは必ずチェックしてください。
セキュリティや信頼性で選ぶ
物流システムの導入で最も気をつけなければならないこと、それは情報漏洩リスク等、セキュリティ面での品質です。
EC市場が成長し、企業からダイレクトに消費者に商品を発送することが当たり前となった昨今ですが、言い換えると個人情報が不用意に世の中に出回る可能性のある世の中でもあります。
セキュリティの管理は企業モラルを示します。
システムの機能やサポート体制等も確認し、セキュリティ面で信頼のできる物流システムを導入しましょう。
物流システム導入による成功事例

それでは、実際に物流システムの導入がどのような効果をもたらしているのか、企業の成功事例を紹介しましょう。
今回は、ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」を導入した事例を紹介します。
成功事例① 属人化と赤字運行の防止
「ロジスティクスサービス 」の導入により、業務効率化とコスト削減が達成された事例です。
■利用機能:AI自動配車
■導入の効果:注文データの取り込みだけで配車が可能になるため、これまで配車業務に3~4時間を費やしていたものが約30分に短縮されました。
さらに、この機能により、新人やパートタイムのスタッフでも配車を組むことができ、配車スキルのあるスタッフに属人化していた配車業務も4~5名の人材によって手がけられるようになったそうです。
それぞれの業務が分散されたことで、業務の効率化が達成されました。
また、輸送コストと収益の関係性が不明確であった問題も解消。
AIによる最適な計画作成により赤字運行が防止され、利益率が向上しました。
この結果、全体的な業務改善と利益の最大化が実現しました。
成功事例② ラストワンマイルの効率化
「ロジスティクスサービス」の導入は、配送業務におけるラストワンマイルの効率化にも貢献しています。
■機能:ナビゲーションアプリ
■導入の効果:「ロジスティクスサービス 」を導入した運送会社は、ナビゲーションアプリの機能を活用することで、個人宅の表札名からビル内のテナントまで確認可能となり、誤配の防止につながっているそうです。
また、導入前の問題点であったドライバーごとの業務量の偏りや、日々40〜50枚の配送指示書出力に伴うコスト問題も解消されたそう。
さらに、配送ルートを完全に把握しきれない新人ドライバーのサポートとしても役立ち、最新の住宅地図データを活用できるアプリにより、誤配なく配送業務を行えるように業務が改善されています。
まとめ:自社の悩みにマッチした物流システムを導入し、業務効率を改善しよう!
物流システムの導入は業務の効率化に有効です。
労働集約型の業界である物流にとって、人口減少による労働力不足は深刻な問題です。
しかし、物流は人々の生活や企業の経済活動を支える重要なインフラであるため、機能を停止することはできません。
また、人口減少による労働力不足はすぐに解消されることはないでしょう。
限りある労働力や物流リソースを最大限有効に活用するためには、デジタルの力(物流システム等)を活用することが効果的です。
物流システムには、業務の正確性や、連続稼働しても疲弊しない耐久性という強みがあります。
人が担うべき作業と、物流システムが担うべき作業を選別し、物流全体の業務効率改善を目指しましょう。
物流業務の改善に! ロジスティクスサービス
ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」は、お客様のニーズに合わせた最適なサービスで物流業務をサポートします。
ロジスティクスサービスでは、高い技術力で設計されたナビゲーションシステムや、地図活用によるソリューション提供といったノウハウを用いて、お客様の物流課題を解決に導くことが可能です。
- 誰でも配車計画が設計できる「AI自動配車」
- 自動配車サービスから最適なルートを案内する「ナビゲーションアプリ」
- リアルタイムの業務進捗把握と事務作業を軽減する「動態管理」
等、物流の効率化を実現するツールとノウハウを提供します。
ぜひ、ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」を物流の効率化にお役立てください。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/