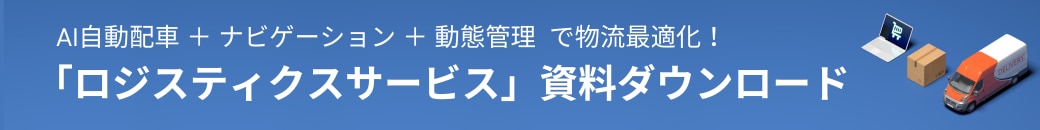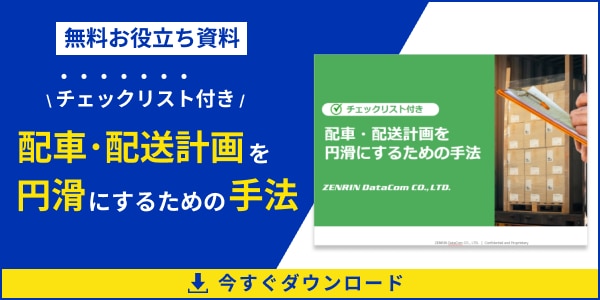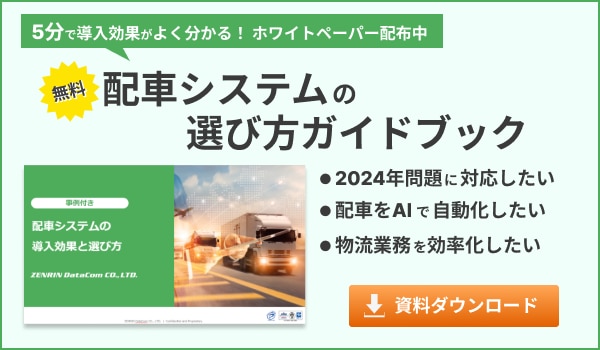物流の2024年問題|長距離走行を抑制する方法はあるのか?詳しく解説
2024年問題とは、働き方改革関連法によって2024年4月1日から、自動車運転業務の年間時間外労働を960時間以内に制限することで発生する諸問題のことをいいます。
この記事では2024年問題の中でも、とくに時間外労働への影響が大きい長距離走行の抑制方法について解説します。
物流の2024年問題にお困りですか?
「ロジスティクスサービス」なら配車業務の効率化、車両台数を削減!
⇒ロジスティクスサービスの資料を見てみたい
目次[非表示]
- 1.物流業における2024年問題とは?
- 1.1.時間外労働の上限規制
- 1.2.有給休暇の取得義務
- 1.3.同一労働・同一賃金
- 2.物流業界における2024年問題の影響とは?
- 2.1.ドライバー1人あたりの走行時間が短くなる
- 2.2.ドライバーが不足する
- 2.3.物流量が減り業績が悪くなる
- 2.4.時間外労働の賃上げにより人件費が高騰する
- 3.2024年問題に備えて長距離走行を抑制する方法
- 3.1.物流システムやITの活用
- 3.2.労働条件・環境の見直し
- 3.3.輸配送効率を向上させる
- 4.2024年問題に向けて荷主側ができる3つの対策例
- 4.1.モーダルシフトの導入
- 4.2.VMIセンターの導入
- 4.3.共同配送
- 5.まとめ:2024年問題を解消するため業務効率を向上させよう
- 6.物流高率を効率を上げるならゼンリングループの「ロジスティクスサービス」が有効!
物流業における2024年問題とは?

2024年4月1日から、働き方改革関連法によって自動車運転業務の年間時間外労働が960時間以内に制限されます。
2024年問題とは、この時間外労働の制限により発生が想定される諸問題のことです。
物流業界はトラックドライバーの高齢化や人手不足が深刻化しています。
その理由は、長時間労働かつ低賃金という働く環境にあるでしょう。
2018年に公布された働き方改革関連法では、労働基準法の改正がなされました。
改正の中で、時間外労働の上限が年間960時間とされます。
大企業では2019年4月1日から施行され、中小企業では2020年4月1日から施行されています。
この上限規制は自動車運転業務については2024年3月31日まで猶予されているものの、2024年4月1日からは、働く環境の改善と労働力不足の双方の解消が迫られているのです。
配車業務の効率化、車両台数を削減ができる「ロジスティクスサービス」の資料を見てみる
⇒資料はこちらから
時間外労働の上限規制
労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内です。
これを超える労働のことを時間外労働といいます。
2018年に改正された働き方改革関連法では時間外労働の上限を以下と定めています。
- 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
- 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月が限度
自動車運転業務においては、業務の特殊性や業界の事情を考えて、例外的に年間の時間外労働の上限が960時間とされているのです。
参考:時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務
有給休暇の取得義務
働き方改革関連法は、法人の従業員に対する年間5日以上の年次有給休暇の取得を義務付けています。
年次有給休暇とは休暇を取得しながらも賃金を得られる制度です。
これは、ブラック企業による過酷な労働による過労死や、休日出勤・長時間労働の常態化を防止し、従業員が働きやすい職場を実現するための取り組みの一環です。
取得義務を設けることで、有給休暇制度の形骸化抑止が期待されています。
トラックドライバーは全産業平均と比較すると、労働時間が年間384~432時間(月32~36時間)と長く、賃金だと5~12%低いという調査結果も報告されているのです。
そのため、計画的な有給休暇の取得で、労働時間と賃金の両面から働く環境の改善を図る必要があるでしょう。
同一労働・同一賃金
同一企業で勤める正規雇用社員と非正規雇用社員の間での不合理な待遇差を発生させない考え方を同一労働・同一賃金と呼びます。
従業員が雇用形態を選び、多様な働き方を実現することが目的です。
待遇とは給与だけではなく、通勤手当等手当の支給ルールや、長期休暇の取得ルール等多岐にわたります。
労使での話し合いや、他企業の成功事例にならって改善を図る企業も多く、業務見直しによる効率化や従業員のモチベーション向上を実現する企業も増加しているのです。
参考:企業事例50音順一覧|公正な待遇の確保に向けた企業の取組事例
物流業界における2024年問題の影響とは?

働き方改革による職場環境の整備は、人手不足やドライバーの高齢化といった問題が顕在化している物流業界が物流機能を維持するために必要な取り組みです。
一方、働く環境の整備により、これまでの物流業界の慣習が通用しなくなります。
たとえば、労働時間の制限は、ドライバー1人あたりが扱える物量の減少につながるでしょう。
ここでは、働き方改革関連法による環境改善がもたらす影響について解説します。
ドライバー1人あたりの走行時間が短くなる
これまで時間外労働を想定して業務を遂行していたドライバーは、時間外労働の上限を意識した業務が必須となり、雇用主側も厳しい監督を余儀なくされます。
厚生労働省の調査によると、通常期で1日当たり2~3時間、繁忙期になると全体の26.2%の企業が3時間以上の時間外労働を行っています。
そこで時間外労働の上限規制により、走行時間の短縮という形でドライバーへの負担軽減が実現されます。
一方で、1日で走破できていた距離が保てなくなり、これまで完遂できていた配送完了期日を伸ばさざるを得ない等、サービスの見直しをしなければいけなくなることが予想されるでしょう。
ドライバーが不足する
時間外労働の上限規制により、さらなるドライバー不足が懸念されるでしょう。
たとえば、従来5名のドライバーで完結していた業務も、1人あたりの労働時間や走行距離が2割減少した場合、1名の増員が必要になります。
同様の問題を抱える物流事業者間でドライバーの獲得合戦が激化し、人手不足や高齢化という課題に拍車をかけてしまうことが懸念されるのです。
物流量が減り業績が悪くなる
ドライバー1人あたりの労働時間が短縮され、走行距離が短くなることにより、取り扱い貨物の減少が懸念されます。
そのため、物量減少は売り上げの低迷を招き、会社の業績悪化にもつながるでしょう。
また、慢性的なドライバー不足により、これまで受諾できていた荷物を運びきれない事態が想定されます。
運びきれない荷物は断らざるを得なくなり、働く環境を優先することで売り上げが低迷し、給料が上がらないという悪循環が生まれてしまう可能性があります。
時間外労働の賃上げにより人件費が高騰する
物流業の2024年問題のひとつに人件費の高騰があげられます。
ドライバーの雇用形態は、企業に勤める場合や個人事業主として企業と契約する等、多岐におよびます。
ドライバーにとっては、同じ業務量であれば賃金が高い方が魅力的です。
そのため、雇用条件や契約条件のよい企業や案件にドライバーが集中することになります。
また、ドライバー不足のため、企業側もこれまでの雇用条件のままではドライバーを採用することが難しくなっているのが現状です。
自社の物流機能やビジネス維持のためには、賃金を上げてでもドライバーを確保せねばならず、物流事業者にとっては人件費高騰が懸念されるでしょう。
2024年問題に備えて長距離走行を抑制する方法

物流事業者は2024年問題に備えて業務や労働環境の見直しを迫られています。
時間外労働の制限による影響が大きい長距離走行において、現状の勤務形態・人員体制では、これまでのリードタイムや輸配送の品質維持が難しくなるでしょう。
長距離走行を抑制するためには、現場の管理だけでなく荷主との協力や社内体制の見直し、新技術の導入による物流全体の作業効率化等、多岐方面からのアプローチが必要です。
ここでは、2024年問題の中でも長距離走行を抑制する方法について解説します。
物流システムやITの活用
人手不足や高齢化といった問題が顕在化する物流業界において、物流システムやITの活用は不可欠となります。
物流業界は、倉庫での作業やトラックの配車、荷役作業等の各フェーズにおいてアナログな慣習が多く残っているのが現状です。
そのため、ITによる業務改善により、倉庫や港湾地区での待ち時間解消や、空車情報を的確に管理し効率的な配車を実現するプラットホームを設置する企業も増えています。
そうすることで、物流業務の効率化が実現でき、結果、勤務時間内での走行距離の最適化が可能となるでしょう。
労働条件・環境の見直し
2024年問題のそもそもの発端は物流業界のブラックな働き方が問題視されたことです。
厚生労働省の調査によると、トラックドライバーの年間所得は全産業と比べて、大型トラックドライバーで約1割、中小規模トラックドライバーで約2割低いといわれています。
また、年間の労働時間も全産業と比較し約2割長いことが指摘されているのです。
この長時間労働かつ低賃金という労働環境を改善しないことには、十分な労働力確保には至らず、抜本的な課題解決は図れないでしょう。
短時間での勤務形態を作ったり、ギグワーカーを活用したりする等多様な働き方を組み合わせ、ワークライフバランスの充実を図りながら、労働条件を改善することも手段のひとつです。
輸配送効率を向上させる
ドライバーの貴重な業務時間を有効活用するために欠かせないのが輸配送の効率化です。
港湾地区や倉庫での荷役作業による長時間に及ぶ待機等、まだまだ非効率な仕組みが多い物流業界。
言い換えると、これらを効率化することで削減できる時間はまだ多くあります。
そのため、配車システムの導入や、倉庫作業の自動化による荷役の効率化、AIによる配送ルートの設計等、ドライバーの輸配送の負担を軽減する取り組みが注目されるようになりました。
また、これら新技術の導入だけではなく、幹線輸送の効率化も効果的です。
幹線輸送とは流通加工拠点等を結ぶ比較的大ロットの輸送を指します。
流通加工拠点の集約や鉄道輸送との組み合わせにより幹線輸送を効率化することで、長距離輸送を担うドライバーの負担軽減が可能です。
また、EC市場の成長による物流の多頻度化によって積載効率を上げる必要も出てきました。
その結果、企業の需要予測や販売計画等の商流情報とトラックの空きスペース等物流企業の情報を相互に活用し、積載効率を高めた輸配送を計画的に行う取り組みも実施されています。
2024年問題に向けて荷主側ができる3つの対策例

2024年問題は物流企業の努力だけでは解決できません。
依頼主である荷主企業が物流企業に協力し、物流全体の最適化が必要です。
ECによる貨物の需要過多や、新型コロナウィルスの規制緩和による経済の回復等により、今後も物流の活発化が予想されます。
ここでは、2024年問題とその解消に向けて、荷主側ができる対策を解説します。
モーダルシフトの導入
2024年問題の中でも、長距離輸送の抑制に効果が期待されているのがモーダルシフトです。
モーダルシフトは貨物や旅客の輸送手段の転換を図る取り組みで、1990年頃から環境配慮や人口減少等の対策の一環で推し進められています。
貨物の輸配送手段はトラックだけではありません。
経済産業省の調査によると、日本の国内貨物の輸送モード(トンキロ別)は、自動車が約50%、内航船が約40%を占め、鉄道輸送は5%程度に留まっています。
その5%を改善するために、1人の運転者で大量の貨物を長距離区間運ぶことができ、CO2削減等環境へも優しい鉄道輸送を活用するよう、JR貨物が物流企業と連携し積極的な鉄道輸送導入を図っています。
VMIセンターの導入
VMIとは、Vendor Managed Inventoryの略称であり、ベンダー(納入業者)が在庫を管理する事を指します。
荷主である企業と納入業者である物流企業が生産計画や在庫状況、出荷量等の情報を共有することで物流全体の最適化を図ることができます。
VMIセンターの活用は物流企業にとって多くのメリットをもたらすでしょう。
たとえば、納品時や集荷時の待機時間の削減や、急な物量増による非効率な輸送の軽減です。
VMIセンターを活用することで、あらかじめ需給を予測し、計画的に配車ができるため、トラックの空きスペースを削減できるでしょう。
ただし、荷主企業側にとっては、ITシステムの整備が必要であること、規模によっては多額の資金が必要になること等から、とくに中小企業にとっては導入ハードルの高さが課題です。
共同配送
長距離輸送抑制の手段のひとつは共同配送です。
共同配送とは、複数の企業間で協力し荷物を共同で保管・輸配送を行ったりすることを指します。
ひとつの企業の荷物だけで長距離輸送する場合、物量の少ない地域への輸送効率は悪くなるでしょう。
そこで、複数の企業の荷物をトラックに積み、適宜目的地に配達をすることで積載効率を上げ、荷主・物流企業双方の効率化を図るのです。
たとえば、東京から出発し最終目的が福岡の案件の場合、同方向の名古屋・大阪・広島等の配達先を持つ企業の荷物も同時に運ぶことができれば、到着地ごとに休憩を挟むことができ、ドライバーは連続運転時間の軽減が図れ、荷主は輸送費用を折半することで物流コストを削減できます。
また、福岡から東京の帰り便で逆方向の輸送を担えれば、さらに輸送効率は向上するでしょう。
まとめ:2024年問題を解消するため業務効率を向上させよう
物流業界における2024年問題の解消は、物流企業やトラックドライバーの努力だけでは実現しません。
2024年問題を解消するためには荷主企業の協力や、荷主企業同士の連携、新技術の導入等さまざまなアプローチが必要です。
トラックドライバーの不足や高齢化が加速する中、EC物流は増加を続け需要は高まっています。
物流のムラ・ムダをできる限り見直し、業務の効率化を図ることで、2024年問題を解消しましょう。
物流高率を効率を上げるならゼンリングループの「ロジスティクスサービス」が有効!
ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」は、お客様のニーズに合わせた最適なサービスで物流業務をサポートします。
ロジスティクスサービスでは、高い技術力で設計されたナビゲーションシステムや、地図活用によるソリューション提供といったノウハウを用いて、お客様の物流課題を解決に導くことが可能です。
- 複雑な配車をAIで自動化
- 輸配送ルートの最適化を図るナビゲーションアプリの提供
- 車両の位置や走行距離の管理を可能とする車両動態管理システム
- 運転日報の自動化
など、さまざまな物流の効率化を実現するツールとノウハウをご提供します。
ぜひ、ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」を物流の効率化にお役立てください。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/