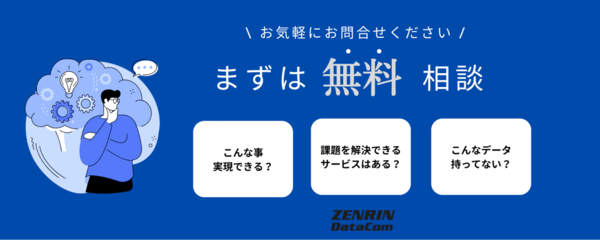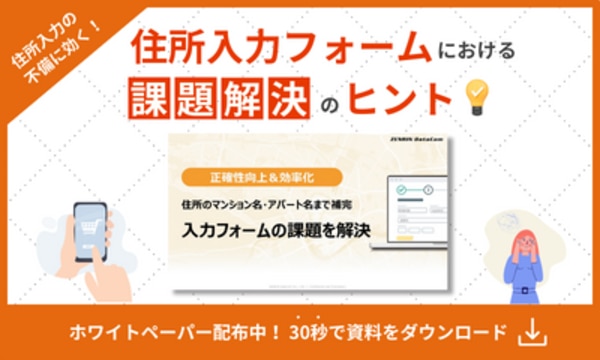API連携とは?基本の仕組みやメリット・デメリットと具体例を解説
外部のシステムやソフトウェア同士を連携することで、利用できる機能を拡張することをAPI連携といいます。
開発・運用にかかるコストや手間を削減し、作業の効率化や利便性の向上も目指せることから幅広いシーンで活用されているサービスです。
本記事では、API連携の具体的な仕組みやメリット、注意点や一般的な実装方法等を解説します。
API連携について知りたい方や興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
★地図のAPIサービスを活用して「アプリ開発」や「ルート検索」などの実装を効率化! →ZENRIN Maps APIの資料を見てみる |
目次[非表示]
- 1.APIはプログラムやWebサービス間を連携するインターフェース
- 2.API連携とは?
- 2.1.API連携の基本的な仕組み
- 3.API連携を活用した身近なサービスの具体例4つ
- 4.API連携を活用する3つのメリット
- 4.1.ソフトウェア開発を効率化できる
- 4.2.サービスの利便性や付加価値が向上する
- 4.3.公開ソフトウェアのデータを利活用できる
- 5.API連携のデメリットや注意点
- 5.1.提供元のトラブルの影響を受ける
- 5.2.APIの利用に継続的なコストがかかる
- 6.API連携の一般的な実装方法
- 6.1.1.導入目的を明確にする
- 6.2.2.連携先の選定・ユーザー登録
- 6.3.3.APIキー・シークレットキーの取得
- 6.4.4.連携開始・動作確認
- 7.まとめ:API連携を活用してシステムを構築しよう
- 8.APIによる地図情報の活用はゼンリングループの「ZENRIN Maps API」がおすすめ
APIはプログラムやWebサービス間を連携するインターフェース

アプリケーション・プログラミング・インターフェース(Application Programming Interface)を略してAPIといいます。
APIのAは「アプリ」、Pは「プログラミング」、Iは「つなぐもの」を指すため、直訳すると「アプリとプログラムをつなぐもの」がAPIとなります。
アプリやソフトウェア、プログラムなどを連携できるので、自社のアプリが持つ機能だけではなく、連携先となる他のアプリやサービスの機能が利用可能になります。
ネットワーク上で連携できるものは「WebAPI」と呼ばれ、双方の情報のやり取りはHTTP/ HTTPSベースで行われます。
プログラミング言語が違う場合でも連携は可能です。
API連携とは?

APIを使用すれば容易にデータ連携や機能を拡張でき、業務の効率化を図ることができます。
API連携の仕組みや具体的な活用例をみていきましょう。
API連携の基本的な仕組み
API連携はリクエストとレスポンスによって構成される仕組みで、リクエストはAPIの利用者を指し、レスポンスはAPIの提供者のことを指します。
リクエストに対するレスポンスの内容は提供者がAPIを設計する際に考えており、その内容を実装して利用可能な状態にします。
例えば、B社のAPIの機能を使いたいと感じたA社は、B社にAPIを提供してもらうだけで機能を使えるようになるのです。
A社は自社で同じ機能を開発する手間がなくなるので、開発にかかる工数やコストを軽減できるメリットが得られます。
API連携を活用した身近なサービスの具体例4つ
API連携の仕組みをより理解するためにも、日常において利用されているサービスの具体例をご紹介していきます。
SNS
日常的にSNSを活用している方もいるでしょう。LINEやInstagram、FacebookやX(旧Twitter)がAPIを発行しており、連携するとさまざまなメリットが得られます。
API活用例①ログイン認証
Webサイトのログイン認証で、SNSのアカウント情報を入力すると会員登録ができる機能があります。
SNSのアカウント情報をそのまま利用し、会員登録ができるようにAPI連携を用いて実装されている事例です。
導入した側は、Webサイトで会員情報を保管する手間がなくなるため、情報漏洩を防止するためにセキュリティ対策を充実させる必要もなくなります。
ユーザーも情報を入力して会員登録を行う手間が省けるので、手間がなくなり利用者や売り上げの増加が期待できる仕組みです。
API活用例②同時投稿
API連携を利用し、SNSでの同時投稿も可能です。
Instagramに投稿する記事をFacebookにも同時に投稿できる機能があり、Instagramで投稿する際に、「Facebookにも投稿」にチェックを入れるだけで、自動でFacebookにも投稿される仕組みです。
同じものを入力する手間がなくなるので、利用者の手間が省けます。
POSレジ
POSレジをAPI連携させることも可能です。
API活用例①在庫管理
在庫管理機能を有するAPIを活用すれば、リアルタイムに在庫数が把握でき、在庫切れや過剰在庫のリスクを軽減できるほか、受発注の業務効率化や在庫状況の可視化などにも役立ちます。
店舗側は在庫を数える手間が省け、発注管理にも役立つので業務の効率化を図れるでしょう。
API活用例②ECサイトとの連携
POSレジで商品を販売すると、その時点での在庫数がECサイトにリアルタイムに反映されます。これにより、顧客が商品を注文した時点で、在庫切れかどうかを確認できるようにすることができます。
また、ECサイトで会員登録した顧客情報を、POSレジと連携することで、実店舗とECサイトの顧客情報を一元管理することができます。
ECサイト
ECサイトを活用する際、ショッピングの支払いでクレジットカードを使うケースもあるでしょう。
カード番号や名前、期限やセキュリティコード等を入力しますが、ECサイトではカード会社が提供するAPIを活用して管理されているケースもあります。
APIを通して決済を要求し、ユーザーによって打ち込まれたカード情報は、ECサイトを通さずに直接カード会社のサーバーまで届く仕組みです。
カード会社側でカードの情報の確認がされ、その後ECサイト側に確認完了の返答を送り、決済が終了となります。
ECサイト側はカード情報の管理をせずに済むので、カードの情報漏洩を防ぐために強固なセキュリティ管理をする必要がありません。
ユーザーも安心して買い物ができるので、利用者の増加も期待できます。
社内システム
社内システムにAPIを連携すると、追加したい機能を自社で開発せず利用できるため、業務の効率化を図れます。
例えば勤怠管理です。これまでの勤怠管理は勤怠データをCSVに出力し、データを手作業で入れ込む必要がありました。
時間や手間のかかる作業ですが、勤怠管理データと連携すればデータの入力作業の負担を減らせます。業務の効率化ができるだけではなく、人件費の削減にもつながるでしょう。
★ゼンリンデータコムは地図表示やルート検索等に活用いただける様々なAPIを提供しています。
API連携を活用する3つのメリット

APIと連携すると、どのようなメリットが得られるのか解説していきます。
ソフトウェア開発を効率化できる
API連携を活用すれば、最初からソフトウェアを開発せずに済むので開発の工程を省略化できる点がメリットです。
すでに提供されているシステムを使うので、開発にかかる時間を削減できます。開発にかかる時間を軽減できれば、その分、他の業務に時間を使えるでしょう。
サービスや商品の質の向上に向けた戦略策定や売り上げにかかわるシステムの開発に時間を割くことができ、売り上げにも影響を与えるはずです。
サービスの利便性や付加価値が向上する
提供するサービスを継続して利用してもらうためにも利便性のよさは大切です。
利便性をよくするためには自社で開発したシステムを採用する方法もありますが、API連携を活用してより使いやすいサービスを提供する方法も考えられるでしょう。
例えば、初めて自社のサービスを利用するユーザーがいた場合、会員登録が必要です。その際、自分の情報を入力する作業を手間と感じ、違うサービスの利用を検討してしまう方も中にはいます。
しかし、SNSや他サイトのユーザー情報をそのまま利用できれば、IDやパスワードを新たに取得するといった登録の手間が省けるのでユーザーの利便性は向上するでしょう。
利用できる機能が拡張されれば使い勝手もさらによくなるので、顧客満足度アップにもつながります。
公開ソフトウェアのデータを利活用できる
利用する際の仕様が一般に公開されているものを公開ソフトウェアといいます。連携をすれば、公開ソフトウェアのデータ活用が可能です。
銀行法の改正によって金融業界ではAPIの公開が広がりを見せていますが、ECサイトやSNSでもソフトウェアが公開されているケースが増えています。
ECサイトであれば顧客の情報や購入した商品情報を取得でき、SNSでは顧客がサービスや商品に対して感じた本音を取得できるので、業務改善やサービス戦略に活用可能です。
API連携のデメリットや注意点

API連携を活用する際には注意すべき点もあるので、以下を参考にして役立てましょう。
提供元のトラブルの影響を受ける
APIを提供するサーバーで問題が発生した場合、利用している企業側では対処ができません。
APIを公開している企業が急に停止するケースもあるため、トラブル時の対策を事前に模索する必要があります。
代替方法がなければ対応が遅れてしまい、自社のサービスや売り上げに影響する可能性もあるので注意してください。
APIの利用に継続的なコストがかかる
APIによっては無償で利用できるものもあれば、有料で提供しているものもあります。
中には従量課金制を採用しているものもあり、ソフトウェアが利用され続ければ課金額も増え続ける仕組みです。
いくら利便性が高くてもコストがかかり過ぎれば継続が難しくなってしまいます。
課金額は提供している企業によって違いがあるので、あらかじめ確認して無理なく継続できるかチェックしてみてください。
API連携の一般的な実装方法

ここからは、API連携を実装する際の一般的な流れを解説していきます。
※企業により実装方法は変わるため一例となります
1.導入目的を明確にする
最初に連携をする目的を決めましょう。
例えば下記の様な目的が挙げられます。
- 自社開発をするコストを減らしたい
- 自社開発をする手間をなくしたい
- 業務効率化のために実装したい
- 自社では開発が難しいから活用したい
目的を明確化させたら、目的が達成できるAPI連携先を探し出し、連携するためのコストや削減できる時間を算出して導入するべきか検討していきます。
\ ゼンリンデータコムでご提案可能な地図APIのUIや機能比較はこちら↓ /
2.連携先の選定・ユーザー登録
連携先を見付けたら、活用するためにもユーザー登録が必要です。
ユーザー登録には、以下の項目等を入力します。
- ソフトウェアの名称
- ソフトウェアの概要
- 利用する目的
- 住んでいる国
ユーザー登録をした後には審査が実施されることが一般的ですが、1~2日程度を要するので計画性を持って導入を進めてください。
3.APIキー・シークレットキーの取得
ユーザー登録終了後、APIを使用する際に必要となるAPIキー・シークレットキーの2つを取得します。取得するための方法は企業ごとに異なるので事前に確認しておきましょう。
それぞれAPI利用に必要となるコードで、セキュリティにも関係する重要な情報です。
取り扱いには十分に気を付けましょう。
4.連携開始・動作確認
APIキーとシークレットキーの取得が完了したら連携開始です。
仕様書に従って実装していきます。
実装が終了したら、正しく作動するか動作確認を行ってください。
まとめ:API連携を活用してシステムを構築しよう
API連携によって自社のサービス向上を図ることができ、顧客満足度のアップも期待できます。
セキュリティの向上や業務効率化も図れるので、企業としてもメリットです。
しかし、連携をする際にはコストの発生や提供元のトラブルといったリスクも理解しておきましょう。
そのようなトラブルにも対処できるよう、前もって対処法を検討しておくことが大切です。
導入を検討している場合は、本記事で紹介した実装方法を参考にして連携を進めてみてください。
APIによる地図情報の活用はゼンリングループの「ZENRIN Maps API」がおすすめ
APIといってもさまざまな種類のサービスがありますが、地図のAPIを利用したいという場合は、ゼンリングループの「ZENRIN Maps API」をご検討ください。
まずはどういった特徴があるのかご紹介します。
ZENRIN Maps APIの特徴
ZENRIN Maps APIでは、住宅地図の表示が可能です。
道路地図から市街地図まで20段階もの地図レベルが準備されており、個人表札名や登記で利用される地番住所まで細かく表示できる特徴があります。
約25年前まで遡って地図情報を表示することも可能です。
- 地価公示、地価調査
- 学校区
- 用途地域
- ブルーマップ
- 相続税路線価
- 固定資産税路線価
さらに豊富なコンテンツがあり、それぞれ用途に合わせてベース地図に重畳して表示できます。
また、標準的なルート検索だけではなく、大型車規制ルートや規制情報が考慮された内容で検索が可能です。
不動産業やサービス業、運輸業や金融業等、幅広い業界で利用できるAPIになりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ゼンリンデータコムは3種類の地図APIから用途に合ったご提供が可能です
ZENRIN Maps APIのほか、Google Maps Platform、Mapbox APIのご提供が可能です。
Google Maps PlatformはGoogleマップの商用版となり、使い慣れたUIでサイトやサービス内に地図を利用することが可能です。
ゼンリンデータコムは900社以上にGoogle Maps Platformを提供しており、日本語での技術サポートが大変喜ばれています。
Mapbox APIは米国で設立されたMapbox社が提供する、地図を使ったサービス構築向けのAPIです。特に地図表記のカスタマイズ性が高く、用途に応じた地図の組み込みを実現することができます。
以下ページでは、各種地図APIの実際のUIと特長を確認できますので、自社のニーズに合った地図APIをご検討ください。
\ 地図APIのUI比較が可能 /
特集|地図APIのご紹介|ゼンリンデータコム法人向けサービス (zenrin-datacom.net)