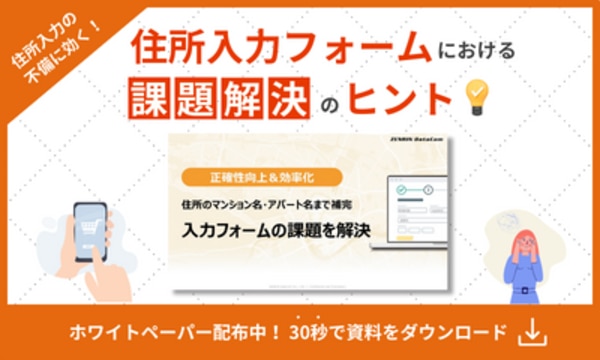アルコールチェック義務化とは?対象者や罰則と2023年の追加点を紹介
国土交通省では、飲酒運転を0にするための取り組みとして、事業所にアルコールチェックを行うよう義務付けています。
これは道路交通法に則ったものですが、2023年12月から改正が適用され、チェック内容が変わりました。
そこで本記事では、そんなアルコールチェック義務化での内容と対象者、さらに実施までに準備すべきことをご紹介します。
これまでの内容と何が変わったのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
★アルコールチェックの実施にお悩みですか?
ゼンリンデータコムの「テレマティクスサービス」はアルコールチェックや車両安全管理にご活用いただけるソリューションです。
→詳しい資料を見る
目次[非表示]
- 1.道路交通法改正によるアルコールチェック義務化のあらまし
- 1.1.いつから始まる?
- 1.2.対象者は?
- 1.3.道路交通法改正の背景は?
- 2.2022年4月にスタートした白ナンバーのアルコールチェックの内容
- 2.1.目視によるアルコールチェックの方法
- 2.2.アルコールチェックの結果の記録方法
- 3.2023年12月から義務付けられる検知器を用いたアルコールチェックの内容
- 4.アルコールチェックの義務に違反した際の罰則は?
- 5.アルコールチェック義務化対応のために企業が準備すべきこと
- 5.1.安全運転管理者を選任する
- 5.2.アルコールチェッカーを導入する
- 5.3.記録の保管方法を検討する
- 5.4.チェック実施のフローを整備する
- 5.5.運転者への周知を行う
- 6.まとめ:アルコールチェック義務化に向けた準備を進めよう
- 7.ドライバーの安全運行の維持管理はシステムで効率化!
道路交通法改正によるアルコールチェック義務化のあらまし

アルコールチェック義務化は、道路交通法の改正によって実施されます。
まずは、義務化が始まるタイミングや対象者、改正に至った背景を解説します。
いつから始まる?
道路交通法の改正が行われたのは、2022年4月です。
それまでは、運送業や旅客運送業等を含む緑ナンバーの自動車を持つ事業所に対して、アルコールチェッカー(アルコール検知器)の備え付けと運転者にチェックを実施することが義務付けられていました。
しかし、2022年4月からは白ナンバーの車を持つ事業所に対しても、規定台数以上であれば目視によるアルコールチェックが義務化となったのです。
さらに、2023年12月からは目視だけでなく検知器を使った確認が義務付けられました。
元々は2022年10月から実施される予定でしたが、半導体不足等の影響で延期し、2023年12月より開始されています。
対象者は?
チェックが義務付けられているのは、安全運転管理者を設置する事業所です。
【安全運転管理者の設置要件】
- 定員が11人以上の自動車を1台以上保有する事業所
- 定員が10人以下の白ナンバー車を5台以上保有する事業所
この要件は、事業所ごとの台数でカウントされるものです。
車種・車両用途は関係なく、さらに黄色ナンバーの軽自動車も対象になります。
50cc以上の自動二輪車は0.5台として計算してください。
さらに、以下の要件に当てはまる場合は副安全運転管理者も選任しなくてはなりません。
【副安全運転管理者の設置要件】
- 自動車を20台以上保有する事業所
20~39台につき1人の副安全運転管理者を選任し、40台以上の場合は20台ごとに1人追加していきます。
副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する役割があるため、要件に当てはまる場合は選任してください。
道路交通法改正の背景は?
道路交通法が改正された背景には、2021年6月に起きた凄惨な事故があります。
当時、トラックの運転手が飲酒運転を行い、下校中だった小学生をはね、児童5人を死傷する事故が起こりました。
運転手が乗っていたトラックは白ナンバーであり、アルコールチェックが実施されていなかったのです。
また、いまだに飲酒運転による交通事故が発生している点も影響していると考えられます。
2022年内で発生した飲酒運転による交通事故の発生件数は2,167件で、そのうち死亡事故件数は120件でした。※この結果は前年比より減少しているものの、現在は減少幅も縮小しています。
飲酒運転による痛ましい事故を起こさないためにも、道路交通法の改正によって義務化の対象範囲が広がったのです。
※出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
2022年4月にスタートした白ナンバーのアルコールチェックの内容
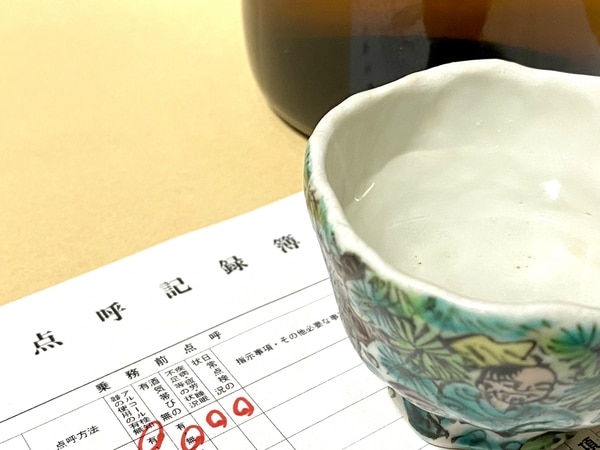
次に、2022年4月から始まっているアルコールチェックについてご紹介します。
どのように確認を行っているのか、その結果はどのように記録するのかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目視によるアルコールチェックの方法
2022年4月から始まっているアルコールチェックは、目視によって酒気帯びかどうかを判断します。
また、酒気帯びの有無を記録した書類を1年間保存することも義務付けられました。
目視による確認は運転前後で行うものと決められています。
この「運転」は、一連の業務を指すものです。
つまり、従業員一人ひとりが運転する直前・直後に都度行うものではなく、業務の開始前や出勤したタイミング、退勤時に行うことになります。
目視での確認は原則対面で行い、運転者の顔色や表情、呼気のにおい、声の調子等から判断することが基本です。
ただし、運転者が直行直帰する場合や出張等、対面で目視を行えない場合もあるでしょう。
そのようなときは、ビデオ通話を介して確認する方法と、電話で応答の様子を確認する方法でも可能です。
アルコールチェックの結果の記録方法
目視で確認した場合、その結果を記録しておかなくてはなりません。
記録の形式や媒体に指定はないものの、記録する内容は決まっています。
【記録内容】
- 確認した日時
- 確認者名
- 運転者名
- 運転者が業務で使用する自動車の登録番号または識別できる記号・番号等
- 確認方法
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
- 先ほどもご紹介したように、記録した書類は1年間保存する必要があります。
記録媒体はノート等の紙媒体でも問題ありませんが、手書きだと記入漏れが発生する恐れもあるため、注意が必要です。
とくに、従業員数が多い事業所の場合は、ExcelやITツール等を活用することで記録と管理が効率的に行えるようになります。
2023年12月から義務付けられる検知器を用いたアルコールチェックの内容
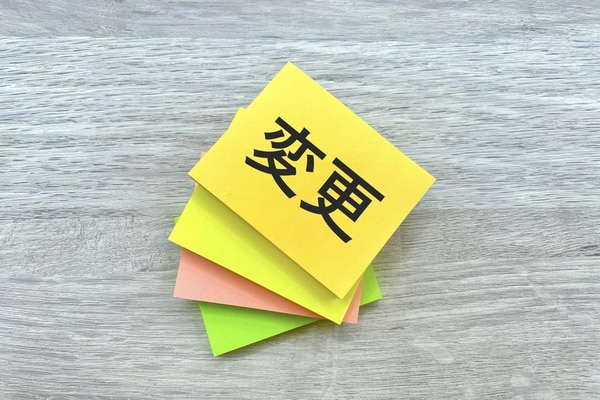
2023年12月からは、アルコールチェックがさらに厳しくなりました。
2023年12月から新たに追加された内容をご紹介します。
営業所ごとのアルコールチェッカーの備え付け
これまでは目視で確認が行われてきましたが、2023年12月1日からは、検知器を活用したアルコールチェックが義務付けられました。
目視と同様に、安全運転管理者がアルコールチェッカーを使って確認し、酒気帯びかどうかの結果を記録・保存します。
アルコールチェッカーは各営業所に常備しておき、ドライバーが遠隔地に行く場合には携帯できる検知器を携行させなくてはなりません。
また、検知器を常備する際は安全運転管理者が取扱説明書の内容に基づいて、適切な管理・保守を行います。
なお、どのアルコールチェッカーを使えばよいのかわからない方も多いでしょう。
国土交通省では、アルコールチェッカーについて推奨している機種はありません。
そのため、自社の勤務体系や保存方法等に合わせて選ぶことがおすすめです。
たとえば、電子データで記録の保存・管理を行いたい場合は、測定結果が自動的にクラウドシステムへ送られる検知器を活用すると、アルコールチェックが効率よく行えるようになります。
アルコールチェッカーの種類と点呼時の使用
アルコールチェックを実施するタイミングは、目視のときと同様に運転前後で行うことになります。
朝礼時や終業時等で点呼を行う際にまとめて行うことで、安全運転管理者の立ち会う手間も省けるでしょう。
アルコールチェッカーの使い方は、機種によって異なります。
種類 |
測定原理 |
メリット |
デメリット |
半導体式 |
センサーに付着する酸素量に応じて、電気の抵抗値が変化する特性を利用 |
小型・軽量で、価格が安い |
精度が電気化学式に比べて劣る |
電気化学式 |
呼気に含まれるアルコール成分を燃料として、電気が発生する特性を利用 |
精度が高く、耐久性が高い |
大型・重量で、価格が高い |
もし、運転者が遠隔地にいて安全運転管理者が対面で確認できない場合は、携帯用の検知器を使って確認してもらいます。
その際、ビデオ通話や電話等を活用して顔を見ながら行いましょう。
ただし、チャットやメールでの確認方法は認められていないので注意してください。
アルコールチェッカーの適切な管理・保守
検知器については毎日電源が入ることと、損傷がないことを確認した上で実施するようにしましょう。
また、週1回以上は酒気帯びをしていない人がアルコールチェッカーを使った場合にアルコールを検知していないか、アルコールを含んだ液体や希釈したものを口内に吹きかけ、検知器を使ったときにきちんと検知されるか確認する必要があります。
検知器の適切な管理・保守を行うことは業務の負担につながる面もあります。
しかし、「置いているだけで使ったことがなく、いざ使用する際に検知機能が反応するかわからない」という状況を防ぐためにも、業務の重要な事項として適切な管理・保守を行うことが大切です。
アルコールチェックの義務に違反した際の罰則は?

アルコールチェックを行わなかった場合、安全運転管理者は業務違反となってしまいます。ただし、2023年12月時点では直接的な罰則はありません。
しかし、都道府県の公安委員会より安全運転管理者の解任や命令違反による罰則を科せられるでしょう。
また、チェックを怠ったことで従業員の飲酒運転が認められた場合、厳しい刑事処分・行政処分が科せられます。
さらに、飲酒運転に荷担した人や飲酒運転の恐れがあるとわかっていながら車両を提供した人、飲酒をすすめた人、同乗した人も処分の対象になるので注意が必要です。
【運転者に対する処分】
分類 |
基礎点数 |
行政処分 |
刑事処分 |
酒酔い運転 |
35点 |
前歴0回で免許取り消し(欠格期間3年) |
5年以下の懲役・100万円以下の罰金 |
|
25点 |
前歴0回で免許取り消し(欠格期間2年) |
3年以下の懲役・50万円以下の罰金 |
|
13点 |
前歴0回で90日間の免許停止処分 |
3年以下の懲役・50万円以下の罰金 |
【車両提供者(事業所・管理者)に対する処分】
分類 |
刑事処分 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役・100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役・50万円以下の罰金 |
【酒類の提供・車両の同乗者に対する処分】
分類 |
刑事処分 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役・50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
2年以下の懲役・30万円以下の罰金 |
アルコールチェック義務化対応のために企業が準備すべきこと
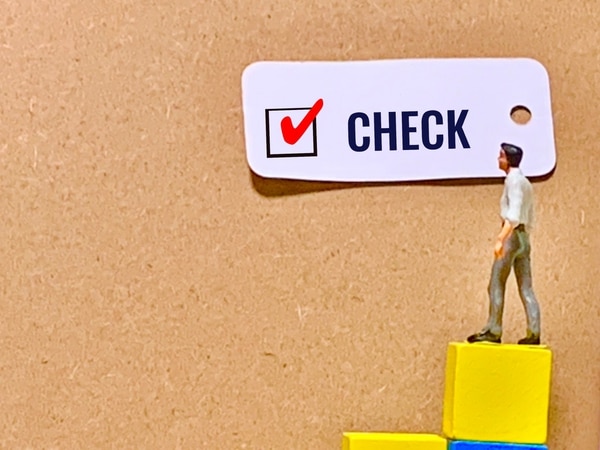
安全に業務を遂行するためにも、アルコールチェック義務化への対応は必須です。
具体的に義務化に向けてどのような準備を行えばよいのか解説します。
安全運転管理者を選任する
まずは、事業所ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。
安全運転管理者を選任した場合、その日から15日以内に事業所がある地域を管轄する警察署へ必要書類を提出しなくてはなりません。
安全運転管理者を選任した際には、道路交通法に基づき公安委員会が実施する「安全運転管理者等法定講習」を選任した人に受講させる必要があります。
選任に関する書類を警察署へ提出すると、講習受講の通知と申出書が送付されるので、毎年1回は受講するように心がけましょう。
アルコールチェッカーを導入する
アルコールチェッカーを使ったチェックが義務化されたため、これまで目視で行っていた事業所は検知器を新たに導入する必要があります。
アルコールチェッカーは正しく計測できるものであれば、どのメーカー・タイプを使っても問題ありません。
現在、各メーカーからさまざまなアルコールチェッカーが発売されています。
自社にとって導入しやすいものがないか比較してみましょう。
★ゼンリンデータコムの「テレマティクスサービス」は車両安全管理にご活用いただけるソリューションです。アルコールチェッカーの提供も可能です
→詳しい資料を見る
記録の保管方法を検討する
アルコールチェックを実施した結果は保存しなくてはならないため、あらかじめ記録の保管方法を決めておくことも大切です。
紙媒体だとPCの扱いが苦手な方でも取り入れやすいメリットがあります。
ただし、紛失するリスクや保管スペースを確保しなくてはならない等、注意すべき点も多いです。
たとえば、Excelを使って記録すれば紙媒体で記録するよりも労力が減り、データ管理も楽に行えるようになります。
ほかの営業所からデータを収集したい場合にも便利です。
その代わり、運転者が多ければその分管理者の負担は増えますし、遠隔地で実施する際には虚偽の申告をされてしまう可能性もあります。
一方、同じPCを使った管理方法でも、クラウドシステムを使って記録する方法は運転者がアルコールチェックを行うとその結果がシステムに自動で送信され、そのまま記録・保管されます。
そのため、記録する手間も省けて、さらに記録漏れのリスクも防げるでしょう。
また、遠隔地にいても不正しにくい点は大きなメリットといえます。
クラウドシステムはExcelと違って費用がかかってしまうものの、利便性や効率性に優れています。
予算面も考慮しながらぜひ導入をご検討ください。
チェック実施のフローを整備する
これまで目視による確認を行っていた事業所でも、検知器を導入しなくてはいけなくなりました。
そのため、チェックを行うときの業務フローを一度見直し、整備する必要があります。
また、実際に運用していく中で運転者から質問・疑問点が投げかけられることもあるでしょう。
このような疑問を解消するために、運用方法をまとめたマニュアルを作成しておくことをおすすめします。
運転者への周知を行う
安全運転管理者は講習も受けるため、アルコールチェックの重要性を認識した上で取り組めるでしょう。
しかし、自動車を運転するすべての従業員も飲酒運転の危険性やなぜ行うのかを理解しておかなくてはなりません。
運転者に周知させるためにも、定期的に安全運転教育を実施することが大切です。
たとえば、社内研修やセミナーを行う、警察庁が配布するリーフレットや資料を事業所内に掲示する等が挙げられます。
まとめ:アルコールチェック義務化に向けた準備を進めよう
今回は、アルコールチェック義務化に関して、改正内容や実施する方法等をご紹介してきました。
2022年4月から目視での確認と記録の保管が義務付けられましたが、2023年12月から検知器の導入が必須となりました。
これまで目視でしか行っていなかった事業所でも、検知器の導入や業務フローの見直し等が必要です。
今回ご紹介した内容を参考にしつつ、アルコールチェックを行う体制を整えていきましょう。
ドライバーの安全運行の維持管理はシステムで効率化!
アルコールチェックも含め、運転者の安全な運行を維持・管理するために「テレマティクスサービス」の活用をご検討ください。
ゼンリンデータコムのテレマティクスサービスは、通信型ドラレコやデジタコ・ドラレコ、OBD-Ⅱ/GPSトラッカー等の連携端末を使い、運行に関するあらゆる情報をクラウドセンターで管理します。
管理した情報を元に業務効率化につながるサービスも提供し、ランニングコストの大幅な削減も可能です。
また、アルコールチェッカーの提供やアルコールチェッカーを活用した運行業務支援も実施しています。
アルコールチェックによる安全管理と業務効率化の両方を目指したい方は、ぜひゼンリンデータコムのテレマティクスサービスの活用をご検討ください。