
店舗DXって何?メリットは?DXの概要や導入事例などを紹介!
昨今聞かれるDXというワードですが、店舗DXというと何を指すのかざっくりとしか分からないという方もいるのではないでしょうか。
店舗DXとは、店舗運用の効率化を含めた、店舗経営するすべての人に関わる要素です。
今回は、店舗DXの概要と導入事例などを説明します。
店舗DXを導入するメリットなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.そもそも店舗DXの「DX」って何?
- 2.DXには店舗運用と店舗体験の2種類がある
- 3.店舗DXが求められている理由
- 3.1.人員が不足している現場が増えている
- 3.2.ECサイトを利用する人が増えたため
- 4.店舗DXを導入する3つのメリット
- 4.1.サービスの向上と効率化
- 4.2.人員不足を補える
- 4.3.感染症への不安から接触を嫌う人に配慮できる
- 5.店舗DXを推進する際の課題
- 5.1.システムへの移行・連携コストがかかる
- 5.2.人材の育成・教育が必要
- 5.3.導入の効果を得るには時間が必要
- 6.店舗DXを導入事例
- 7.まとめ 店舗DXは効率化と顧客満足度アップの両立が実現できる!積極的に導入しよう
- 8.店舗DXを推進するならぜひゼンリンデータコムにご相談ください!
そもそも店舗DXの「DX」って何?

店舗DXというワードに用いられるDXは、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)を指します。
直訳すると、デジタル技術を駆使して変革させることです。
DX自体は、多店舗展開や立地戦略などにも用いられるため、店舗運用にとどまらず、多くの箇所でDX化が進んでいます。
店舗DXとは、データやデジタル技術を駆使することで、店舗経営やビジネスモデルを根本から替えることです。
店舗DXが導入されるようになった背景には、SNSが流行し、情報が飽和している現代社会が関係しています。
店舗経営をする企業は、情報社会における顧客のニーズに合った商品や、サービスの提供方法を模索しなければならない状況になりました。
流行の移り変わりが早い社会に対応するため、価格や質の競争に勝とうとデジタルを駆使する企業が増えています。
DXには店舗運用と店舗体験の2種類がある
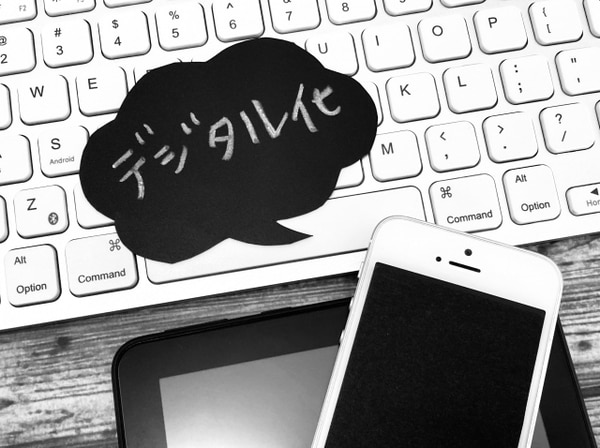
店舗DXは、店舗運用と店舗体験の2つに用いられます。
店舗運用
店舗運用にDXを導入する理由のひとつに業務効率化があります。
電子マネーやクレジットカードの決済システム導入によるキャッシュレス化などもDXの例といえます。
キャッシュレス化することで、会計手続きなどを簡略化することが可能です。
手作業では非効率な業務をデジタルに任せて負担を減らし、人手が必要な業務にリソースを割けられます。
店舗体験
店舗体験にDXを導入すると、店舗全体をオンライン化できます。
これまで直接接客していた飲食店がオンライン注文を導入するケースがありますが、これが店舗体験におけるDX化の一例です。
導入事例の詳細については、後述で触れていきます。
店舗DXが求められている理由

店舗DXが求められている理由は、主に2つ挙げられます。
ここからは、導入が増えている理由を説明します。
人員が不足している現場が増えている
店舗DXが望まれている理由のひとつに、店舗経営における人員不足が関係しています。
TDB景気動向オンラインに掲載された記事によると、正社員における人手不足企業の割合が、2022年10月の時点で50%を超えているとの調査結果が出ています。
出典:帝国データバンク 人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)
店舗運用は非正規雇用従業員に支えられているところが多いですが、少子高齢化の影響により年々働き手が足りなくなってきています。
そのため、デジタルを導入して運用できる業務はなるべくDX化をし、人手不足を補おうとする企業が増えてきました。
少子高齢化は現在も続いているため、これまで以上にDXを導入する店舗は増えるでしょう。
ECサイトを利用する人が増えたため
ECサイトで売買する顧客が増えたことも理由のひとつです。
家の中で注文して配達してもらうECサイトは、利便性の高さから需要が増しています。
スマートフォンが普及したことで気軽に注文しやすくなり、近年では新型コロナウイルス流行による自宅待機時間の増加や人との接触への不安から、積極的に利用した方も多いのではないでしょうか。
ECサイトはデジタルにあたるので、店舗DXのひとつといえます。ECサイトの利用者が増える=店舗DXの需要増加と紐づけられるでしょう。
昨今は、これまでECサイトを運営していなかった飲食業や販売業が、自社のホームページにECサイトをつくったり、大手のオンラインマーケットに自社のネットショップを開設したりする動きをみせています。
ECサイトを利用する企業の増加と共に、DX化の流れがより加速するかもしれません。
店舗DXを導入する3つのメリット

ここからは、店舗DXを導入する際の3つのメリットを紹介します。
サービスの向上と効率化
店舗DXの導入によるメリットのひとつは、サービスの向上と効率化です。
これまでの対面の接客においては、どうしても予約の漏れや注文漏れなどのヒューマンエラーが起きる場合もあります。
また、会計スタッフが経験の浅い方だと、なかなか会計が進まず、顧客によってはストレスが溜まってしまう可能性もあります。
そのようなときに、オンライン予約やセルフレジなどを導入すれば、問題解決の要因となり、サービスの品質が向上するでしょう。
また、売り上げを自動集計してくれるようなシステムを導入すれば、売上管理業務の効率化ができるなど、いままで多くの時間がかかっていた業務時間の短縮が可能です。
このように、サービスの向上と効率化を図れる点がメリットといえるでしょう。
人員不足を補える
先ほども触れましたが、人手不足の解消にはDX化が役立ちます。
どうしても人の手が介入せざるをえない業務は「人」に、デジタルやデータを活用できる業務はDX化をすることで、業務の分担が可能となり、人手不足の不安を解消できるでしょう。
人手とデジタルの役割分担は人手不足の解消だけではなく、効率化やサービス向上につながる一石二鳥のメリットを得られます。
感染症への不安から接触を嫌う人に配慮できる
新型コロナウイルスが流行して以降、感染への不安から人との接触を拒む顧客も増えてきました。
店舗DXは、感染に不安を覚える人に配慮した店舗運用ができるのもメリットです。
DX化によりデジタルを通したやり取りが顧客と店員の間で可能となるため、非接触でオーダーや会計ができるようになります。
これにより、感染防止のアルコール消毒やアクリル板等の設置箇所を減らすことでき、コスト削減も実現可能です。
店舗DXを推進する際の課題

人手不足を解消しながら効率化まで図れる店舗DXですが、以下のような課題もあります。
システムへの移行・連携コストがかかる
店舗DXの課題として、システムへの移行・連携コストがかかることがあげられます。
DX化は人件費におけるコストダウンがメリットのひとつですが、初期投資として導入する際は逆にコストがかかります。
そのため、初期投資のコストに加え、店舗DXの導入後にすでに使用しているシステムからのデータ移行や、連携をする際のコストも試算して導入を検討しましょう。
詳しくは後述で触れますが、人材育成や教育にかかるコストや、導入してすぐに効果を得られるものではない点を踏まえて、初期コストを投じなければなりません。
人材の育成・教育が必要
業務をデジタルに任せることで効率化が可能となるDX化ですが、あくまでデジタルやデータを活用するのは「人」の手です。
働き方が大きく変化するため、従業員に対して新しい業務を教えなければならず、育成と教育の時間をかける必要があります。
また、従業員側も、使用者側の都合でこれまでの働き方がリセットされ、新しい内容を覚えることに負担を感じます。
従業員側の理解を得ておかないと、不満からモチベーションの低下につながりかねません。事前にしっかりとコミュニケーションを取るべきでしょう。
導入の効果を得るには時間が必要
DX化は、導入の効果を得るまでに時間を要します。
初期コストの負担が大きい上に、従業員側に対して理解を得たり新たな業務マニュアルを作成したりと、導入直後は金銭面だけでなく教育に要する時間的な負担面の課題も多いです。
DX化はそのような課題に対し、時間をかけてクリアすることで、業務効率化とコストダウンが実現できます。
また、導入後は定期的に効率化やコストダウンにつながった箇所をチェックし、うまくいかなかった箇所はDXの運用方法の改善を図る必要があるでしょう。
店舗DXを導入事例

ここからは、店舗DXの導入事例について紹介します。
店舗運用と店舗体験双方の事例について紹介するので、導入をご検討の方はぜひご覧ください。
店舗運用の場合
店舗運用におけるDXのひとつとして、効率的に店舗情報の管理をするためのツール導入があります。
店舗情報ページを一元管理し、経営している店舗を地図上で表示したり、今後のイベントスケジュールを店舗ごとに確認することができます。
特に多店舗展開している場合は、店舗すべての情報を一度に更新したり、修正するのも非常に工数がかかります。
しかし、デジタルを介して情報管理をすることで各店舗の状況を詳細に記録でき、経営者側は蓄積された情報をいつでも閲覧できます。
店舗情報に紐づけて取り扱い商品の管理や危機管理・災害情報もチェック可能です。
もしものことが起こった場合の緊急対応の指示や、復旧対応の情報共有が迅速に行えます。
以上のことから、とくに多店舗展開している企業は積極的に店舗DXを行い、店舗運用をデジタルに任せるケースが多いです。
★店舗情報の管理・可視化なら「Area Marker」
→まずはサービスを見てみる
店舗体験の場合
店舗体験のDX導入事例のひとつとして、ホームページや店舗に店舗内部の3Dマップを公開しているケースです。
ショッピングモールなど多くの店舗がひしめき、出店や移転・閉店などが頻繁に起こる業態では、ホームページ掲載のマップや店内マップの更新作業も大きな負担です。
システム上で管理・修正・公開管理が行えるツールを活用することで、担当者の業務効率化になり、且つお客様は常に最新の情報を取得できる状態になります。
まとめ 店舗DXは効率化と顧客満足度アップの両立が実現できる!積極的に導入しよう
店舗DXは、初期コストに加え従業員の育成や教育といった課題があり、導入直後はあまりメリットを実感できないかもしれません。
しかし、導入が進むにつれて人の手では時間のかかる業務の効率化や、デジタルに任せた業務に人件費をかけないことによるコストダウンなど、中長期的スパンで考慮するとメリットが多いです。
初期コストを投じる余裕がある状況下で、従業員側の理解を得られているなら、店舗DXを導入してみてはいかがでしょうか。
店舗DXを推進するならぜひゼンリンデータコムにご相談ください!
ゼンリンデータコムは、店舗DXを推進する上で役立つサービスを提供しています。
店舗のデータをデジタルで一元管理し、蓄積されたデータを効率的に活用するなら「Area Marker」がおすすめです。
「Area Marker」は、多店舗を運営する方に特におすすめのツールで、たとえば都道府県をまたいで多店舗展開をしていても「Area Marker」を通して、データ管理と店舗のサービスや方針の共有ができます。





