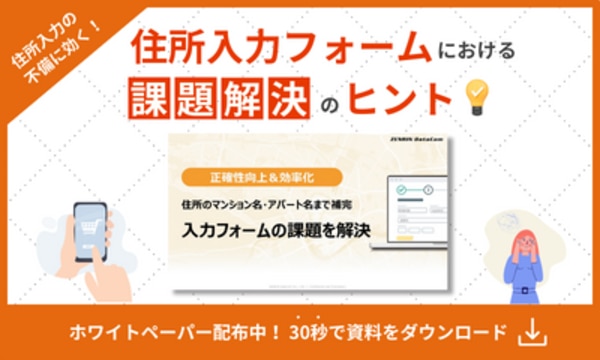積載効率とは?計算方法と向上のメリットを詳しく解説
物流業界では、多くの企業が「いかに積載効率を高められるか」を重視しています。積載効率が高まることで、貨物の積み込みや輸送など、物流プロセス全般の効率性が向上し、企業にとって多くのメリットが得られます。
そこで今回は、積載効率とは何か、その計算方法や向上のメリット、効率性を高める具体的な方法について詳しく解説します。また、実際の取り組みによって積載効率が改善された事例もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
■物流課題の解決・DX化に「ZENRIN ロジスティクスサービス」! |
目次[非表示]
- 1.積載効率とは?
- 2.積載効率の計算方法
- 3.積載効率を高める具体的な方法
- 3.1.商品カテゴリーの集約によるスペース最適化
- 3.2.共同配送の導入
- 3.3.運行管理システムの活用
- 4.積載効率を向上させるメリット
- 4.1.輸送コストの削減
- 4.2.人手不足の解消
- 4.3.荷物の破損リスクの軽減
- 5.積載効率改善の事例紹介
- 6.まとめ:積載効率を高めて物流コストを削減しよう
- 7.ZENRIN ロジスティクスサービスで積載効率を最大化
積載効率とは?

積載効率とは、輸送手段の許容積載量に対して実際に積み込んだ貨物の割合で示す指標です。例えば、小型トラックの最大積載量が1トンの場合、積載した貨物の重量が1トンに近いほど積載効率が高いと言えます。
積載効率が高いと、一度に多くの貨物を運べることができるため、物流コストの削減や環境負荷の低減が期待できます。また、積載効率の高いことで輸送時間の短縮にもつながり、物流プロセスの最適化を実現することが可能です。
■物流のコスト削減なら「ZENRIN ロジスティクスサービス」! |
積載効率の計算方法
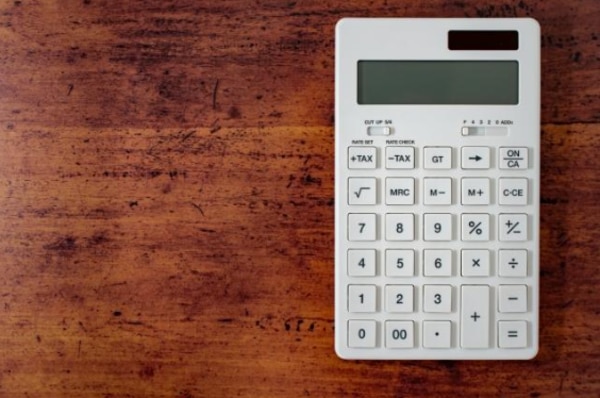
積載効率を計算するには、積載重量÷最大積載重量×100で計算できます。例えば最大積載量10トンのトラックに7トンの貨物を積載した場合、積載効率は以下のようになります。
7トン÷10トン×100=70%
つまり、トラックの最大積載重量に対して70%の貨物を積めていることがわかります。ただし、荷物を降ろしてから会社に戻る際には荷物がないため、積載率は0%になります。そのため、平均積載率は(70%+0%)÷2(往復)=35%です。
複数箇所で積み下ろしを行う場合、途中で荷物の増減があるため、その量に応じて積載効率も変動します。
積載効率を高める具体的な方法

積載効率を向上させて効率的な輸送を実現させるためには、どのような対策を講じるべきなのでしょうか?ここでは、積載効率を高める具体的な方法を解説します。
商品カテゴリーの集約によるスペース最適化
積載効率を向上させる方法の一つとして、商品カテゴリーを集約してスペースの最適化することが挙げられます。
トラック庫内スペースを有効に活用するためには、商品カテゴリーの細分化を避けることが必要です。カテゴリーが細かく分かれていると、コンテナに入れられる商品の数が減ってしまいます。
しかし、商品カテゴリーを集約することで、コンテナにより多くの商品を詰め込むことができ、結果として多くの貨物を運ぶことが可能になります。
★AI自動配車・ナビゲーションアプリで物流DX の「ZENRIN ロジスティクスサービス」 |
共同配送の導入
共同配送とは、複数の企業がトラックや拠点等を共有し、荷物をまとめて配送することを指します。例えば、同じ方面に届ける荷物がA社は3トン、B社は5トンある場合、それぞれの会社がその量を運べるトラックを持っていないと、最大積載重量が多いトラックを使用することになり、無駄なスペースが生じてしまいます。
しかし、A社とB社が協力して共同配送を行うことで、10トントラック1台に両者の荷物を積載して運ぶことが可能になります。これにより、トラックの積載効率が向上するだけでなく、空車走行の減少や配送ルートの最適化によるコスト削減・環境負荷の軽減が期待できます。
さらに、近年ではドライバーの人手不足や物流コストの増加といった問題が顕在化しているため、今後ますます共同配送の導入が進むと考えられます。
運行管理システムの活用
積載効率を向上させるためには、1台の車両だけでなく、自社が所有する全ての車両の走行距離や積載状況をリアルタイムで把握することが重要です。
車両の現在位置や運行ルートを把握し、積載率と合わせて考慮することで、より効率的な運送が可能になります。これらのデータを迅速に管理・収集するためには、TMS(輸配送管理システム)の導入がおすすめです。
TMSは配送の各工程における情報を管理し、効率化を図るためのシステムです。主に配車管理・動態管理・コスト管理の3つの機能をを持っています。
機能 |
詳細 |
配車管理 |
車両数や積載量、ドライバー、交通状況等を考慮した上で、 最適な配車や配送計画を作成する機能 |
動態管理 |
配車管理機能で作成した配送計画がきちんと遂行されているか、 リアルタイムに車両情報を得ることで確認する機能 |
コスト管理 |
各トラックの走行量や消費燃料等を計算し、 配送にかかるコストを管理する機能 |
積載効率を向上させるメリット

積載効率を向上させることで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?続いては、積載効率を向上させるメリットを紹介します。
輸送コストの削減
積載効率を向上させることで、輸送コストの削減というメリットがあります。輸送コストとは、貨物をある場所から別の地点へ運ぶ際に発生するすべての費用を指します。
例えば、トラック輸送の場合、燃料費、ドライバーの人件費、高速道路の通行料金、保険料などが含まれます。また、倉庫での荷役作業や積み下ろし、梱包作業にかかる費用、輸送中の保管費用も輸送コストの一部です。
積載効率が向上すると、トラック2台で輸送していた貨物が1台に収まることがあり、その結果、燃料費やドライバーの人件費、通行料金、保険料などの輸送コストを削減できます。
また、積載効率の向上に伴い配送計画が最適化されることで、空車走行を減らし、さらに輸送コストの低減することが可能です。
人手不足の解消
物流業界はEC市場の拡大に伴い需要が増加していますが、一方でドライバー不足が深刻化しています。内閣府が公開した「地域の経済2023 補論(1)」によると、トラックドライバーの就業者数は1995年の98万人をピークを迎えましたが、2020年には77.9万人まで減少していることが明らかになりました。
さらに、道路貨物運送業の年齢構成を見てみると、2022年における全産業の50代の比率は21.8%なのに対し、道路貨物運送業は29.8%と約3割が50代で占めていることがわかります。このまま若年層の担い手が増えない場合、高齢層の退職に伴い、労働力不足がさらに深刻化する可能性が高いです。
積載効率を向上させることで、一度に運べる貨物量が増え、往復する回数が減少し、労働環境の改善も期待できます。労働環境が改善されると、若年層の担い手も増え、人手不足の解消につながるでしょう。
★AIによる最適な配送ルート作成で、燃料費や人件費等のコスト削減! |
荷物の破損リスクの軽減
物流業界において、輸送中の荷物が破損するリスクもあります。荷物が破損することで顧客満足度は低下し、企業に対する信頼度も落ちてしまうでしょう。
荷物が破損する原因として考えられるのは、輸送中の衝撃や振動による影響、荷物の不適切な扱いや積み方等が挙げられます。
積載効率を向上させ、トラックの庫内に空きスペースをつくらせないようにすると、コンテナが移動するリスクも軽減し、荷物が破損する可能性を抑えられます。
また、積載効率を高めるとそのトラックに適した量の貨物を積載できるようになり、過積載を防げて事故のリスクも抑えることが可能です。
荷物の破損リスクが軽減、顧客されることで、顧客満足度も向上し、経営の安定化につながります。経営が安定すれば最新機器の導入も可能となり、さらなるサービス品質の向上が期待できます。
積載効率改善の事例紹介
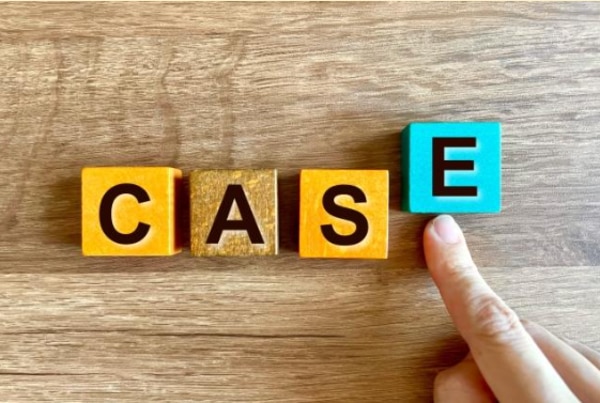
積載効率を改善・向上させるためには、自社の問題点を把握し、適切な対策を講じることが必要です。
しかし、具体的にどのような方法をとればいいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。そこで、ここからは、積載効率を実際に改善・向上させた事例を3つ紹介します。
AI配車システム導入による積載効率改善事例
納品条件の影響で効率化が難しいとされてきたチルド販売物流において、AI配車システムを導入し、積載効率を改善した事例です。
チルド商品はリードタイムが短いため、低積載になりがちで非効率な輸配送が行われていました。この問題を改善しようと導入されたのが、AI配車システムです。
これまでは担当者が経験に基づいて配送ルートを最適化していましたが、AI配車システムの導入により、さらに効率的な配送ルートの作成が可能になりました。
また、効率的な配送計画に基づき、得意先との納品条件の変更や現場の作業改善等も行われたことで、車両台数の削減や積載効率の向上が実現しました。
実際の効果として、年間で使用した車両台数は4,745台となり、前年より28%の削減に成功しました。また、年間積載率も19%向上し、71%に達しました。
参考:「令和4年度物流パートナーシップ優良事業者表彰」において「物流DX・標準化表彰」を受賞しました。
段ボール箱の標準化による積載効率改善事例
切り花の卸売業を営む企業が、ドライバーの待機時間短縮を目指し、段ボール箱の標準化によって積載効率が改善した事例です。
切り花は種類が非常に多く、花を入れる段ボール箱のサイズも様々でした。段ボール箱のサイズが異なるため、パレットへの荷積みが難しく、積載効率が低下していました。そのため、これまではパレットを使わずに段ボール箱を直接積み込んでいました。
しかし、この方法では積み込みや荷下ろしに時間がかかり、ドライバーの負担が増えてしまいます。そこで、パレット荷積みに変更するために段ボール箱のサイズを標準化しました。
パレットのサイズに合わせて段ボール箱を標準化したことで、積載効率が向上しました。また、大型トラック1台あたり、1日1万円の人件費削減や、作業時間を2時間弱短縮させることに成功しました。
■物流課題の解決・DX化に「ZENRIN ロジスティクスサービス」! |
パレット輸送化による積載効率向上事例
家庭紙を取り扱うメーカーが、同業他社に呼びかけて業界全体で統一したパレットを開発し、積載効率を向上させた事例です。
4社が共同で任意団体を設立し、パレットのレンタル・回収業務を共同で行えるようにしました。
さらに、家庭紙業界専用の統一パレットを開発したことで、同一パレットのグループ内で混載発注が可能となり、積載効率の低下を防ぐことができました。
また、ドライバーによる積み下ろし作業が倉庫側のフォークリフトによる荷下ろし作業に代わり、作業時間が約90分から約20分まで短縮することができています。
まとめ:積載効率を高めて物流コストを削減しよう
今回は、物流業界における積載効率について解説してきました。物流業界は人手不足や環境負荷への対策など、さまざまな問題を抱えていますが、積載効率を向上させることでコスト削減や人手不足の解消が期待できます。
今後、持続可能な物流を目指すためには、積載効率の改善・向上が欠かせない要素となります。今回ご紹介した取り組みや事例を参考に、積載効率の改善・向上に向けて取り組んでいきましょう。
ZENRIN ロジスティクスサービスで積載効率を最大化
積載効率を改善させるためには、最適な配送計画の作成に加え、リアルタイムの情報を活用した動態管理が必要です。「ZENRIN ロジスティクスサービス」は物流事業者様やシステムベンダー様向けに、物流の効率化を支援するサービスです。
ZENRINの強みである正確な地図情報を活用し、お客さまのニーズに合わせた最適なサービスをご提供いたします。
例えば、「AI自動配車」機能を活用することで、誰でも効率的な配車計画を作成でき、配車・配送にかかる時間や車両台数、燃料費の削減が可能です。
現在使用している業務アプリとの連携や、地図情報、住所検索、ルート機能などの各種APIもご用意しているので、積載効率を最大化し、効率的な物流業務を実現したい方は、ぜひZENRIN ロジスティクスサービスの導入をご検討ください
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/