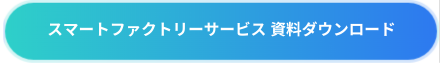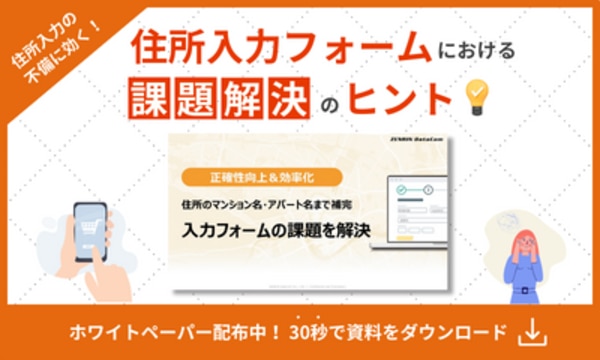屋内測位とはどんな技術?用途や測位手法別の特徴、その選び方を解説
屋内測位とは、GPSのような位置情報取得の技術です。
屋内測位には、さまざまな手法があり、多様な用途で使用されています。
この記事では、屋内測位がどういったものなのか、その手法や特徴を解説していきます。
屋内測位の活用シーン例や選択するときのポイント等も解説しているので、屋内測位を導入しようと検討している方は、ぜひ参考にしてください。
★屋内測位技術を用いて、倉庫や工場内の業務改善が可能です!
→サービスの詳細を見てみる
目次[非表示]
- 1.屋内測位(インドアマッピング)とはどのような技術?
- 2.屋内測位の11の手法の特徴を比較
- 2.1.Wi-Fi測位
- 2.2.ビーコン測位
- 2.3.RFID測位
- 2.4.歩行者自立航法測位
- 2.5.IMES測位
- 2.6.音波測位
- 2.7.地磁気測位
- 2.8.UWB測位
- 2.9.可視光測位
- 2.10.垂直測位
- 2.11.マーカー測位
- 3.屋内測位技術の活用シーン例
- 4.屋内測位手法を選択するときのポイント
- 4.1.用途に合った機能を備えているか
- 4.2.コストはどれくらいかかるか
- 4.3.簡単に機器を設置できるか
- 4.4.保守・運用は容易か
- 4.5.アプリと連携できるか
- 5.まとめ:用途に適した屋内測位手法を導入しよう!
- 6.屋内測位を用いた工場や物流センターの可視化なら「スマートファクトリーサービス」!
屋内測位(インドアマッピング)とはどのような技術?

屋内測位(インドアマッピング)とは、位置情報を取得する技術のことです。
スマートフォンの地図アプリやカーナビは、GPSで位置情報を取得し、現在位置を表示させています。
しかし、電波の入らない地下や屋内ではGPSが使用できません。
そういったGPSが使用できない場所でも位置情報を取得できる技術が屋内測位です。
屋内測位は、電波の入らない場所にある倉庫の荷物の位置管理等にも利用されています。
★屋内測位技術で倉庫や工場を効率化!「スマートファクトリーサービス」
→サービスの詳細を確認する
屋内測位の11の手法の特徴を比較

屋内測位にはさまざまな種類があります。
以下に、屋内測位の代表的な11の手法の特徴をご紹介します。
屋内測位技術 |
特長 |
主な用途 |
Wi-Fiアクセスポイントを利用 |
商業施設、オフィス |
|
低コストで導入可能 |
美術館、博物館 |
|
個体識別にも利用可能 |
工場、倉庫 |
|
スマホのセンサーのみで利用可能 |
ナビゲーション |
|
高精度な測位が可能 |
医療、製造 |
|
障害物に強い |
倉庫、工場 |
|
安定した測位が可能 |
ロボット、車両 |
|
高精度かつリアルタイムな測位 |
AR/VR、産業用ロボット |
|
カメラを利用した測位 |
店舗、イベント会場 |
|
高層ビル内での測位 |
高層ビル内でのナビゲーション |
|
マーカーを利用した測位 |
建設現場、工場 |
Wi-Fi測位
Wi-Fi測位とは、Wi-Fiのアクセスポイントに複数接続されることでデバイスの位置を測定する手法です。
アクセスポイントからデバイスまでの距離を電波の強さや伝達時間等で判断し、正確な位置を把握します。
デバイス側からは特別な操作は必要ありません。
位置情報の提供に同意してもらうだけなので、導入にコストがかからないという利点があります。
しかし、個人情報の漏えいリスクがあるので運用には注意が必要です。
ビーコン測位
ビーコン測位とは、BLEビーコンを使った位置情報取得技術です。
ビーコンは狼煙(のろし)という意味で、煙の代わりにBluetooth4(BLE)電波を使用します。
ビーコンが発する電波をスマホや受信機で受信し、その電波の強さからビーコンまでの距離を測るという位置測位の方法です。
ビーコン測位での有効半径は10〜100mほどで、取得する位置には1〜5mの誤差が生じます。
ビーコン測位の有効範囲はGPSより狭く、また周辺の物等による反射や電波の干渉で誤差が生じる場合もあります。
しかし、電力消費が少なく、小型軽量化が可能です。
また、受信機は市販デバイスを使用することでコストを抑えられる等といった利点があります。
RFID測位
RFID測位とは、無線通信タグを商品等につけ、位置を測定する手法です。
RFIDタグを専用のリーダーで読み取ることで、どの位置にタグがあるのかを取得します。
タグには、自ら電波を発するものと、リーダーから発せられた電波を返すものがあり、通信可能範囲は数cm〜数mとそこまで広くはありません。
RFIDは、バーコードのようにスキャンする必要がなく、非接触での読み取りが可能です。
スキャンするのが難しい高所にある荷物等の管理に役立てられます。
また、障害物があっても読み取りが可能なので、箱の中にある商品のタグでも認識できます。
複数のタグの一括読み取りも可能で、タグのデータの書き替えもできるので、多数の荷物を管理するのに便利です。
しかし、導入コストが高い点には注意が必要です。
タグが1枚約10円と、管理する荷物の数が多ければ多いほどコストが高くなってしまいます。
歩行者自立航法測位
歩行者自立航法測位とは、PDR(Pedestrian Dead Reckoning)とも呼ばれている手法です。
歩行者が端末を所持し、その移動速度や角度等から位置を測定します。
端末には、「加速度センサー」や「磁気センサー」「ジャイロセンサー」が搭載されていて、これを持ち歩くことにより歩行者がどこにいるかを取得しているのです。
歩行者自立航法測位は、「絶対位置」ではなく「相対位置」で測定するため、スタート位置を正確に指定する必要があります。
また、移動していくごとに誤差が大きくなっていってしまうので、その都度補正が必要です。
歩行者自立航法測は、単独で使用するよりも、他の測位法と組み合わせて使用することで、より精度が高まります。
IMES測位
IMES測位とは、日本独自の技術です。
宇宙航空研究開発機構JAXAが民間企業と考案しました。
GPS衛星と同じ構造の電波を発信するIMES送信機を屋内に設置することで、GPS電波の届かない屋内でも測位が可能となる技術です。
IMES測位では、測位対象が何階にいるかといった高さまでわかります。
各フロアの利用者がよく通過する場所等にIMES送信機を設置し、利用者は自分のスマートフォン等で現在位置を確認します。
音波測位
音波測位とは、超音波を使用した測位の手法です。
子機から発信される超音波を、親機が受信することで位置の特定をします。
スマートフォンのマイクでも受信可能なので、スマートフォンを親機としても使用できます。
音波測位は、電波を使用した測位に比べて指向性が高く、より正確な位置検知が可能です。
また、音波は電波と違って壁を突き抜けることができないため、部屋と部屋の区別や吹き抜けのあるフロアの区別等に向いています。
しかし、音波測位は高精度な位置検知が可能ですが、導入コストは高い傾向にあります。
また、子機を電池駆動で長時間稼働させておくといった工夫も必要です。
地磁気測位
地磁気測位とは、地球の持つ地磁気を利用して位置を観測する手法です。
スマートフォンやタブレット等に搭載されたセンサーと専用アプリで、場所によって変わる地磁気データを観測します。
あらかじめ屋内マップを作成しておき、地磁気データと照合することで現在位置や移動履歴を取得します。
地磁気測位は、誤差2m程度と高精度な測位をリアルタイムで行えるのが特徴です。
地図アプリや、商業施設のナビ、屋内災害時の避難にも活用されています。
地磁気センサーには特別な機器設置は必要ありません。
そのため、スピーディーで低コストな導入が可能です。
しかし、地磁気が乱れる場所の測位は苦手であり、端末によっては誤差が出ることや、データ測定と管理には手間と時間がかかるといった注意点もあります。
UWB測位
UWBとは、「Ultra Wide Band」の略です。
超広帯域の無線通信技術といった意味があります。
タグが発信する電波を2個以上のセンサーで受信して測位する手法で、電波の到着時間や信号の角度から高精度な位置取得が可能です。
タグの電波を受信して位置を測るのはビーコン測位と同じですが、ビーコン測位が電波の強弱で測位するのに対して、UWB測位は電波の到達時間で測位します。
そのため、UWB測位は少ないセンサーの設置数でも高い精度での測位が可能です。
UWBの電波は到達距離の最長が30m程度、誤差は数10cmと非常に正確です。
消費電力が少ないのも特徴といえるでしょう。
ビーコンと比べて、電波の到達距離も正確性も上回っています。
しかし、まだ広く採用されていないため、コストが高く地域によって規制が異なるといった注意点もあります。
可視光測位
可視光測位は、目に見える光を利用して測位する手法です。
ビーコン測位やUWB測位が電波を使用するのに対して、可視光測位はLED照明等の光を使用し、LEDの光を高速に点滅させ信号を送ることで位置情報を伝達します。
可視光測位はすでにある照明器具を専用のLEDに切り替えるだけで使用できます。
そのため、導入コストや手間を抑えることが可能です。
また、カーテンや仕切りで遮光することで通信の遮断もできます。
電波通信のような情報漏えいのリスクが低く、他の機器への影響もありません。
ただし、障害物があると通信できない点や環境に干渉されることが多いといった点には注意が必要です。
垂直測位
垂直測位とは、気圧データを使用して位置を取得する手法です。
GPSの位置情報と気圧データから、現在地の高さを算出できます。
GPSでわかる位置情報は平面のみですが、垂直測位では高さが加わり、三次元での位置情報の取得が可能です。
垂直測位は、2〜3mの精度で高さの特定ができるので、ビルの何階にいるかということもわかります。
そのため、ビル火災等の災害時にも役立ち、火災が起きた際には火災現場や逃げ遅れた人の把握ができるので、消火活動が効率的に行えます。
マーカー測位
マーカー測位は、「AR(拡張現実)」を応用した手法です。
マーカー測位では、専用の紙状媒体のマーカーを資材や室内の柱や壁に貼りつけ、カメラで撮影することで位置を測位します。
室内に取りつけるマーカーを「基準点マーカー」、荷物につけるものを「資材マーカー」と呼びます。
基準点マーカーと資材マーカーをカメラで撮影することで、位置情報を取得するのです。
ビーコン測位等と異なり、特殊な装置は不要で、紙で印刷したマーカーをつけるだけなので導入が簡単です。
測位の精度は1mと高精度で、資材の位置の把握等に役立ちます。
屋内測位技術の活用シーン例

屋内測位技術は具体的にどのように活用されているのでしょうか。
ゼンリンデータコムの「スマートファクトリーサービス」を例にご紹介します。
「スマートファクトリーサービス」は、現場から得られるデジタルデータを活用して、工場内などのボトルネックを把握し、改善提案を行うサービスです。
様々な屋内測位技術を課題に合わせてご提案可能で、計測・データ集計・分析・レポートまで行います。
たとえば、フォークリフトの稼働率の偏りや、作業エリアの広さの違いを明らかにし、工場内レイアウトの変更やフォークリフトの利用用途の再検討に役立てることが可能です。
また、屋内測位を利用した作業員の作業実態の明確化も行えます。
作業員の待ち時間や準備作業等が数値化され、実態の把握が可能です。
作業員の作業実態がわかることで、作業分担や工場レイアウトの見直しにも役立ちます。
★関連記事:スマートファクトリーとは?
屋内測位手法を選択するときのポイント

屋内測位には、上記で紹介したものやそれ以外にもさまざまな手法があり、何を選べばよいか迷ってしまうことも多いでしょう。
屋内測位手法を選択するときに考慮するべきポイントを以下にまとめました。
用途に合った機能を備えているか
屋内測位はそれぞれの手法で違った機能を備えています。
自分が使用する目的に必要な機能が備わっている測位法でなければ、導入する意味がありません。
たとえば、高層商業ビルでのナビゲーションなら、何階にいるかといった高さ位置の取得が必要であるため、垂直測位法等がおすすめです。
高さ位置の取得ができない手法では、ビル内での位置を正確に取得できません。
どういう目的で、どのように使用するか、そのためにはどういった機能が必要か、といった情報をきちんと精査してから選択しましょう。
コストはどれくらいかかるか
屋内測位法を選択するときに、気になるのはコストではないでしょうか。
できるだけコストは抑えたいと考えている人が多いことでしょう。
とくに、コストを抑えたい方には、ビーコン測位と地磁気測位がおすすめです
しかし、コストが安かったとしても使いにくかったり、目的のことができなかったりするのでは困ります。
このくらいの金額は出せるという予算ラインと、必要な機能や精度といった性能とのバランスが大事です。
機能と価格を比較し、コストパフォーマンスのよい測位法を選びましょう。
簡単に機器を設置できるか
屋内測位の導入には専用機器を設置する手法が多くあります。
電源を引く必要があるものや、特殊な機器を設置する必要があるものもあるので注意が必要です。
機器設置がしやすい手法としては、ビーコン測位や地磁気測位がおすすめです。
電源を引く必要がないだけでなく、遮蔽物が多い場所でも使用することが可能です。
設置する場所によっては、電源の確保が困難な場合や、スペースがない等で機器の設置が不可能な場合もあります。
導入する環境を調査し、使用したい手法の機器の設置が可能かどうか前もって確認することが大切です。
保守・運用は容易か
測位システムは導入して終わりではありません。
その後も継続してデータを取得し、運用していく必要があります。
また、システムの不具合やアップデートへの対応、ハード交換のサポート業務も行う必要があります。
導入はできても、保守・運用ができなければ、継続した使用は難しいでしょう。
電池を使用するビーコンや、自ら電波を発するタイプのRFIDは電池切れのときに機器を一つひとつ確認する必要があるので運用が大変ですが、電源のいらない地磁気は管理が簡単でおすすめです。
アプリと連携できるか
屋内測位では、スマートフォンを受信端末にすることが考えられます。
スマートフォンを受信端末にするときに必要なのがアプリです。
アプリと連携すると、簡単にスマートフォンで位置情報の取得ができます。
アプリ連携ができる屋内測位の手法はさまざまありますが、導入しやすいのはビーコンです。
コストが安く設置も簡単なうえにアプリとも連携ができて非常に使いやすい手法といえます。
他にもアプリ連携のできる測位法はいろいろあるので、自分に合ったものを見つけましょう。
まとめ:用途に適した屋内測位手法を導入しよう!
屋内測位にはさまざまなものがあり、それぞれ利点や注意点、特徴が違います。
導入する目的や、場所、使用方法、かけられるコストや手間を考え、自分に合ったものを導入しましょう。
その際、さまざまな手法をじっくり比較して検討することが大切です。
実際の使用例等も参考にしてみましょう。
屋内測位を用いた工場や物流センターの可視化なら「スマートファクトリーサービス」!
工場や物流センターで屋内測位を使用して、業務の最適化を行うなら、ゼンリーデータコムの「スマートファクトリーサービス」をご検討ください。
ゼンリーデータコムでは、さまざまな屋内測位技術に対応しており、目的に応じた最適な屋内測位の提案をすることが可能です。
たとえば、以下のような提案ができます。
- 高精度測位を導入し、倉庫のレイアウトの変更や移動ルールの設定を行う
- RFIDを導入して、製造工程における製品の追跡や在庫管理進捗管理を行う
- 簡易ビーコン測位を導入し、非作業時間の作業再割り当てやシフトの見直しを行う
「自分に合った測位法がわからない」「目的や条件を検討する時間がない」という方は、ぜひゼンリーデータコムの「スマートファクトリーサービス」をご検討ください。