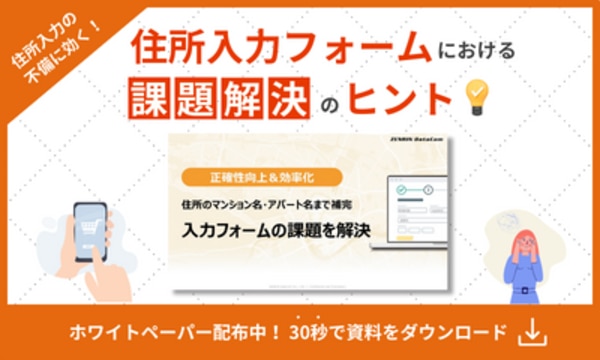13種類の用途地域の特徴を徹底解説│用途地域の調べ方も紹介
都市計画では、地域ごとに特定の用途が定められており、その用途以外での土地開発は制限されることがあります。このように、あらかじめ用途が決められている土地を「用途地域」と呼びます。
用途地域は全部で13種類あり、それぞれに異なる特徴があります。本記事では、これら13種類の用途地域の特徴を詳しく解説します。
また、用途地域を調べる方法についても説明しますので、興味のある方はぜひご覧ください。
★用途地域を地図上に重ねて表示可能! |
目次[非表示]
- 1.用途地域とは?
- 2.用途地域は大きく3つに分類できる
- 3.13種類の用途地域の特徴をそれぞれ解説
- 3.1.住居系の用途地域
- 3.1.1.1 第一種低層住居専用地域
- 3.1.2.2 第二種低層住居専用地域
- 3.1.3.3 第一種中高層住居専用地域
- 3.1.4.4 第二種中高層住居専用地域
- 3.1.5.5 第一種住居地域
- 3.1.6.6 第二種住居地域
- 3.1.7.7 準住居地域
- 3.1.8.8 田園住居地域
- 3.2.商業系の用途地域
- 3.3.工業系の用途地域
- 4.用途地域の調べ方を4つ紹介
- 4.1.用途地域マップで調べる
- 4.1.1.用途地域マップの見方
- 4.2.各自治体のホームページで調べる
- 4.3.国土数値情報で調べる
- 4.4.不動産会社に調べてもらう
- 5.まとめ:用途地域を理解し正しく土地を活用しよう
- 6.用途地域を地図上に重畳するなら「ZENRIN Maps API」がおすすめ
用途地域とは?

用途地域とは、市街地を形成するために用途ごとに分けられた地域のことです。各地域では、建築できる建物の種類や用途、高さが定められており、これらは全て都市計画法によって規定されています。
「用途地域があることで自由に土地活用ができない」と考える方もいるかもしれませんが、用途地域がないと住宅の隣に大規模な商業施設や工場が建設される可能性があり、日当たりや騒音などのトラブルが発生し、住みにくくなることがあります。
さらに、大型トラックが狭い一般道を通行するのが難しくなったり、渋滞が発生する可能性があるため、商業施設や工場側にもデメリットが生じます。こうした理由から、それぞれの地域で用途が定められるようになりました。
★用途地域データをAPIでスピーディーに取得! |
用途地域は大きく3つに分類できる

用途地域は5年に1回程度の頻度で見直しが行われており、2018年4月1日から新たな用途地域が追加されて現在の13種類になりました。この13種類の用途地域は、大きく3つに分類することが可能です。
- 住居系の用途地域
- 商業系の用途地域
- 工業系の用途地域
それぞれ解説していきます。
住居系の用途地域
住居系の用途地域は、13種類のうち8種類が該当します。名前の通り、主に居住用の建物が中心となる地域です。住居系の用途地域では、住民が快適で安全に暮らせるように配慮されています。
そのため、商業系や工業系の建物を建築できない地域もあれば、中規模の商業系・工業系の建物を建てることが許可される地域もあります。
ただし、中規模の商業系・工業系の建物を建設できる地域でも、条件を満たさない場合は建築できません。各地域の用途に適合しない建物を建てると、建築基準法第48条に違反することになります。
商業系の用途地域
商業系の用途地域は、主に商業地が中心となる地域です。駅周辺や便利な施設が揃っており、多くの人々が集まって買い物や娯楽を楽しむことができます。
商業系の用途地域では、住宅の建設も可能ですが、多くの人が集まり賑やかな地域になりやすいため、周辺の環境音が気になる方には適していないかもしれません。
工業系の用途地域
工業系の用途地域は、主に工業の発展や利便性を高めることを目的とした地域です。
工業と一口に言ってもさまざまな種類があり、危険物を取り扱う業種も存在します。危険物を扱う業種の場合、住民の安全を考慮し、工業系の用途地域にしか建設できません。
ただし、工業の中には危険性が低く、騒音や振動が発生しにくい業種の場合、近隣に住宅地があっても問題ないとされ、建築が許可される地域も存在します。
しかし、頻繁にトラックが運行されるケースもあるため、子どもがいる家庭は注意が必要です。
13種類の用途地域の特徴をそれぞれ解説

13種類の用途地域はそれぞれ異なる特徴を持ち、建築できる建物に制限がある地域もあります。ここでは各用途地域の特徴について詳しく解説していきます。
住居系の用途地域
まずは住居系の用途地域についてです。住居系の用途地域は、番号が進むにつれて制限が厳しくなっており、後半になると建てられる建物の種類が増えていきます。
1 第一種低層住居専用地域
この用途地域は、主に戸建てや低層マンション(2~3階建て)の住環境を保護するためにに設定されています。
この地域では、高さ10mまたは12mまでの低層住宅しか建築できません。また、コンビニなどの商業施設は、たとえ高さが10mまたは12m以下であっても、原則として建築できないことが定められています。
ただし、50平方メートル以下の診療所や理髪店など、生活に欠かせない施設は建築可能です。また、小学校や中学校などの教育施設も建てられます。
この地域は基本的には閑静な住宅街であり、広い庭を持つ戸建てや駐車場を作りやすい点がメリットのひとつです。
2 第二種低層住居専用地域
この用途地域も低層住居の住環境を保護するために設定されています。
建物の高さ制限は第一種と同じですが、第一種で建設できる建物に加えて、床面積150平方メートルまでの店舗も建設可能です。これにより、コンビニや飲食店などが建てられるようになっています。
第二種も低層住居が中心ですが、第一種と比べてコンビニや飲食店が建設できるため、利便性は向上しています。
第二種は、第一種と同じような街の景観を保ちながら、買い物や外食がしやすい地域に住みたい人に適しています。
3 第一種中高層住居専用地域
上記の低層住居専用地域とは異なり、中高層住居専用地域では建物の高さ制限がなくなるため、戸建てや低層マンションに加えて、中高層のマンションも建設可能です。この地域には分譲マンションが多く建ち並んでいます。
また、住居以外の建物としては、小学校や中学校のほか、高校や大学、病院等も建設可能です。店舗も床面積500平方メートル以下で、かつ2階建て以下の建物であれば建築できます。
ただし、オフィスビルの建設は許可されていません。落ち着いた住環境と利便性を求める人に適した用途地域と言えるでしょう。
4 第二種中高層住居専用地域
第二種地域は、第一種と同様の制限がありますが、店舗の建設については床面積1,500平方メートルまで認められています。
これにより、スーパーマーケットも建設可能となり、前述の用途地域と比べて生活の利便性が大幅に向上することが期待されます。
さらに、第二種地域では、2階建て以内かつ床面積1,500平方メートル以下であれば事務所の建設も可能です。オフィスとして利用されることで、その地域に住んでいない人も訪れる場所となるでしょう。
5 第一種住居地域
第一種住居地域は、主に住居が中心となっていますが、比較的大規模な建物の建設も認められており、商業エリアとしても利用可能です。
床面積3,000平方メートルまでの店舗や事務所、ホテルなどの宿泊施設も建てられます。このため、第一住居は他の地域と比べて住宅地というイメージが薄いかもしれません。
また、ボウリング場などの娯楽施設も建設でき、夜間は比較的明るい傾向にあります。ただし、カラオケ店やパチンコ店などは原則として建設が許可されていません。
6 第二種住居地域
第二種住居地域では、第一種で建てられる建物に加えて、ボウリング場やスケート場等の娯楽施設も建設可能です。床面積10,000平方メートル以下であれば、カラオケ店やパチンコ店も建てられるようになります。
第一種に比べて制限が緩和されているため、より商業地としての趣を感じられるでしょう。とくに娯楽施設が増えていることから、利便性が高く、近場で遊びたい人にとって便利なエリアです。
建築できる店舗の種類が増える一方で、映画館や劇場などの施設、そして風俗営業を営む施設は第二種地域でも建設できません。
7 準住居地域
準住居地域は、自動車関連施設と住居環境の調和を図るために、定められた用途地域です。主に国道や幹線道路沿いのエリアが指定されています。
自動車関連施設には、車庫や倉庫、床面積150平方メートル以下の自動車修理工場が含まれます。また、客席が200平方メートル未満であれば、映画館や劇場等の施設を建設することも可能です。
国道や幹線道路に面しているため、車での移動が多い人にとっては便利なエリアと言えます。しかし、交通量が多いため、住居の近くを通る自動車の影響で振動や騒音に注意が必要です。
8 田園住居地域
2018年4月1日から新たに追加された田園住居地域は、低層住居専用地域と同等の厳しい建築制限が設けられた地域です。この地域では、低層住宅を中心に、農地と住宅街が共存しています。
住宅以外にも、幼稚園から高校までの教育施設や図書館、病院、神社・寺院等が建設可能です。また、床面積500平方メートル以内であれば、農家が営む直売所や農家レストラン、農機具用の倉庫、農作物の貯蔵庫も建てることができます。
田園住居地域は、「生産緑地の2022年問題」対策として設けられました。生産緑地の多くは1992年に指定されており、2022年を過ぎるとその指定が解除され、固定資産税などの負担が増えるため土地を売却する人が増えることで土地価格が大暴落するのではないかと懸念がありました。
しかし、指定を延長する法整備が整ったため、大暴落は避けられ、現在は田園住居地域の指定が促進されるような状況にはなっていません。
商業系の用途地域
商業系の用途地域には、主に近隣商業地域と商業地域の2種類があります。商業系はその名の通り、店舗や事務所、商業施設などを建設する際の制限が比較的緩やかなエリアです。
ただし、商業系の建物に特化しているわけではなく、居住用の建物も建てることが可能です。とくに、高層マンションが商業系の用途地域に建設されるケースが多く見られます。
9 近隣商業地域
近隣商業地域は、準住居地域に設けられた制限が緩和されたエリアです。この地域では、店舗や事務所、商業施設に床面積の制限がなく、大規模な施設を建設することができます。
さらに、床面積150平方メートル以内であれば、安全と認められた工場や、300平方メートル以下の作業場を持つ自動車整備工場等も建設可能です。
生活の利便性が向上する一方で、多くの人や車が行き交うため、静かな住環境を望むことは難しいかもしれません。賑やかな環境を好む人や、日中はほとんど家を空けている人にとっては適した住環境と言えるでしょう。
10 商業地域
商業地域は、近隣商業地域と比べて店舗に対する制限がなく、商業施設の建設から高層オフィスビルまで建設できる地域です。主に都市部のターミナル駅周辺が商業地域に分類されます。
商業地域では、商業施設を建設する際の制限がないため、飲食店や映画館、風俗営業の店舗等も建設可能です。
商業地域に居住用の建物を建てると、多くの人が訪れるため、騒音が気になる場合があるでしょう。また、治安が他の地域に比べて悪化する可能性も考えられます。住環境よりも利便性を重視したい場合には、商業地域が適しています。
工業系の用途地域
工業系の用途地域は、主に工場や倉庫等を建てることを目的とする地域になります。ただし、工業専用地域以外では工場や倉庫以外の建物を建てることができます。
11 準工業地域
準工業地域は、軽工場(繊維・食料品・皮革製品など)をはじめ、さまざまな種類の工場が建設できる用途地域です。
工場以外にも、住居や病院、娯楽施設、宿泊施設なども建てられます。住居が建設されることから、基本的には環境や人体に悪影響を及ぼさない工場の建設が認められています。
住居や商業施設、工場などさまざまな建物が建設されるため、住みやすさは建てられる建物によって変わるでしょう。たとえば、準工業地域に商業施設が多ければ、生活の利便性が高くなり、住みやすいと感じるかもしれません。
12 工業地域
工業地域は、準工業地域では建設できない工場も建設できる用途地域です。危険物を取り扱う工場の建築も可能で、主に湾岸エリアや工場跡地等が工業地域に該当します。
準工業地域と同様に、住居や店舗を建てることもできますが、病院や小学校・中学校等の教育施設、映画館、宿泊施設は建設できません。
住居や店舗は建てられるものの、その他の施設が少ないため、住宅地としてはあまり良い環境とは言えません。また、工場の数が増えれば出入りするトラックの数も増えるため、小さなお子さんがいる家族には適さないエリアです。
13 工業専用地域
工業専用地域は、その名の通り工業専用の用途地域であり、工場しか建設できません。住居を建てることはできず、工場であれば石油コンビナートや鉄工場等、さまざまな種類の工場が建設可能です。
なお、工場に付属する形で事務所や診療所、保育所を建設することは可能です。店舗は物品販売店や飲食店は建設できませんが、その他の店舗であれば建てられます。
★APIで簡単、用途地域のデータを取得! |
用途地域の調べ方を4つ紹介

土地ごとに用途地域が決められていますが、用途地域を調べる方法が分からない方もいるかもしれません。用途地域の調べ方は、以下の4つがあります。
- 用途地域マップで調べる
- 各自治体のホームページで調べる
- 国土数値情報で調べる
- 不動産会社に調べてもらう
それぞれの調べ方について、詳しくご紹介していきます。
用途地域マップで調べる
用途地域マップは、国土交通省国土政策局の国土数値情報を基に作成された地図データを公開しているサイトです。
このマップでは全国の用途地域を調べることができ、各地の用途地域が更新されると、用途地域マップも随時更新されます。地図上が色分けされており、その色によって用途地域を把握できます。
ただじ、用途地域マップは民間の企業が運営しているため、最新情報ではない可能性があります。
そのため、用途地域マップはあくまで参考程度に留め、正確なデータを確認したい場合は各自治体のホームページや国土数値情報などを調べることをお勧めします。
用途地域マップの見方
用途地域マップを活用する際は、まず「用途地域マップ」のサイトを開き、「ここから開始」を選択します。すると都道府県名が表示されるので、調べたい土地の都道府県名をクリックしましょう。
次に市区町村名が表示されるので、該当するものをクリックしてください。なお、ここでグレー表示になっている地域名は、用途地域が公開されていないか、存在しないことを示しています。
市区町村名をクリックすると、その地域の用途地域マップが表示されます。マップを拡大すると、色で細かく分けられているため、調べたい地域がどの色になっているか確認可能です。
たとえば、第一種住居地域は黄色、商業地域はピンク、工業地域は水色で表示されています。また、より具体的な住所を指定したい場合は、左上の「住所検索」で大字・町丁字を入力することも可能です。
用途地域マップには便利な機能も揃っています。マップの上部にある「描画ツール」を使うことで、基準点を地図上に置いたり、距離や面積を計算したりできます。中心から1km、2km、3kmの同心円を作成することも可能です。
各自治体のホームページで調べる
用途地域は国土交通省ではなく、各市区町村が主体となって設定しています。そのため、各自治体のホームページから用途地域を調べることが可能です。
たとえば、東京都港区の用途地域を調べたい場合、検索エンジンで「港区 用途地域」と入力して検索すると、「港区都市計画情報提供サービス」が表示されます。
このサイトをクリックすると、港区の地図や主要施設、住所から用途地域を検索できます。また、自治体のホームページにも最新版の用途地域等図のPDFファイルが掲載されており、こちらからも確認可能です。
ただし、自治体によっては用途地域を公開していない場合もあります。ホームページで確認できなかった場合は、自治体の都市計画課に問い合わせることで、用途地域が記載された都市計画図を閲覧できる場合があります。
国土数値情報で調べる
国土交通省は、国土に関する基礎的な情報を無償で提供する「国土数値情報ダウンロードサイト」を運営しています。
国土数値情報とは、国土計画の策定や実施をサポートするために整備されたもので、行政区域や鉄道、道路、地価公示等、国土に関する情報を網羅しています。
国土数値情報ダウンロードサイトで、国土数値情報の「都市計画決定情報」をクリックすると、用途地域や都市計画区域、防火・準防火地域等の地物情報がまとめられた国土数値情報をダウンロード可能です。
年度やデータ形式(CityGML、シェープファイル、GEOJSON)、都道府県を選択すると、選んだ都道府県の市区町村が表示されますので、調べたい土地がある市区町村を選びましょう。
下にダウンロードボタンが表示されるため、それをクリックすれば用途地域も含んだ国土数値情報を入手できます。
不動産会社に調べてもらう
用途地域はインターネットから無料で調べられますが、不動産会社に調べてもらうことも可能です。不動産会社の担当者は用途地域を把握していることが多いため、直接尋ねて確認するのも良いでしょう。
ただし、担当者がどこまで情報を把握しているかは異なる場合があります。たとえば、以前の用途地域情報を確認しただけで、変更後の情報を把握していないこともあります。
また、担当者によっては用途地域を一切把握できていないこともあります。さらに、不動産会社も土地の用途地域を調べる際には、自治体のホームページや国土数値情報から確認しているため、不動産会社を通さなくても自分で用途地域を調べることが可能です。
まとめ:用途地域を理解し正しく土地を活用しよう

今回は、用途地域の種類と特徴、さらに調べ方についてご紹介してきました。
用途地域は大きく住居系・商業系・工業系の3つに分けられ、そこから13種類に分類されます。各地域によって建てられる建物の種類や規模が異なるため、注意が必要です。
また、調べ方にはさまざまな方法があります。用途地域マップや各自治体のホームページ、国土数値情報等はインターネットから手軽に調べられ、すべて無料で確認可能です。
ただし、中には用途地域の情報が公開されていない場合もあるため、必要に応じて各自治体の都市計画課に問い合わせて用途地域を確認することをお勧めします。
用途地域を地図上に重畳するなら「ZENRIN Maps API」がおすすめ

用途地域を地図上で手軽に確認したい場合、「ZENRIN Maps API」の活用がおすすめです。
ZENRIN Maps APIは、ゼンリングループが全国の調査網から収集・整備した情報を一元管理する時空間データベースを活用し、WebサイトやWebアプリ、スマートフォンアプリ等に地図コンテンツや検索機能を実装するための開発ツールです。
ZENRIN Maps APIを利用すれば、各市町村が策定した都市計画図を地図上に重畳できます。用途地域はもちろん、区域区分や建ぺい率、容積率、防火地域、準防火地域等の情報も地図上に重ねて表示可能です。
その他にも、ZENRIN Maps APIにはルート探索機能や位置情報を高度化するデータコーディング、ユーザーデータの編集・運用に利用できるホスティング機能等が備わっています。
Webサイトやアプリに用途地域を表示できる地図コンテンツを開発したい場合は、ぜひZENRIN Maps APIをご活用ください。