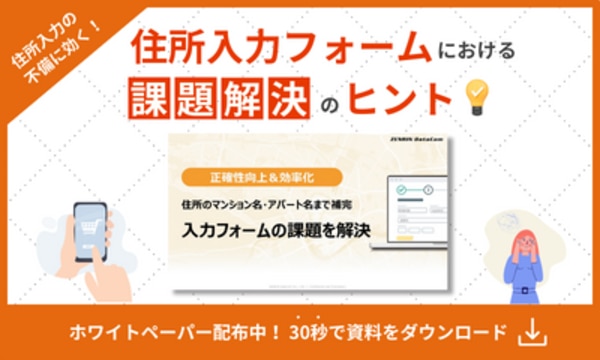地価の調べ方を7つ紹介!地価を左右する要因や調査する際の注意点も解説
不動産を売買したり、相続や贈与を行う際に、地価を調べることはよくあります。
地価は、公正な不動産取引や正確な鑑定を行う上で重要な指標ですが、地価の意味や調べ方がはっきりしないといった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、地価の基本的な概要や種類、調べ方について詳しくご説明します。土地の価格を左右するポイントや調査を行う上での注意事項も解説していますので、不動産の取引や相続、贈与を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
★地価を反映したマップ作成をご検討なら「ZENRIN Maps API」 |
目次[非表示]
- 1.土地の価格(地価)とは?
- 2.土地価格(地価)の種類は主に6種類
- 3.土地価格(地価)を調べる方法を6つ解説
- 3.1.国土交通省が発表する公示地価で確認
- 3.2.過去の取引データから実勢地価を確認
- 3.3.固定資産税納税通知書を用いた評価額の確認
- 3.4.国税庁による相続税路線価で確認
- 3.5.不動産一括査定サイトでの確認
- 3.6.APIを利用し地図上に地価を反映して確認
- 4.土地の価格を左右する要因とは?
- 5.土地価格(地価)を調査する際の注意点
- 5.1.調査データの最新性を確認する
- 5.2.地域特性を考慮する
- 5.3.複数の情報源を比較する
- 6.まとめ:最新データを用いて正しく土地価格を調査しよう
- 7.地価を反映したマップの作成なら「ZENRIN Maps API」
土地の価格(地価)とは?

地価とは、土地の価格を指します。土地は一つとして同じものがないため、定価を設定して売買することはできません。そのため、不動産取引や税金の計算には、基準となる価格を使用する必要があります。
国土交通省は地価公示法に基づき、毎年1回標準地の価格を公示しており、これが土地取引の目安となります。しかし、実際の取引では、売主と買主が価格を決定することが多く、公示価格で取引されるとは限りません。
また、土地の価格を決定する基準は複数あり、不動産取引や相続などの目的によって参考にする指標が異なります。これらの基準を理解することで、目的に応じた土地の相場を把握することができます。
土地価格(地価)の種類は主に6種類

土地の価格となる基準は、以下6種類に分類されます。
- 公示地価
- 基準地価
- 実勢価格
- 路線価
- 固定資産税評価額
- 相続税路線価
それでは、それぞれの土地価格の特徴をご紹介します。
公示地価
公示地価は、毎年1月1日時点の1平米あたりの土地価格で、国土交通省が毎年3月下旬頃に発表します。
全国の都市計画区域に基準地(調査地点)が定められており、各拠点は2人以上の不動産鑑定士によって調査されます。その後、土地鑑定委員会での審議を経て価格が決定されています。
公示価格は土地の公的な価値を示すため、公共事業用地の取得価格の基準となる指標です。また、公正な不動産取引を実現するために、一般の土地取引でも参考にされています。
公示地価は国が指定する不動産鑑定士によって算出されるため、信用性が高いです。そのため、公示地価に基づいた希望金額を提示することで、土地売却の成功率が高まるでしょう。
基準地価
基準地価は、公示地価を補完するために都道府県が発表する土地価格で、都道府県価格調査とも呼ばれています。価格はその年の7月1日時点のものであり、毎年9月下旬頃に発表されます。
基準地価の役割は、公示地価と同様に、適正かつスムーズな土地の価格査定を実現することです。評価方法も公示地価とほぼ同じですが、鑑定に都市計画区域内外の土地も含まれ、調査する不動産鑑定士は1人以上という点が異なります。
公示地価は1月1日時点の土地価格であるのに対して、基準地価はさらに半年程先の土地価格を把握できます。地価が変動した際は、この2つの価格を比較することで動向を把握することができます。
実勢価格
実勢価格は、土地が実際に売却されたときの土地価格であり、つまり時価のことです。売り手と買い手が価格について交渉し、双方が合意した価格が実勢価格になります。公示地価や基準地価のように公的機関が定めるものではなく、当事者同士が自由に価格を設定することが可能です。
取引が成立するまで実際の実勢価格はわかりませんが、似た土地の過去の実勢価格を参考にすることで、売却相場を把握できます。根拠のない高い価格を提示しても、買い手が見つからない可能性があります。
しかし、似た土地の実勢価格を参考にすることで、現実的な価格を設定できるでしょう。そのため、土地を売却する際には、公示地価や基準地価だけではなく、実勢価格を調査することが重要です。
路線価
路線価は、道路(路線)に面した宅地1平方メートルあたりの価額から算出される土地価格です。土地の相続税や贈与税等の税金を計算する際に用いる基準となります。調査対象は主要道路に面した土地となるため、対象外の土地は発表されません。
路線価は、市町村(東京23区は都)が発表する固定資産税に関するものと国税庁が発表する相続税に関するもの(相続税路線価)の2種類に分けられます。
固定資産税に関する路線価は3年に1度更新され、後述する固定資産評価額の計算に用いられます。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、前年1月1日時点の土地価格を基にしています。市町村が3年ごとに更新しており、4月頃に発表されています。この評価額は、固定資産税、都市計画税、不動産所得税、登録免許税などの税額を計算するために使用されます。
評価額は、固定資産税路線価を基に算出されています。毎年4から6月頃に送付される課税明細書に評価額が記載されています。そのため、個別に固定資産税路線価を用いて計算する必要はありません。
一般的に固定資産税評価額は、公示地価の70%が目安とされていますが、土地の地域(市街地か村落地か)、面積・形状等などの要素によって評価額は異なります。
相続税路線価
相続税路線価は、相続税や贈与税の計算に使用される土地価格です。一般的に「路線価」というと、この相続税路線価を指します。
国税庁が毎年7月に発表し、その年の1月1日時点での主要道路に面する宅地の1平方メートルあたりの価格を示しています。この価格は、不動産鑑定士の評価や有識者の意見を参考にして決定され、公示地価の約80%が目安となります。
相続税路線価は1平方メートルあたりの価格で示されるため、土地の面積を掛け合わせることで、土地全体の評価額を算出することが可能です。
この計算方法を「路線価方式」と呼びます。なお、路線価が設定されていない土地は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算する「倍率方式」が用いられます。
|
★地価を反映したマップの作成なら!
|
土地価格(地価)を調べる方法を6つ解説

地価を調べる方法は種類毎に異なり、以下の方法が挙げられます。
- 国土交通省が発表する公示地価で確認
- 過去の取引データから実勢地価を確認
- 固定資産税納税通知書を用いた評価額の確認
- 国税庁による相続税路線価で確認
- 不動産一括査定サイトでの確認
- APIを利用し地図上に地価を反映して確認
ここで、6つの地価の調べ方について詳しくご紹介します。
国土交通省が発表する公示地価で確認
公示地価は国土交通省によって発表されており、「不動産情報ライブラリ」からその年の公示地価を調べることが可能です。手順は以下の通りです。
- 「地図検索」をクリックし、調査したい土地の住所を入力
- 「価格情報」をクリックし、メニューから「国土交通省地価公示」を選択して「決定」をクリック
- ○マークをクリックして、その土地の公示地価を確認する
詳細表示をクリックすると、より詳しい土地情報や公示地価の推移を確認できます。○の色がオレンジであれば住宅地、黄土色であれば商業地を示しています。公示地価が表示されない土地もあるため、その場合は近隣の土地を参考にしましょう。
参考:不動産情報ライブラリ
過去の取引データから実勢地価を確認
実勢地価は売買取引が成立した時点で決まるため、取引前には正確な価格はわかりませんが、過去の取引データから目安を把握することができます。
過去の取引データを取得するには、国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」の利用がおすすめです。「不動産価格(取引価格・制約価格)情報の検索・ダウンロード」から、地域や時期等を絞り込んで取引データを取得できます。
地域は住所だけでなく、路線・駅名からも検索可能です。価格情報区分は、アンケート調査に基づく不動産取引価格情報と、不動産情報ネットワークシステムの価格情報に基づく成約価格情報の両方で確認できます。
実勢地価は信頼性の高い価格ですが、調べたい土地に関する取引データが公表されているとは限りません。そのため、対象地域全体の相場を把握する指標を利用するとよいでしょう。
固定資産税納税通知書を用いた評価額の確認
固定資産税評価額を調べるには、まず毎年送られてくる固定資産税納税通知書を確認しましょう。この通知書の課税明細書には評価額が記載されています。
また、不動産がある地域の役所や都道府県税事務所で固定資産税台帳を閲覧することでも評価額を確認できます。さらに、「縦覧帳簿」を利用すれば、他の人が所有する不動産の価格も確認することが可能です。
固定資産税納税通知書以外では、不動産がある地域の役所や都税事務所で固定資産課税台帳を閲覧することで確認できます。「縦覧帳簿」であれば、他の人が所有する不動産の価格を確認することも可能です。
他にも、役所・都道府県税事務所の窓口、または郵送で取得できる固定資産評価証明書を利用する方法もあります。
証明書の申請には、マイナンバーカードや運転免許書等などの本人確認書類等が必要ですので、詳細は役所のホームページを確認してください。
国税庁による相続税路線価で確認
相続税路線価は、国税庁が運営する「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から調べられます。相続税路線価の調べ方は以下のとおりです。
- 調べたい都道府県をクリックして、「路線価図」を選ぶ
- 市町村名を選び、地域を絞り込んで検索する
- 該当する路線価図を選んでクリックして、詳細を表示する
路線価図ページ毎に表示されるため、調べたい土地が見つけにくいときは、画面上部にある「この市区町村の索引図ページへ」をクリックしてください。地図が表示されるので、当該の土地を探しやすくなります。
不動産一括査定サイトでの確認
素早く土地価格を調べたい場合、不動産一括査定サイトの活用もおすすめです。
不動産情報を入力するだけで、不動産情報を入力するだけで、複数の不動産仲介会社に一度に査定依頼ができるため、個別に依頼する手間が省けて便利です。
複数の不動産仲介会社から査定を受けることで、価格を比較検討することができます。また、所有する土地の売却相場を把握しやすくなり、適切な価格設定が可能となるため、売却活動をスムーズに進めることができるでしょう。
APIを利用し地図上に地価を反映して確認
法人の場合、APIを活用して地図上に地価を表示させることができます。APIは、アプリケーション同士を連携させるためのシステムです。
地価表示機能を持つAPIを導入することで、自社ソフトウェアやWebサイト上で、調べたい土地の地価を確認することが可能です。
APIを利用する際は、制度の高い地図データを活用したサービスを利用することがポイントです。定期的に情報更新が更新され、最新の地図や地価情報を取得できることもポイントです。
「ZENRIN Maps API」で最新の地価情報を取得し、業務効率化! |
土地の価格を左右する要因とは?

同じエリア内でも土地の価格はそれぞれ異なります。これは、様々な要因が価格に影響を与えるためです。主な要因としては、以下のものが挙げられます。
- 立地条件
- 土地の広さや形状
- 環境要因
- 法的制限
- 市場の需給バランス
これらの要因がどのように価格に影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。
立地条件
土地価格は、立地条件によって大きく変わります。利便性の高い場所ほど需要が高まり、価格も上昇します。ここでいう利便性とは、周辺環境や地域の発展度など、生活のしやすさを指します。
例えば、駅に近い土地は通勤や通学に便利で、買い物や病院、学校などの施設が近くにあると利便性が高くなります。そのため、こうした土地は地価が高くなる傾向があります。特に駅に近い土地は交通の便が良いため、価格が高くなりやすいです。
さらに、自然災害に対する強さも価格に影響します。地盤が強い地域や防災対策がしっかりしているエリアは人気があり、土地の価格が高くなる可能性があります。
土地の広さや形状
土地の広さや形状も価格に影響を与える重要な要素です。広い土地は多用途に利用できるので、価格が高くなる傾向にあります。
例えば、マンションやオフィスビル等高層の建物を建設できるエリアの場合、広い土地は希少性が高く、地価の上昇しやすいです。
ただし、広い土地だからといって、必ずしも価格が高くなるわけではありません。立地条件やその地域で使いやすい広さであるか等、総合的に見て判断されます。
また、土地の形状も使いやすさに影響します。正方形や長方形といった整形地は建物が建てやすいため、価値が高くなりやすいです。一方、旗竿地や三角地などの複雑な形状の土地は、整形地に比べて価値が下がる傾向にあります。
環境要因
土地の価格は周辺環境によっても大きく影響されます。例えば、南側に道路がある土地は日当たりが良いため、価格が高くなる傾向にあります。
また、角地は一面の道路に接している土地と比べて日当たりと風通しが良く、人気が高いため、価格が上がりやすいです。
ただし、現状は日照条件が良くても、将来的に高層ビルやマンションが建設されて日照が悪くなる可能性がある土地はマイナス要素となることがあります。
前面道路の幅や敷地との高低差も価格に影響します。幅が広い道路に面している土地は使いやすく、価格が高くなりやすいです。
一方、土地と道路に大きな高低差がある場合、階段が必要になったり、下水の排水に問題が生じるため、価格が下がることがあります。
さらに、有害物質で汚染された土地や埋蔵文化財が発見された土地、産業廃棄物処理所やパチンコ店などの嫌悪施設が近くにある土地も、価格が低くなる傾向があります。
法的制限
土地の価格には、建て方や使い方に関する法的制限も大きく影響します。建築基準法や都市計画法、政令・条例などにより、土地に建てられる建物の種類や高さ、大きさなどが規制されています。
例えば、第一種低層住宅専用地域では、建築可能な建物は住宅や小中学校などに限定されており、高さも10mまたは12mに制限されています。
一方、第二種中高層住宅専用地域では日影規制はあるものの、高さ制限がないため、マンションや1,500平米までの店舗などの建築が認められています。
このように、法的制限によって土地の利用が制約されることがあり、需要の大小も異なるため、土地の価格は変動します。中には建物を建てられない区域もあり、そのような区域では地価が安くなる傾向があります。
市場の需給バランス
不動産市場における需給バランスも土地価格に大きな影響を与えます。需要が高い土地は、土地価格が上昇します。一方で、供給が高い土地は価格が下がる傾向にあります。
土地の需給バランスは景気の影響を受けやすいです。景気がよくなると労働者の賃金があがり、土地購入や住み替えのための売却が活発になります。これにより、需要と供給のバランスが整いやすくなります。
逆に景気が悪いときは、高価な土地や建物を購入する人が減り、不動産を売りたい人が増えるため、供給過多な状態になりやすいです。
他にも、住宅ローンの金利も土地の需給バランスに影響を与える重要な要素です。低金利の状態であれば、住宅ローンを使って土地を購入しやすくなるため、不動産取引が活発になります。
反対に金利が高くなると土地を購入する人が減少し、不動産取引が減少します。そのため、土地の供給が需要を上回り、価格が下がりやすくなります。
土地価格(地価)を調査する際の注意点

地価を調べることは、不動産の売却や購入を優位に進める上で大切です。実際に地価を調べる際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 調査データの最新性を確認する
- 地域特性を考慮する
- 複数の情報源を比較する
これらのポイントを押さえて、地価を調査する際の注意点について詳しく見ていきましょう。
調査データの最新性を確認する
地価を調べる際には、データが最新であるかどうかを確認しましょう。地価は時期によって変動するので、過去のデータと現状の価格は大きく異なることがあります。
例えば、土地の売買において参考になる公示地価は、1月1日時点の価格が公表されています。需給バランスの変化などで現状の地価が変わっている場合、公示地価の情報が必ずしも正確ではないことがあります。
9月には、7月1日時点の基準地価が確認できるため、半年でどのくらい地価が変動したのかをチェックするとよいでしょう。また、不動産鑑定士などの専門家に鑑定を依頼して、現状の価格相場を把握する方法もあります。
地域特性を考慮する
地価を調べるときは、地域の特性も考慮しておきましょう。地域ごとに市場の動向や環境が異なるため、それによって地価に大きく影響します。公的に発表される地価情報だけではなく、土地の価格に影響を与える要素がないかも確認してみましょう。
例えば、利便性が高い立地や使いやすい土地などのプラスの要因があれば、需要が高いため公示地価よりも高く取引される可能性があります。
反対にマイナス要因がある土地は買い手が見つかりにくく、その点を考慮して土地価格を設定する必要があります。また、買い手はマイナス要因を理由に価格交渉を行うことも考えられます。
複数の情報源を比較する
複数の情報源を比較することも大切です。公示地価や基準地価、実勢価格等さまざまなデータを取得することで、より現実的な地価を把握できます。
特に土地を売却する場合、価格を高く設定しすぎると買い手が見つからないことがあります。売れない場合は値下げが必要になり、結果的に売り手が損をしてしまう可能性があります。
複数のデータを比較し、売却につながりやすい価格を設定できれば、大きな損失を避けながら土地取引を進めることができます。
まとめ:最新データを用いて正しく土地価格を調査しよう
土地の価格には、公示地価や基準地価などさまざまな種類があり、どの地価が参考になるのかは目的によって異なります。そのため、地価の種類や役割を理解して、土地の取引や税金の計算に活用しましょう。
地価は時期やあらゆる要因で変動するため、最新のデータを使って調べることが大切です。国の情報サイトや不動産一括査定等を使えば最新の土地価格を調べられるので、ぜひ活用してみてください。
★最新のデータを反映した地図APIなら! |
地価を反映したマップの作成なら「ZENRIN Maps API」
ZENRIN Maps APIは、詳細な住宅情報・建物情報・道路情報を保有する高精度なゼンリン地図データを実装できるAPIです。ルート検索や検索機能等、多様な機能を利用して業務を効率化させることが可能です。
地図上に公示地価を重畳させることも可能です。ZENRIN Maps APIは、一般財団法人 土地情報センターの地価公示マスタを使用しているため、信頼性の高い土地価格情報をマップに反映できます。
APIを導入することで、不動産業における物件調査の効率化や、また提案力の向上が期待できます。
自社システムに地価を反映したマップを実装したいときは、APIの導入実績が豊富なゼンリンデータコムへお気軽にご相談ください。