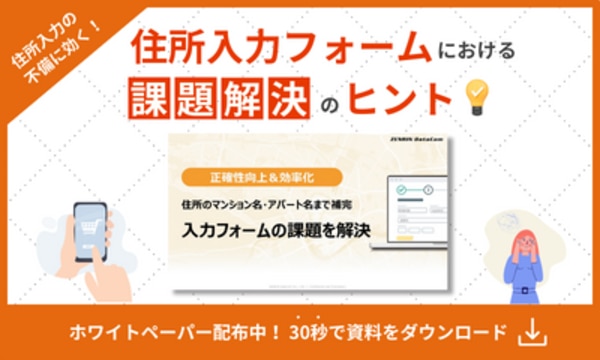MaaSとは? 導入メリットや国内外の事例を分かりやすく解説
MaaS(Mobility as a Service)は、移動の利便性を高めるための新しいサービスとして注目されています。
内閣官房が2018年に発表した「未来投資戦略2018」では、MaaSは公共交通全体のスマート化を実現する重要な手段のひとつとして、自動運転技術と共に紹介されました。
MaaSは都市部だけでなく、地方の交通問題の解決にも寄与するため、対策が進められている分野です。
そこで本記事では、MaaSの定義、導入のメリット、企業事例等についてご紹介します。
MaaSについて詳しく知りたい方や、日本および海外での事例に興味がある方は、ぜひ最後までお読みください。
★MaaSサービスの構築をご検討中ですか? |
目次[非表示]
- 1.MaaSとは?
- 2.MaaSが注目されている背景
- 3.MaaSの普及レベルについて
- 3.1.【レベル0】統合なし
- 3.2.【レベル1】情報の統合
- 3.3.【レベル2】予約、決済の統合
- 3.4.【レベル3】サービス提供の統合
- 3.5.【レベル4】政策の統合
- 4.MaaSを導入するメリット
- 4.1.公共交通サービスの利用を促進する
- 4.2.混雑を回避できる
- 4.3.地方への移動や旅行客をサポートできる
- 4.4.物流の効率化につながる
- 4.5.観光業界の活性化につながる
- 4.6.スマートシティが実現する
- 4.7.排ガス排出量が減少する
- 4.8.SDGs達成につながる
- 5.MaaSの実現における現状の課題
- 5.1.MaaS実現のための法整備
- 5.2.データの共有やオープン化
- 5.3.エコシステムの導入
- 5.4.都市部と地方の地域格差
- 5.5.付加価値の考案
- 6.MaaSの導入事例
- 6.1.株式会社ゼンリン「STLOCAL(ストローカル)」
- 6.2.コンピューターサイエンス研究所「視覚障がい者歩行支援アプリ Eye Navi」
- 6.3.トヨタ「my route」
- 6.4.JR東日本「Ringo Pass」
- 6.5.MaaS Global社「Whim(ウィム)」(フィンランド)
- 7.まとめ MaaSを導入してよりシームレスな交通サービスを実現しよう
- 8.MaaSサービスの構築に! ゼンリングループの「ZENRIN Maps API」をご活用ください
MaaSとは?

MaaS(マース)とは「Mobility as a Service」の略で、複数の交通手段を需要に応じて統合し、一つのサービスとして提供する次世代の交通システムを指します。
AIや5Gといった最新技術を活用し、移動をより効率的かつ便利にすることを目的としています。
2012年にサンフランシスコで初めて議論され、2015年のITS世界会議で注目を集めました。その後、2016年にフィンランドで本格的にビジネス化されたことで世界に広まり、日本でも2019年から国の支援を受けながら導入が進められています。
MaaSが注目されている背景
MaaSという概念が急速に注目を集めている背景には、私たちが直面している様々な社会課題と、それを解決しうるテクノロジーの進化があります。
高齢化社会と交通弱者の増加
日本では高齢化が急速に進んでおり、運転免許を返納した高齢者など、自ら車を運転できない「交通弱者」が増加しています。
特に公共交通機関が衰退しつつある地方では、日々の買い物や通院といった移動手段の確保が深刻な課題です。
MaaSは、デマンドバスや乗合タクシーなどを活用し、こうした交通弱者の移動を支える重要な手段として期待されています。
都市部における交通渋滞と環境問題

都市部では、自家用車の利用集中による交通渋滞が慢性的な問題となっています。
交通渋滞は経済的な損失を生むだけでなく、排出ガスによる大気汚染やCO2排出による地球温暖化といった環境問題にもつながります。
MaaSによって公共交通機関の利便性が向上し、自家用車から公共交通への利用転換が進めば、これらの問題の緩和が期待できます。
テクノロジーの進化とスマートフォンの普及
MaaSの実現に不可欠なのが、IT技術の進化です。誰もがスマートフォンを持つようになり、リアルタイムの位置情報や交通データを簡単に入手・活用できるようになりました。
これにより、複雑な経路検索やリアルタイムでの予約・決済といった、MaaSの中核となる機能が技術的に可能になりました。
MaaSの普及レベルについて

MaaSは普及度に応じて、5つのレベルに分類されます。
どの程度交通サービスが統合されているかによって、MaaSの普及レベルは変わるので、それぞれのレベルを確認してみましょう。
MaaSの普及レベルは、次のとおりです。
レベル0 | MaaSが普及していない状態 |
レベル1 | 情報が統合されている状態 |
レベル2 | 予約や決済サービスが統合されている状態 |
レベル3 | 交通サービスが統合されている状態 |
レベル4 | 政策が統合している状態 |
それぞれのレベルについて解説します。
【レベル0】統合なし
レベル0の交通システムは、従来の交通システムのように、各移動サービスが独立して運行されている状態を指します。
例えば、タクシー、バス、電車、Uber等の移動手段が存在しますが、これらのサービスは連携していません。
複数の交通機関を利用する際には、各サービスを個別に予約したり、時間を調べたりする必要があります。
【レベル1】情報の統合
レベル1では、複数の交通機関をまとめて予約・決済することはできませんが、電車やバス等、異なる交通手段を使った目的地までのルート検索が可能です。
例えば、目的地まで電車だけでは行けず、途中でバスに乗り換える必要がある場合でも、ひとつのWebサイトやアプリで検索すると、どの電車やバスに乗るべきか、それぞれの乗車料金、乗り換えの最適なタイミング、目的地までの所要時間等が簡単にわかります。
【レベル2】予約、決済の統合
レベル2は、レベル1の機能である複数の交通機関に関する情報を検索するだけでなく、同じプラットフォーム上で発券や席の予約、決済等もまとめて行える状態を指します。
これにより、発券や予約の手間が大幅に軽減され、ひとつのWebサイトやアプリですべての交通機関の支払いを完了することが可能です。
日本国内ではまだ実証実験の段階ですが、海外ではすでに実用化されている例があります。例えば、ドイツの「DB Navigator」や中国の「滴滴出行(Didi)」は、予約から決済までをワンストップで行えるサービスを提供しています。
【レベル3】サービス提供の統合
レベル3は、各交通機関の事業者間での連携が進み、どの交通機関を利用しても目的地までの料金が統一されている状態です。
このレベルでは、複数の事業者が存在しているにもかかわらず、利用者にはひとつの事業者が運営しているかのように感じられるほどサービスが統合されています。
レベル2までは公共交通機関が中心となって連携していましたが、レベル3になるとレンタカーやカーシェア等も含めてサービスが統合されるようになります。
ひとつのプラットフォームからすべての交通手段を確保できるため、サービス毎に支払うのではなく、サブスクリプション型の料金体系が採用されることも考えられるでしょう。
海外では、MaaS Global社の「Whim(ウィム)」がこのようなサービスとして知られています。
【レベル4】政策の統合
レベル4は、国や自治体が都市計画の中でレベル3を成功させている状態を示します。この段階では、国と自治体、そして事業者が協力して交通サービスを提供することが求められます。
具体的には、移動の利便性を向上させるために、ターミナルの再配置や増設を検討したり、まちづくりと連携して交通機関の近くに商業地や住宅地を形成したりする等の施策が取られるでしょう。
レベル4に達すると、交通に関連するさまざまな社会問題の解決が期待できます。
MaaSを導入するメリット

MaaSを導入することで、次のようなメリットが得られます。
「なぜMaaSが注目されているのか」と、疑問を抱いている方は、MaaSを導入するメリットを確認しておきましょう。
公共交通サービスの利用を促進する
MaaSを導入することで、交通サービスの利用を促進できます。
今まではGoogle Mapsでルートを検索したり、乗換案内を確認したり、各交通機関の専用サイトで予約・支払いをしたりと、各交通手段に応じた交通サービスを利用していました。
それに対してMaaSを導入すれば、ひとつのアプリ等で利用可能な交通手段をすべて確認できます。その結果、交通サービスの利用方法がわからない高齢者や、旅行先や出張先等、土地勘がないエリアでの移動時でも、交通サービスを利用しやすくなるのです。
MaaSを導入することで、さまざまな交通サービスをシームレスに利用できるようになるため、利便性が高くなるでしょう。
混雑を回避できる

MaaSを導入すれば、複数の交通手段を有効活用できるため、混雑を回避できます。
MaaSの導入により、カーシェアリングが普及し、タクシーやレンタカーを定額制で利用可能となるのです。
そのため、自家用車以外の公共交通手段を利用する人が増えて、車を所有する人が減少します。
自家用車が減少することで、都市部の混雑が回避されるようになるでしょう。
MaaSを導入することで、混雑を回避して最適な交通手段を選択できるようになります。
地方への移動や旅行客をサポートできる
MaaSを導入すれば、地方への旅行客をサポートできます。
地方都市へ旅行した際には、土地勘がなく交通手段で悩むこともあるでしょう。
MaaSの普及により、バスや電車等、従来の公共交通機関だけでなく、乗車数1〜2名程度の超小型モビリティや自動運送車が交通手段として加わります。
MaaS導入により、旅行客が地方都市を移動する際に、最適な交通手段を選択することが可能です。
MaaSを普及させることで、交通サービスが普及していない地方都市の活性化が見込めます。
物流の効率化につながる
MaaSは、人の移動に関するサービスを一括して提供する概念ですが、広い意味では物流に関する移動も含まれます。
物流MaaSは、物流に関するすべてのデータを連携させることで、物流全体を最適化するものです。これは、1社だけでなく、物流業界全体や荷主、自治体等が協力して実現されます。
物流MaaSが実現すると、企業内での業務効率化はもちろん、企業間でシステムを共有することにより、他社とのやり取りも効率化できます。
さらに、物流の効率化により、必要なドライバーやトラックの数が減少し、コストを大幅に削減することが可能です。迅速かつ正確な配送が可能になるため、サービスの品質向上にもつながります。
観光業界の活性化につながる
MaaSが普及すると、これまで遠くて行きづらかった場所にも簡単に行けるようになります。その結果、観光需要がさらに活発化することが期待されるでしょう。
例えば、地方の交通網が未発達で観光客が少なかった地域でも、MaaSの導入により訪れる人が増え、地域全体の活性化につながります。
さらに、観光に特化した「観光型MaaS」では、移動手段の統合だけでなく、ユーザーの訪問履歴や検索履歴をAIが分析して、おすすめの観光スポットや最適なルートを提案するサービスも期待されています。
観光型MaaSが発展すれば、混雑の緩和や乗り換え時間の短縮が進み、移動に伴うストレスも軽減されるでしょう。
スマートシティが実現する
スマートシティは、ICTやAI、IoT等の先端技術を利用して、エネルギー事業や交通網、行政サービス等のインフラを効率的に整備・管理する都市のことです。
MaaSでは、車両の位置情報や乗客数等、公共交通機関に関する膨大なデータを収集できます。これらのデータをAIが分析することで、スマートシティの実現が可能になるのです。
例えば、リアルタイムでデータを収集・分析することで、道路の混雑状況を把握し、目的地に到着するまでの最適なルートを提案できます。
さらに、スマートシティが実現すれば、観光スポットや商業地と連携してクーポンを配布したり、イベント情報をリアルタイムで配信したりすることも可能です。
排ガス排出量が減少する
MaaSが広がることで、公共交通機関やカーシェアリングの利用者が増え、自家用車の使用が減ることが期待されています。これにより、排ガスの排出量が減少し、環境への負担が軽減されるでしょう。
特に、地方では車が主要な移動手段となっている地域が多いです。一般社団法人 日本自動車工業会が実施した「2023年度乗用車市場動向調査」によると、乗用車の世帯保有率は77.6%で、地方の小都市やそれ以下の地域で特に高いことが明らかになっています。
排ガスは地球温暖化の原因となるだけでなく、酸性雨や光化学スモッグ等の大気汚染も引き起こす可能性があります。
MaaSを活用して排ガスの排出量を削減できれば、これらの環境問題の解決にも貢献することができるでしょう。
SDGs達成につながる

SDGs(持続可能な開発目標)は、2015年の国連サミットで採択された2030年までに持続可能でよりよい社会を目指すための国際目標です。
この目標は、17の大きな目標と169の具体的なターゲット、そして231の指標から成り立っています。主な目標には、貧困の解消、平等な教育、ジェンダー平等、環境保護等が含まれます。
MaaSは、電車やバス、タクシー等の交通機関を統合し、最適に利用できるサービスです。この仕組みにより、交通資源の効率的な利用が可能となり、経済、社会、環境のすべてにおいて持続可能性を高めることができます。
さらに、MaaSが普及することで、交通手段の選択肢が増え、人々の移動がより便利になり、時間と労力の節約が実現します。
これにより、貧困や不平等の解消といったSDGsの目標達成にも大きく貢献することが期待されているのです。
MaaSの実現における現状の課題

MaaSを実現するためには、現状の課題と向き合い克服しなくてはなりません。
現状挙げられる課題は、主に以下の5つです。
MaaS実現のための法整備
日本国内でMaaSを実現するためには、法整備が必要です。
例えば、アメリカではUberのサービスとして、一般のドライバーが自家用車を使用してお客さんを運び、料金を受け取ることができます。
しかし、日本では自家用車を使ってお客さんを運び、料金を受け取る行為は道路運送法第78条で禁止されている行為です。
それでも、日本でも規制は少しずつ緩和されています。例えば、道路運送法の改正により、過疎地域では国土交通大臣からの登録を受けた場合に限り、自家用車を使ってお客さんを運び、料金を受け取ることができるようになりました。
また、以前は国内で禁止されていたタクシーの相乗りも解禁されています。
このように、政府はMaaSの実現に向けて少しずつ法整備を進めています。
データの共有やオープン化
MaaSでは、リアルタイムの交通情報、予約、決済等をひとつのプラットフォームで提供するため、交通データの共有やオープン化が不可欠です。
企業同士がデータを共有・連携することが重要ですが、国内の企業はこうしたデータの公開にあまり積極的ではありません。
そこで、国土交通省は事業者間でのデータ連携を促進するため、以下の取り組みを実施すると発表しました。
- 連携するデータ範囲の線引きと連携時のルール整備
- データ形式の標準、統一化
- API仕様の標準化や設定の必要性
- 情報を網羅したデータプラットフォームの実現
- 災害時におけるデータの公益的利用
エコシステムの導入
MaaSを導入するには、公共交通機関や自治体だけでなく、通信会社やモビリティ提供会社等、さまざまな企業の協力が必要です。
しかし、そのためには、業界を横断するエコシステムを構築する必要があります。このエコシステムの導入には、競合関係にある企業が協力し合うことになるため、調整が難航する可能性があります。
さらに、デジタル対応に対して消極的な自治体も存在し、これが導入の障害となることが課題として懸念されているのです。
エコシステムの導入を円滑に進めるためには、各事業者や自治体との関係を調整することも重要となります。
都市部と地方の地域格差
地方では都市部への人口流出により、過疎化が進む地域が増えています。
総務省の「平成29年版情報通信白書」によると、三大都市圏と地方圏の転出入超過数の累計で、地方圏からの人口流出が年々増加していることがわかります。
人口流出に伴い、交通機関の衰退が顕著な過疎地域において、MaaSの導入は急務です。しかし、同じ過疎地域でもそれぞれが抱える問題や状況は異なるため、システムを他の地域にそのまま導入しても十分な効果を発揮しない可能性があります。
MaaSを導入する際には、都市部と地方の地域格差を少なくするために、各地域の課題やニーズの調査を行い、地域に合わせたUXデザインに変更することが必要です。
付加価値の考案
MaaSを国内で成功させるには、単にさまざまな移動サービスをひとつのプラットフォームに統合するだけでは十分な収益を得るのが難しいかもしれません。
なぜなら、地方の公共交通事業者は人口減やコロナ等の影響を受け、廃線を余儀なくされたり赤字経営になるなど、非常に厳しい状況だからです。
そのため、MaaSを導入する際には、移動サービスだけでなく、他の産業と連携して新たな付加価値を提供することが重要となります。例えば、観光業や医療分野と協力することで、利用者が増え、収益を上げやすくなるでしょう。
MaaSの導入事例

MaaSを推進している企業は数多く存在しています。
具体的にどのような実証実験や導入事例があるのか、いくつかの事例を確認してみましょう。
それぞれの事例から、MaaSについて理解を深めてみてください。
株式会社ゼンリン「STLOCAL(ストローカル)」
STLOCALは、街を周遊することでその町が持つ歴史や文化を発見し想い出につなげていくサービスで、現在は長崎市や佐世保/西九州、五島、長崎空港/大村エリアの観光スポットを検索し、公共交通機関の電子チケットを購入したり、お得なクーポンを発行したりできる観光型MaaSサービスです。
このサービスは株式会社ゼンリンが提供しており、地図APIサービスである「ZENRIN Maps API」のMaaS基盤をもとに構築されています。
STLOCALを利用すれば、長崎の人気観光地から地元の人しか知らないような穴場スポットまで、
豊富な観光情報を得ることができます。
また、周遊コースも用意されているので、どこに行くか迷ってしまう方にもぴったりです。
さらに、STLOCALを使えば電車やバス、ロープウェイ、船等の交通チケットをまとめて購入できるため、移動もしやすくなります。
旅をする前に観光スポットの入園券や体験チケット等も一括して購入できるので、旅の計画がスムーズに進むでしょう。
参考:STLOCAL(https://stlocal.net/)
コンピューターサイエンス研究所「視覚障がい者歩行支援アプリ Eye Navi」
2023年4月にリリースされた「Eye Navi」は、視覚障がい者が安全かつ効率的に移動できるよう、
画像処理や音声ガイドなどの技術を活用し歩行を支援するスマートフォン用アプリです。
音声で目的地までの方向や経路案内がなされ、またAIを活用した歩行者や車止め等の「障害物・目標物」の検出、自動車のドライブレコーダーのように歩行時の映像を自動で保存する「歩行レコーダー機能」を備えていることで、シームレスな移動を実現します。
「経路案内」の機能にゼンリングループの地図APIをご利用いただいています。
参考:視覚障がい者歩行支援アプリ Eye Navi(https://eyenavi.jp/)
トヨタ「my route」
「my route(マイルート)」は、トヨタ自動車が開発し、福岡市や横浜市などで展開しているMaaSアプリです。 アプリ内で鉄道やバス、タクシー、シェアサイクルなどを組み合わせた多様なルートを検索・予約・決済できます。
また、地域の店舗で使えるクーポンを配信するなど、移動と地域サービスを連携させ、街の活性化を目指す取り組みも行われています。
参考:トヨタ自動車、マルチモーダルモビリティサービス「my route」のサービス提供エリアを全国へ順次拡大 | コーポレート | グローバルニュースルーム | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト
JR東日本「Ringo Pass」
「Ringo Pass」は、JR東日本が提供する、MaaSの実現に向けたマルチモーダルサービスアプリです。このアプリ一つで、提携しているタクシーの配車・決済や、シェアサイクルの利用・決済が可能になります。
Suicaで培った決済システムのノウハウを生かし、将来的には鉄道やバスなど、より多くの交通モードとの連携を目指しています。
都市部における「ラストワンマイル」の移動をスムーズにすることから始め、段階的にサービスを拡大していくアプローチを取っています。
MaaS Global社「Whim(ウィム)」(フィンランド)
世界初のMaaSアプリとしてMaaS Global社が開発した「Whim」は有名です。
Whimは公共交通機関を含めたカーシェアリング・レンタカー等から、最適な交通サービスを提供しています。
ルートや目的地に合わせて交通サービスを案内するだけでなく、アプリ内で予約・決済が可能です。
Whimはサブスクリプションサービスであり、毎月定額費用を支払うことによって利用できます。
世界的にも初めてのMaaS導入事例として、注目を集めているMaaSアプリです。
WhimはMaaSレベル3に該当します。
まとめ MaaSを導入してよりシームレスな交通サービスを実現しよう
MaaSを導入すれば、シームレスな交通サービスが実現できます。
MaaS普及レベルが向上すれば、公共交通サービスの利便性を高めて自家用車の所有率を軽減することが可能です。
自家用車を所有する人が減少することで、都市部の混雑回避・地方での交通サービス最適化が期待できます。
0〜5までの5段階あるMaaS普及レベルにおいて、日本はまだレベル1の段階です。
スマートモビリティチャレンジによって、多くの企業が自動運転・交通サービスのシームレス化を目指して最先端技術を導入しています。
今後の日本社会の発展に向けて、MaaSの導入をご検討ください。
MaaSサービスの構築に! ゼンリングループの「ZENRIN Maps API」をご活用ください
MaaSサービスの構築を検討する際には、ゼンリングループの「ZENRIN Maps API」の活用もご検討ください。
「ZENRIN Maps API」では、ゼンリンの調査員を年間30万人導入して作成した、精度の高い地図情報をAPIで提供可能です。
あらゆるインターフェースに活用でき、さまざまな言語、検索機能等に対応しているため、汎用性が高いサービスです。
「ZENRIN Maps API」から、正確な地図データを取得し、交通サービスの統合化にご活用ください。