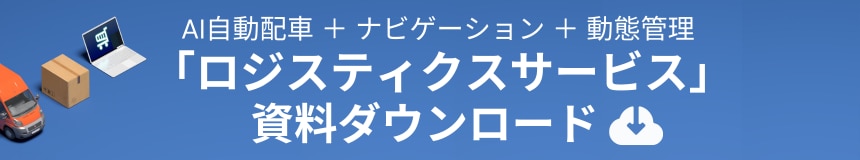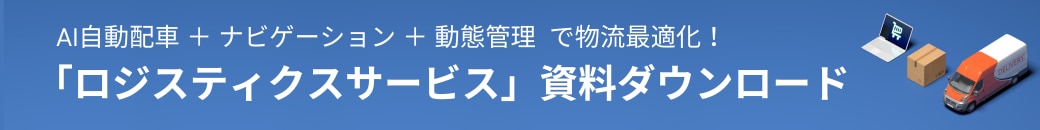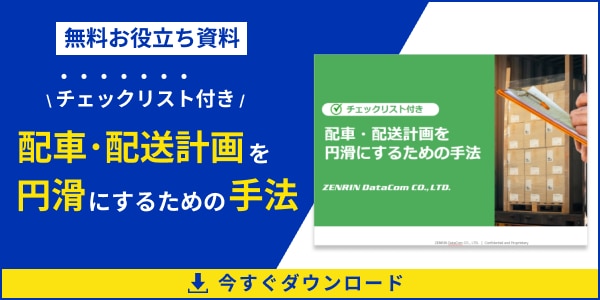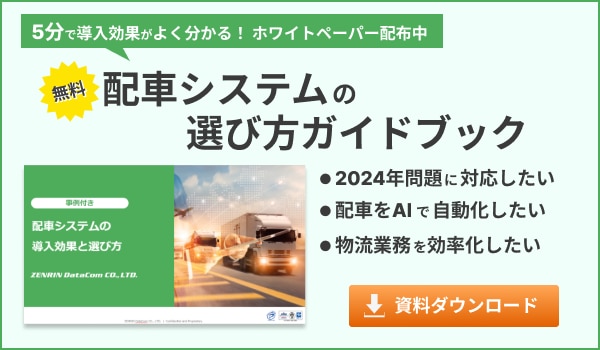物流コストとは? コスト上昇の原因や削減方法などを解説
物流業務を改善するためには、「物流コスト」の把握が必要不可欠です。
しかし、実際にかかる物流コストを正確に把握できている企業は少ないのではないでしょうか?
そこで本記事では、物流コストの内訳についてや上昇してしまう原因について解説します。
物流コストを削減する方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.物流コストとは
- 2.物流コストを予測するためには内訳の把握が重要
- 2.1.内訳① 輸送・運送費
- 2.2.内訳② 荷役費
- 2.3.内訳③ 保管費
- 2.4.内訳④ 管理費や人件費
- 2.5.内訳⑤ 包装費
- 3.物流コストを削減するために知っておきたい物流コスト比率とは
- 3.1.物流コスト比率の推移状況
- 4.物流コストが上昇してしまう原因3選
- 4.1.1.ガソリン価格の上昇
- 4.2.2.ドライバーの不足
- 4.3.3.積載効率の低下や輸送頻度の増加
- 5.物流コストを削減する方法5選
- 5.1.1.物流拠点を集約する
- 5.2.2.人件費や管理費を見直す
- 5.3.3.業務の効率化を図る
- 5.4.4.専門業者に委託する
- 5.5.5.管理ツールなどを導入する
- 6.まとめ:ツールなどを導入し、物流コストを削減しよう
- 7.物流コストの削減なら「ロジスティクスサービス」
物流コストとは

物流コストとは、物流業務において物を移動させるためにかかる費用の総称です。
物流というと輸送や運搬をイメージする人も多いと思いますが、商品の梱包や、保管するときにかかる費用も物流コストとして扱われます。
基本的に物流コストとは物流を生業にしている企業のコストを指し、細かくは以下のように分類することが可能です。
ミクロ物流コスト |
物流業界における企業ごとの売上高物流コスト比率の平均値。調査機関が企業に回答を得たデータを公開している。 |
マクロ物流コスト |
国全体の物流コスト。マクロ統計で推計している。 |
企業物流コスト |
企業にかかる物流コスト。 |
現在は原油価格の高騰を背景に、輸送面での物流コストも上昇傾向です。
全体の物流コストにあたるマクロ物流コストが上がっていくと、それに伴って物価が上がる傾向にあるため、物流だけでなく販売関連の企業も物流コストに関しては注意しておかなければなりません。
物流コストを予測するためには内訳の把握が重要

物流コストの変化を逐一チェックするのは重要ですが、予測するうえでは内訳の把握も必要です。
物流コストの内訳は大きく5つにわかれます。
内訳ごとにコストの変化をチェックして、今後の物流コストが上がるのか下がるのかを予測することが求められます。
それぞれの内訳について解説します。
内訳① 輸送・運送費
物流コストで一番イメージしやすいのが、輸送・運送費ではないでしょうか。
輸送・運送費で必要になる費用は主に下記のとおりです。
- 運搬するために利用する車両費用
- 配送業者を利用する場合の配送料
- ガソリン代
- 減価償却費
など
輸送・運送費は物流コストの内訳の中でも比率が高く、この部分のコスト削減が物流コスト削減の近道となります。
人件費だけでなく、運搬に必要な足となる飛行機などの運賃や、自社で運搬するためのトラックのガソリン代など、多くのコストがかかるため物流コストの内訳の中でもとくにチェックしなければなりません。
内訳② 荷役費
荷役費は、荷役作業にかかるコストのことです。
荷物を運ぶ作業のプロセスでは、ピッキングや仕分け、積付けを行ってから入出庫・運搬が行われます。
その際にかかるコストが荷役費に該当し、作業を行うスタッフに支払う人件費が主なコストの要因です。
作業量に応じて時間がかかればそれだけ人件費もかさみます。
そのため、長時間労働をスタッフに依頼すればするほど、荷役費の高騰につながるのです。
裏を返せば、一連の作業を効率化すればコスト削減を図れるため、ロケーション管理*1やアウトソーシング化などを活用し効率化する動きが進んでいます。
*1 ロケーション管理|倉庫内にある商品がどこの棚にあるのか、コードや番号を割り振りデータで管理することで、探す手間の削減や業務効率化を図る手法のこと
内訳③ 保管費
保管費とは、取引先に納品するまで商品を預かっておく際にかかるコストです。
具体的には外部倉庫を借りる場合の賃料や、自社で倉庫を保有している場合の維持費が大部分を占めます。
また、火事などの事故が起こった際のリスクヘッジとして保険に加入する必要性もあり、保険料も保管費のコストです。
保管料を削減するため
- 荷量に合った大きさの倉庫を借りる
- 光熱費を削減する
- 保管する拠点を統廃合する
などの工夫が必要になってくるでしょう。
内訳④ 管理費や人件費
物品の管理やそのためにかかるスタッフの人件費も、物流コストの内訳のひとつです。
管理費は、物流システムおよび受発注システムなどを導入する際に必要となる、初期投資や運営・維持費がコストとなります。
人件費に関しては上記の内訳でも触れましたが、運搬や荷役などのスタッフだけでなく、管理業務や営業のスタッフへのコストも必要です。
物流業務は繁忙期と閑散期に応じて必要な人手が変動します。
そのため、繁忙期に有期契約でスタッフを確保してコスト管理を行うのも選択肢のひとつです。
内訳⑤ 包装費
先ほどの荷役費でも触れましたが、物品を包装する際も人手が必要ですので、材料費や人件費などの包装に関わるコストを負担しなければなりません。
こちらも繁忙期に合わせて外注でスタッフを契約し、閑散期にコスト負担を減らす方法でコスト削減が図れます。
物流コストを削減するために知っておきたい物流コスト比率とは

物流コストの削減は、ビジネス上の最重要課題のひとつです。
まずは、自社の物流コストがどの工程で多くかかっているのかを把握し、無駄なコストが発生していないか把握しましょう。
物流コストは内訳でカテゴリー分けできるため、内訳ごとのコストをグラフで可視化などを行い、物流コスト比率をチェックできるようにするとわかりやすいです。
物流コスト比率を常に把握したうえで、優先的にコストを削減しなければならない箇所を明確化し、段階的に全体のコスト削減につながる改善を行っていきましょう。
物流コスト比率の推移状況
物流業全体の物流コストの比率は、日本ロジスティクスシステム協会(JILS)が情報を公開しています。
2021年度の物流コストに関する報告では、輸送費が50パーセントを超えており、次に保管費が20パーセント弱です。
参考:日本ロジスティクスシステム協会(JILS) 2021年度 物流コスト調査報告書
物流コストで輸送費が過半数を占めるのは2021年だけでなく、毎年の傾向です。
加えて、近年は原油価格の高騰などが影響して輸送費自体の必要経費が上昇傾向となっています。
物流コスト削減を目指す場合は、比率として最も高い輸送費の削減を優先的に目指すのが最善です。
物流コストが上昇してしまう原因3選

ここからは、物流コストが上昇する要因について説明します。
主な要因とされるのは、以下の3つです。
原因分析を事前に行い、どのようにコスト削減に取り組むべきか明確化しましょう。
それぞれ詳しく解説します。
1.ガソリン価格の上昇
ガソリン価格の高騰は輸送費にダイレクトに影響します。
海外から物品の輸送依頼をしたり、自社で運搬を行う際にもガソリン代の影響を受けるため、ガソリン代が上昇傾向の現在は輸送費もかさみます。
東京都区部におけるガソリン1リットル当たりの価格は、2022年7月に170円を超えました。
リーマンショック直前に180円を付けた2008年に迫る勢いで上昇しているため、ガソリン代のコストがさらに増えることも想定してコスト管理をしなければなりません。
ガソリン代に影響を与えるニュースをチェックして、その都度ガソリン代の変化を予測し対応する必要があります。
2.ドライバーの不足
現在物流業界はドライバー不足が問題視されていますが、運搬や輸送を担当するドライバーが不足すると物流コスト上昇につながってしまいます。
昨今はネットを利用した商品の売買が増加しており、それに伴い物流の需要も増加傾向です。
それにもかかわらずドライバーの報酬に見合わない長時間労働など、労働環境は決してよいとはいえず、ドライバー自体が減ってしまっているため、需要に見合ったドライバーの確保が困難です。
そうなると、ドライバーの待遇改善と人員確保のために雇用条件を見直す必要があります。
ドライバーにかける人件費が増え、輸送・運搬費を値上げする企業が数多く出てきたため、結果として物流コストは上昇しているのです。
もちろん、ドライバーの待遇を改善しないのは働き方改革の観点からも許されない話なので、ドライバーの待遇面を考慮することも大切です。
3.積載効率の低下や輸送頻度の増加
物流の需要が増加するにつれて、大型の荷物に加え小ロットの荷物の輸送が求められるようになりました。
小ロットの出荷の増加によって運搬時の空きスペース増加による積載効率が低下し、結果として輸送・運搬の頻度が増えてしまいコストが増加する状況が増えています。
効率的な輸送・運搬と安全面を両立させることが、今後のコスト削減に繋げるための課題です。
物流コストを削減する方法5選

ここからは、物流コストを削減する方法について解説します。
主に以下の5つがコスト削減案としてあがる項目です。
それぞれ段階を踏んでいく必要がありますが、これらの項目の改善を行い、コスト削減を行いましょう。
1.物流拠点を集約する
物流拠点を減らし集約することでコスト削減ができます。
物流拠点を多く用意すれば、商品の発注から納品までの輸送時間をカットでき、業務上のパフォーマンスは向上します。
しかし、その分保管のための倉庫が増え、管理者も必要となるためコストが増大することがデメリットです。
現在では宅配サービスの向上により、離島など一部地域を除きおおむね1日から2日以内での輸送が可能となり、リードタイムの問題も解消されてきているため、物流拠点をコスト削減のために減らす企業が増えています。
2.人件費や管理費を見直す
人件費の見直しを図ることも物流コスト削減の重要な項目です。
先ほども触れましたが、物流業界におけるドライバーの人手不足の原因は待遇がよくないことにあり、その点に関しても改善することが求められます。
しかし、作業用のロボットやツールでもできる軽作業や読み取り、事務作業に関しては人件費をかけずに自動化することも不可能ではありません。
人手が必要な工程ではしっかりと待遇改善を行い、自動化できるところは自動化し人件費を見直しましょう。
3.業務の効率化を図る
業務の改善については多くの企業が実践していますが、実際には実現できないことも多くあります。
余計なコストを削減するためには、効率化は徹底して行わなければなりません。
しかし、社内で効率化できる項目の洗い出しや業務の改善方法を検討するだけでは見えてこない部分があります。
勤務状態や輸送の際のドライバーの運転状況を管理するツールを導入すれば、これまでチェックしきれなかった部分がデータで可視化され、効率よく業務を行うための改善点が見えてくるでしょう。
4.専門業者に委託する
専門業者に委託するアウトソーシングも物流コスト削減における有力な選択肢です。
システムの構築から実際の物流業務まで委託を請け負ってくれる業者も多く、プロに大部分の仕事を任せることで、在庫管理の最適化や業務効率化を目指します。
専門業者に効率化したい箇所の仕事を任せることで、結果的に余計なリソースにお金をかけずにコストを削減できるでしょう。
システム構築からオペレーションまでを委託できる3PLといわれるアウトソーシングが、物流業界で人気を集めていますが、さらに物流のコンサルティングまで担当してくれる4PLも注目されています。
5.管理ツールなどを導入する
ここまで4つの物流コスト削減方法について触れてきました。
しかし、いずれも社内でチェックするだけでは見えてこない問題も多く、実際にどの部分から改善すればよいのかがわからないことも多いでしょう。
そのようなときに役に立ってくれるのが、物流業務の管理ツールです。
どのような箇所にコストがかかっているのか、どこを改善すればいいのかを分析してくれるだけでなく、細かいデータを管理して確認しやすくしてくれます。
どの物流コスト削減を実施するにあたっても、コストがかかる箇所の確認や削減方法の明確化が求められるため、管理ツールの導入は有力な選択肢といえるでしょう。
まとめ:ツールなどを導入し、物流コストを削減しよう
ここまで、物流コストの概要や削減方法について説明しました。
物流コスト削減については物流拠点を必要以上に増やさない、勤務状態の管理やアウトソーシング化など、業務内容の見直しや最適化を行い、いかに効率化できるかが重要です。
物流の管理ツールは最適化ルーティンの作成や業務状況の分析を行ってくれるため、どの物流コストを削減する場合でも役に立つでしょう。
物流コスト削減を目指す場合は、専用の管理ツールの導入が第一歩といえるかもしれません。
物流コストの削減なら「ロジスティクスサービス」
物流コストの削減のために管理ツールを使用するなら、ゼンリングループの「ロジスティクスサービス」の導入もおすすめです。
「ロジスティクスサービス」は運搬業務や配車状況を分析したうえで、配車とルーティングの最適化、効率的な配送計画を作成・提供します。
加えて、APIで提供できるサービスもありますので、すでに管理用の自社システムを利用している場合でも必要な機能を追加し利用することが可能です。
業務効率化のために初めてツールを導入したいと考えている場合や、使い慣れたシステムにコスト削減のための管理ツールを組み込みたい場合も「ロジスティクスサービス」をぜひご検討ください。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/