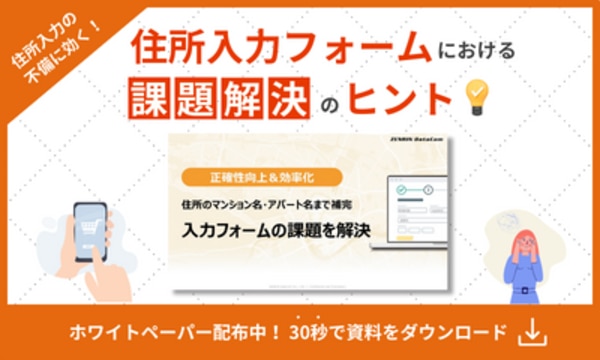測地系とは?座標系との違いや日本測地系と世界測地系の変換方法についても解説
地球上における特定の地点の位置を数値で表示する際、測地系という基準が用いられます。測地系は地図の作成や測量等さまざまな社会活動を支えているものですが、具体的にどのような基準なのか、座標系とは何が違うのか詳しく知らない方もいるでしょう。
そこで今回は、測地系の概要・種類や座標系との違い、日本測地系・世界測地系の変換方法等について解説します。また、地図データの利用におすすめのサービスもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
★測地系の変換にお困りですか?ZENRIN Maps APIが解決します。
→お気軽にゼンリンデータコムへご相談ください
目次[非表示]
測地系とは?

測地系とは、地球上でのある地点の位置を緯度・経度・高さで表す際の座標の基準です。地球の形・大きさ・座標原点等を基準点から測定した座標が測地系に該当します。
測地系で位置を決める際の基準点は、世界各国で異なります。日本にも独自の基準点があり、時代と共に変化してきました。
そんな測地系は、特定の位置にアクセスできるようにするための基盤として提供されており、大規模工事・測量・土地管理・地図制作等あらゆるシーンで活用されています。
測地系の種類

測地系は、大きく分けて世界測地系と日本測地系の2種類があります。それぞれの特徴や違いは以下のとおりです。
世界測地系
世界測地系は、国際的に定められている測地系のことです。世界的に整合性や地球全体に適合性がある測地系であることから、日本でも活用されるようになりました。
現在は人工衛星やVLBI等を用いて、地球規模で高精度な観測が可能となっています。例えば、VLBIなら天体が放つ電波を用いて、数千kmも離れたアンテナの位置を図ることができます。わずか数mmの誤差は生じてしまうものの、観測の精度は非常に高いです。
これらの高度な観測データから明らかになった地球の形状・大きさに基づいて測量されるものが、世界測地系です。
日本測地系
日本測地系は、日本独自の基準点で構成された測地系です。2002年の測量法改正まで、日本測地系を用いて測量が行われていました。
この測地系では、地球の形をベッセル楕円体として、天文観測によって定められた緯度・経度原点値と原方位角を基準に測定されているのが特徴です。
ベッセル楕円体は、ドイツの天文学者であるベッセルが定めた楕円体です。地球の形は球体というイメージがありますが、実物は自転していることから遠心力によって楕円形となっています。その考えのもと、日本測地系では明治時代からベッセル楕円体が採用されているのです。
また、日本では明治時代に正確な地形図を作成する目的で、全国に緯度経度の基準点網が整備されました。天分観測によって、東京天文台(旧国立天文台跡地)の緯度経度が日本測地系における経緯度原点と定められたのです。
★測地系の変換にお困りですか?
→お気軽にゼンリンデータコムへご相談ください
測量の基準が日本測地系から世界測地系に改正された背景

日本では長きにわたって日本独自の測地系を基準に測量が行われていました。しかし、2002年4月から測量法が改正され、基本測量や公共測量では世界測地系を用いることが義務付けられています。
改正された主な背景は、基準点網にひずみやGPS・GISの普及に対する対応です。明治時代と現代では、測量技術や測量機器の性能に違いがあり、技術が向上して昔よりも正確な測量が可能となりました。
また、100年間に及ぶ地殻変動の影響で、日本列島の位置にズレが生じています。例えば、東京から見たときの札幌の位置は西に9m程、福岡は南に4m程ずれていることが判明しています。
そして、現代はGPSやGISを活用した位置情報の測定や利用技術が登場し、急速に普及しました。これらの技術に対応していくためには、世界共通の基準で高精度な測量が求められるようになったのです。
このように、技術の進歩や時代の変化に対応するために、測量法が改正され、日本測地系から世界測地系に移行することになりました。
地球の大きさや形状の定義

測地系を構成する要素には、地球の大きさと形状があります。地球の形状モデルに準拠楕円体とジオイド面があるので、それぞれの定義をご紹介します。
準拠楕円体
地球には山や谷が存在するので、表面に凹凸がある形状をしています。しかし、このままの形状を基準にすると測量が複雑になってしまうので、シンプルな形状にモデル化されています。
準拠楕円体(地球楕円)は、地球の形状を後述するジオイド面に近い楕円体にモデル化したものです。GRS80楕円体やWGS84楕円体等の種類があり、名称や地球の大きさ等の定義は国によって異なります。
例えば、日本測地系で採用されているベッセル楕円体の場合、長半径(赤道半径)は6,377,397.155m、扁平率は1/299.152813です。2024年5月現在、世界測地系として広く使われているGRS80であれば、長半径は6,378,137m・扁平率は1/298.257 222 101と定義されています。
ジオイド面
地球の表面は海洋に覆われており、その水が重力や遠心力に逆らわずに地球の表面を覆ったと仮定した場合の海洋面の形状をジオイド面と呼びます。簡単にいえば、凹凸のある地球の形状を滑らかにモデル化したものです。
日本では、ジオイドと東京湾平均海面は一致すると考えられています。そのため、東京湾の平均海面を標高0mと定義して、日本の土地の高さ(標高)が測定されているのです。東京湾平均海面を地上に固定するために設定された日本水準原点の数値は、東京湾の平均海面上24.3900mと定義されています。
なお、ジオイド面にも起伏があり不規則な形状となっているため、よりシンプルなモデルとして準拠楕円体が考案されました。
測地系と座標系の違い

測地系は、地球上の位置を緯度・経度・標高を使って示す基準です。
それに対して座標系は、平面や空間での位置を示す際、原点や座標軸等によって位置を定める基準のことです。
「原点をどこにするか」「座標の単位をどうするか」等のルールに従って座標を決めていきます。
代表的な座標系には、緯度経度座標系や平面直角座標系があります。緯度経度座標系は、地球上の特定の位置を緯度と経度で表す地理座標の一種です。緯度・経度は地球中心の角度から「○○度○○分○○秒」で表現されます。
平面直角座標系は、地球を2次元の平面上に投影し、XY座標で表現する投影座標系の一種です。日本では公的測量で使われており、狭い範囲の測量や大縮尺地図で活用されています。
公共測量で使われている平面直角座標系は国土地理院によって19に分類されており、適用区域ごとに計番号が異なる特徴があります。
日本で用いられる世界測地系の種類

世界測地系は各国で採用されており、国ごとに使われている種類が異なります。日本では、日本測地系 2000・日本測地系 2011・WGS 84が使われています。それぞれの特徴は以下のとおりです。
日本測地系 2000
日本測地系 2000(JGD2000)は、測量法と水路業務法の一部改正に伴い、2002年4月から用いられている世界測地系です。以前の日本測地系との違いは以下のとおりです。
旧日本測地系 |
日本測地系 2000 |
|---|---|
・日本周辺のみに適用することが前提の測地系 |
|
日本測地系 2000では、準拠楕円体にGRS80楕円体を採用しています。また、座標系に関しては、旧日本測地系は日本独自の基準となっていましたが、ITRF 94座標系を採用しました。
日本測地系 2011
日本測地系 2000に代わる測地系として登場したのが、日本測地系 2011(JGD2011)です。東日本大震災の影響による地殻変動が起き、国土地理院は2011年10月に測地成果を発表しました。
その成果をもとに測地系は再構築されています。そして、2012年の測量法改正に伴い、日本測地系 2011に移行しました。
準拠楕円体は、2000同様にGRS80です。しかし、座標系に関しては東日本と北陸はITRF2008、それ以外の地域はITRF 94座標系を採用した点が大きな変更点です。また、ジオイド面の基準も日本のジオイド2011に変更されています。
WGS 84
WGS 84は、アメリカで構築された世界測地系です。主にGPSの運用に用いられている測地系になります。
準拠楕円体に、WGS84楕円体を採用しているのが特徴です。座標系は海域の測地系ではWGS84が標準とされていますが、精密に陸地を測量する場合はITRF系が推奨されています。
日本測地系2011とWGS84では、準拠楕円体や座標系の種類が異なります。しかし、準拠楕円体と座標系の差はわずかなものと見なされているので、ほぼ同じものと考えて問題ありません。
日本測地系と世界測地系の相互変換の方法

日本独自の基準である日本測地系は、2002年4月以前まで長きにわたって使われてきました。
旧日本測地系は、現在適用されている世界測地系に相互変換することが求められます。ここからは、相互変換が必要となる理由や変換方法をご紹介します。
日本測地系と世界測地系の相互変換が必要な理由
旧日本測地系と世界測地系では、採用している準拠楕円体が異なります。つまり、地球の形状のパラメーターが異なるため、測量成果にズレが生じてしまうのです。旧日本測地系(ベッセル楕円体)と世界測地系(GRS80楕円体・WGS84)のパラメーターは以下のとおりです。
準拠楕円体 |
長半径 |
扁平率 |
|---|---|---|
ベッセル楕円体 |
6,377,397.155m |
1/299.1528128 |
GRS80楕円体 |
6,378,137m |
1/298.257222101 |
WGS84 |
6,378,137m |
1/298.257223563 |
このように、準拠楕円体によってパラメーターの定義が異なります。相互変換を行うことで、経緯度の数値のズレを補正することが可能です。相互変換の方法は、簡易計算式と高度計算式の2つに分けられます。
簡易計算式による変換
日本測地系と世界測地系の経緯度の差を加える、または引くことで相互変換が可能です。あくまでも簡易的な計算となるため、数mほどの誤差が生じます。精度はそれほど高くないため、大まかな変換と考えてください。
【日本測地系を世界測地系に変換する場合の計算式】
- 世界測地系緯度:緯度(日本測地系)-0.00010695×緯度(日本測地系)+0.000017464×経度(日本測地系)+ 0.0046017
- 世界測地系経度:経度(日本測地系)-0.000046038×緯度(日本測地系)-0.000083043×経度(日本測地系)+0.010040
【世界測地系を日本測地系に変換する場合の計算式】
- 日本測地系緯度:緯度(世界測地系)+0.00010696×緯度(世界測地系)-0.000017467×経度(世界測地系)-0.0046020
- 日本測地系経度:経度(世界測地系)+0.000046047×緯度(世界測地系)+0.000083049×経度(世界測地系)-0.010041
高精度計算式による変換
より精度の高い相互変換を行うためには、高精度計算式を使います。国土地理院が公開する「Web版 TKY2JGD」を活用すれば、簡単に高精度計算式による相互変換が可能です。
Web版 TKY2JGDでは変換する方向を選択して、経緯度または平面直角座標を入力し、「計算実行」をクリックするだけで自動的に変換してくれます。経緯度は平面直角座標を手動で入力する以外に、下部の地図上で選択すると自動的に数値を入力することが可能です。
★日本測地系⇔世界測地系の相互変換ならゼンリンデータコムにご相談ください
→まずは気軽に相談してみる
詳細な地図データを利用するならゼンリンデータコムにご相談ください

ビジネスに地図データを利用したいときは、ゼンリンデータコムにお任せください。地図システムや物流DX等に活用できる地図APIを複数ご用意しています。ゼンリンデータコムから利用できる主な地図APIは以下のとおりです。
API名 |
特徴・メリット |
測地系 |
|---|---|---|
・Google LLCが提供するWeb地図サービス |
世界測地系 |
|
・詳細な住宅地図の表示が可能 |
世界測地系 |
地図APIサービスによって特徴や機能差があるため、目的・用途に合わせてお選びいただけます。どの地図サービスを選ぶべきか迷った際は、ゼンリンデータコムまでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ|ゼンリンデータコム法人向け地図・位置情報サービス
まとめ:測地系を理解して測量や地図作成等のビジネスに活かそう
今回は測地系についてご紹介しました。測地系は、地球上で特定の位置を数値で表す際の基準です。
国によって測地系の定義に違いがあり、日本にも独自の基準がありました。現在は地殻変動やGPS・GISの普及への対応が求められたことで、世界的な範囲で適用できる基準が用いられています。
測地系は測量や地図制作、土木・建築等さまざまなシーンで用いられています。そのため、測地系の理解を深めてビジネスに活用していきましょう。