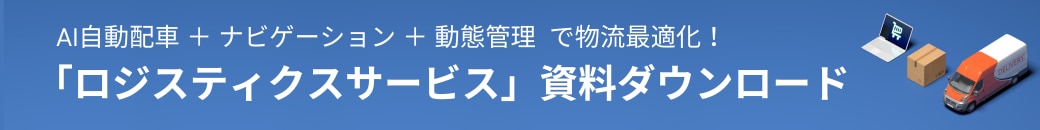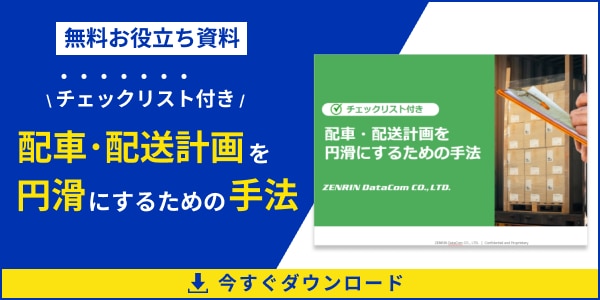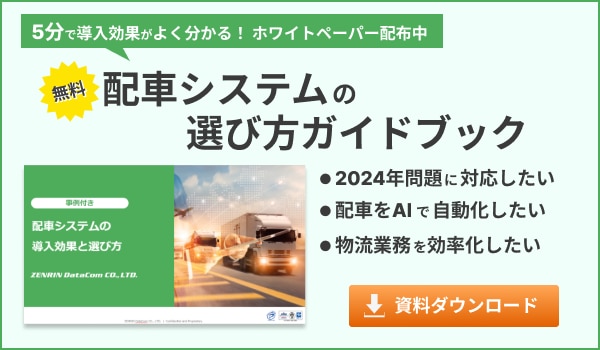現状の物流とこれから求められることとは?物流の基本やロジスティクスとの違い等を解説!
物流とは、物的流通の略で、物流業者がその商品を消費者へ届けるプロセスのことです。
プロセスの中には単に商品の輸送だけでなく、商品の生産から物流センター内での商品の保管、在庫管理、包装等、消費者へ届けるまでに必要な機能や過程が含まれています。
この流れを一括して管理することで、物流全体を最適化することが可能です。
この記事では、物流の目的や機能、領域をはじめ、今後の物流業界の展望について解説していきます。
■物流システムで物流業務の効率化を図りませんか?
⇒ロジスティクスサービスの資料を見てみる
目次[非表示]
- 1.物流とは
- 1.1.物流とロジスティクスの違い
- 1.2.物流と流通の違い
- 1.3.物流と商流の違い
- 2.物流の基本的な流れ
- 3.物流業務に必要な機能
- 4.物流の主な領域
- 5.今の物流の課題とこれからの物流に求められること
- 6.物流の基本を把握し、課題解決に取り組もう!
- 7.物流業務の効率化には「ロジスティクスサービス」が有効!
物流とは

物流とは、先述したとおり、一般企業がその商品を消費者へ届けるまでの過程のことを指します。
ただ、物流と意味を間違えやすい言葉として、「ロジスティクス・流通・商流」等があり、違いが明確にわからない方も少なくありません。
ここからは、物流とこれら3つの違いについて紹介していきます。
物流とロジスティクスの違い
ロジスティクスは、「必要な商品を、必要なときに、必要な場所に、必要な量だけ迅速に」供給する仕組みのことです。
物流は、このロジスティクスの中に含まれています。
2つの違いは以下のとおりです。
- 物流:モノの一連の流れ(商品の包装・保管・輸送等)
- ロジスティクス:物流の一括管理・最適化
このように物流を一括管理しているのがロジスティクスです。
ロジスティクスを導入することで、素早く無駄のない物流の過程を実現し、物流全体を最適化できるでしょう。
関連記事:ロジスティクスとは?物流との違いや仕組みについて徹底解説!
物流と流通の違い
物流と流通では、所有権やプロセス、役割が異なります。
物流と流通には以下の違いがあります。
- 物流:モノの地理的な移動
- 流通:消費者と生産者の間に立ち、モノだけでなく、お金や権利等、サービスや商品を移動させる一連の流れ
上記のように、流通は生産者から消費者に商品を受け渡すまでの一連の流れで、物流はその中の「モノの流れ」を指します。
つまり、大枠である流通の中に物流があるということです。
似たような言葉ですが、内容が違うので混同しないように気を付けましょう。
物流と商流の違い
一般的に、物流と商流には以下のような違いがあります。
- 物流:モノの地理的な移動
- 商流:商品の所有権・金銭・情報の移動
モノの流れを指す物流と違い、商流は商品の所有権の移動等の取引上の流れを指します。
配送業者が消費者に商品を届けて受領サインを求めたとき等、物流と商流が同時に発生する場合や、どちらか一方のみ発生する場合もあります。
物流と商流は役割が違いますが、物流業界において、密接な関係があるのです。
物流の基本的な流れ

物流の基本的な流れは以下5つの主要なステップで構成されます。
- 商品の入荷:商品が供給元から物流センターに運ばれる
- 商品の保管・管理:商品を適切な環境で安全に保管
- 顧客からの受注:顧客からの受注が発生すれば、流通加工が始まり、商品は出荷の準備として適切にパッケージ化
- 倉庫業務:受注された商品は正確に並べられ、トラッキング番号等の重要な情報が商品に追加
- 配送:商品の配送が開始され、顧客に安全・正確に配送
以上が物流の基本的な流れとなります。
物流業務に必要な機能

物流の機能とは、生産者から消費者へ、モノを効率良くスムーズに届けるための仕組みのことです。
商品を運ぶ、移動するだけでなく、保管や包装加工等の工程も含まれています。
ここでは、物流の6大機能について紹介します。
【物流の6大機能】
輸送・配送
生産者から消費者へモノを送り届ける機能が「輸送・配送」です。
輸送は、「一時輸送」ともいわれ、工場から物流センターまで運ぶ場合等、長距離の移動を伴う場合を指します。
配送は「二次輸送」といわれ、物流センター等から消費者に届ける、近距離の小口輸送のことです。
この輸送と配送で物流コストの6割を占めるといわれています。
保管
物流機能の中でも、輸配送とともに中核的な機能である「保管」は、物流センターや配送センター等が該当します。
商品や荷物が入庫してから在庫管理し、ニーズに応じて発送するまでの流れをスムーズに行うための機能です。
生産者と消費者間の時間的・空間的ギャップを調整して、タイムリーにモノを届ける役割を担っています。
また、冷蔵・冷凍倉庫や食品加工を行うプロセスセンター等、商品の品質や価値を保つ機能を担う保管施設も保管機能に当てはまります。
保管効率を上げるには、商品のピッキングがスムーズにできるようになることがポイントです。
保管スペースの見直しや設備を整える等の工夫を施しましょう。
包装
商品を生産されたままの状態で、飛行機や船、トラック等で輸送してしまうと、傷ついたり、破損したり、品質が低下してしまう恐れがあります。
包装は、この物流過程で生じる傷や破損等の物理的なダメージから商品を守るための過程です。
ダンボールや木箱等で保護するケースが多いようです。
そうすることで、振動や落下による破損を防ぐだけでなく、湿気によるカビの発生や腐食による品質低下の予防が可能です。
また、ダンボール等で包んだ商品に、内容名や内容量、製造年月日等を印字すると商品の区別がしやすくなるメリットもあります。
荷役
「荷役」は、物流センターや倉庫の内外で行う荷物の積み下ろし、運搬、入出庫、ピッキング、仕分け等の業務全般を表す作業工程のことです。
物流コストにおいて大きな割合を占め、荷役のロスは物流コストの増加に直結します。
荷役の工程は、以下の6つです。
- 荷揃え
- 積み付け・積卸し
- 運搬
- 棚入れ(保管)
- 仕分け
- ピッキング(集荷)
それぞれの作業が物流の生産性や品質に大きな影響を及ぼすため、効率化したいポイントでもあります。
流通加工
流通加工は、商品を仕入れた後、倉庫や物流センターで適切に加工し、顧客への配送を最適化する機能のことです。
流通加工には、商品の仕分け、ラベリング、包装、商品の組み立て、再梱包等の作業が含まれます。
これにより、商品の保管や輸送時の効率が向上し、顧客に対して正確かつ迅速に商品を提供することが可能になります。
さらに、流通加工は在庫管理や品質管理にも影響を与えるだけでなく、例えば商品の組み立てを行い配送することでお客様の手間を省くことができます。
総合的な物流業務において、流通加工はスムーズな流通を実現するためや、顧客満足度に欠かせない機能といえるでしょう。
情報処理
商品の効率的な流通を実現するためには、適切な情報処理が欠かせません。
情報処理は、在庫管理、運送ルート最適化、配送スケジュール作成等の情報を把握し、サポートすることです。
在庫管理では、商品の入出庫を追跡し、在庫状況をリアルタイムで更新します。
運送ルート最適化の場合は、輸送コストと時間を最小限に抑える最適なルートを計算することが求められます。
また、配送スケジュール作成では、ドライバーのスケジュールやお客様の時間指定等に対応した最適なスケジュールを立てる必要があります。
これらの取り組みが物流業務の円滑な運用と顧客サービスの向上に大いに貢献するため、情報処理の機能も、物流において非常に重要です。
物流の主な領域

物流は、企業の活動や実態に応じて以下4つの領域があります。
サプライチェーン※の最適化を目指すためには、これらの物流領域が円滑に運営されていることが必要です。
それぞれについて紹介していきます。
※サプライチェーンとは原材料の調達から消費者の手に届くまでの一連の流れを指す
調達物流
調達物流は、組織が商品やサービスを生産するために必要な材料や部品を供給者から調達するプロセスを指します。
これには、商品の購入、配送、在庫管理、および供給リスクの管理などが含まれます。
調達物流は、製造業の運用効率とコスト管理に大きな影響を及ぼし、商品の品質と供給の信頼性にも直接影響するプロセスです。
以前はあまり注目されていない領域でしたが、日本では多くの会社が多品種少量生産を取り入れています。
「必要なモノを、必要な量だけ、必要なときに」調達し生産するジャストタイム供給が業務効率の改善につながるため、多くの企業で実践されている物流です。
生産物流
生産物流とは、調達した部品や資材の管理から商品の管理、包装、倉庫への発送までを含む流れのことです。
調達した部品や資材の保管・管理、荷役、梱包、包装作業、出庫作業等が含まれます。
調達物流や販売物流の間を担うため、円滑な連携を図ることで納期管理や出庫管理、発送管理を最適化できるだけでなく、配送車両の動態管理もすることが可能です。
値札やラベルの取り付け、袋詰め、販売サイズへの小分け、ギフト商品にするためのセット組み等の流通加工も「生産物流」に含まれます。
販売物流
「販売物流」とは、完成した商品を物流センターや小売店を介して消費者に運ぶ物流です。
納品先と取り決めたサービスレベル(納品ルール)にしたがって納品を行います。
近年、ネット通販等が普及したことにより、消費者へ届ける物流も販売物流の中では大きな割合を占めています。
配送センターや物流倉庫を介するか、生産拠点から直送するか、どのパターンでもジャストタイム供給を実現させるためには、輸送・配送・在庫管理等の効率化が不可欠です。
回収物流
「調達物流」「生産物流」「販売物流」による、生産から消費までの流れを「動脈物流」と呼びます。
これに対して、返品されたモノやダンボール等の廃材・リサイクル可能なオリコン(プラスティックコンテナ)等を回収するためのモノの流れのことを、「回収物流」または「静脈物流」といいます。
近年、企業のSDGs活動への姿勢が注目されており、資源を無駄にしない「回収物流」への取り組みが欠かせません。
今の物流の課題とこれからの物流に求められること

物流業界は、消費者が快適に生活を送るために欠かせませんが、解決しなければいけない課題も多くあります。
物流業界では以下のようなことが主な課題とされています。
- 労働力不足
- サプライチェーンの脆弱性
- 燃料費と環境負荷
- 技術の進化と適応
- 物流の透明性 等
これらの課題を解決するためには、以下のことが求められます。
- 環境負荷の軽減
- デジタル化と自動化
- データ活用
- 柔軟性とレジリエンス
- 顧客体験の向上 等
法改正による取り組みも少しずつ加速しており、業界全体の効率化や働きやすさ等が、今後発展し続けていく可能性のある業界です。
通販事業等のインターネットサービスは今後も拡大していくと考えられるため、物流業界の市場も拡大する可能性が高いです。
多くの企業で、物流システムや流通ロボットの導入、トラックの自動運転やドローンの活用、さらにAI技術を活用した業務効率化が進んでいくでしょう。
物流の基本を把握し、課題解決に取り組もう!
物流は消費者の生活に欠かせない社会インフラです。
インターネットサービスの普及による通販事業の拡大に伴い、物流業界全体の市場規模も拡大しています。
人材不足が課題とされていましたが、近年は人材不足を補うDX等の取り組みや、業務効率化のための取り組みを行っている企業も増えており、今後もそのような対応が増えていくと考えられます。
働き方改革の法改正も可決され、今後ますます物流業界における課題解決の取り組みが必要です。
業務の効率化や働きやすさという面からも発展し続けていくため、物流業界の基本を把握し、課題解決に取り組みましょう。
物流業務の効率化には「ロジスティクスサービス」が有効!
「ロジスティクスサービス」は、物流業務の効率化に有効なソリューションです。
以下が主な機能です。
- AI自動配車機能:ベテラン配車マンのノウハウを蓄積し、誰でも簡単に配車計画を作成できるよう支援してくれます。
- ナビゲーションアプリ:最適な運行ルートで到着地点へ案内してくれます。
- 動態管理機能:リアルタイムで業務の進捗状況を把握でき、ドライバーのサポートや日報の自動化など事務作業の負担軽減にも寄与します。
ロジスティクスサービスを導入することで、配車とルーティングの最適化ができ、物流のコスト削減の実現が可能です。
さらに、既存の業務アプリとの連携や、物流業務に役立つ各種APIの提供もしています。
ご興味のある方、ぜひ以下から資料をダウンロードしてみてください。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/