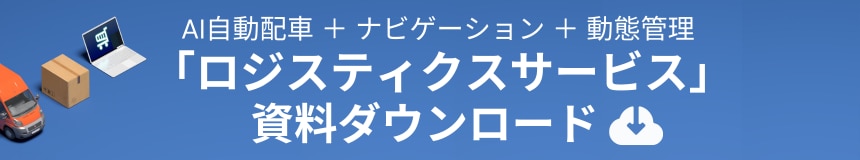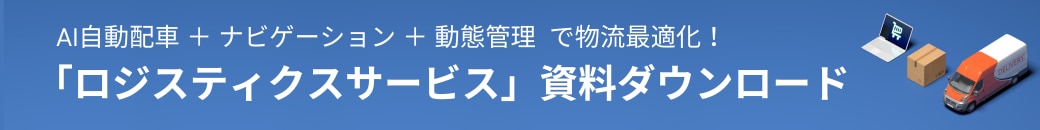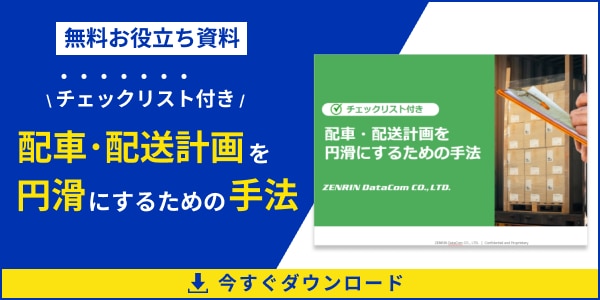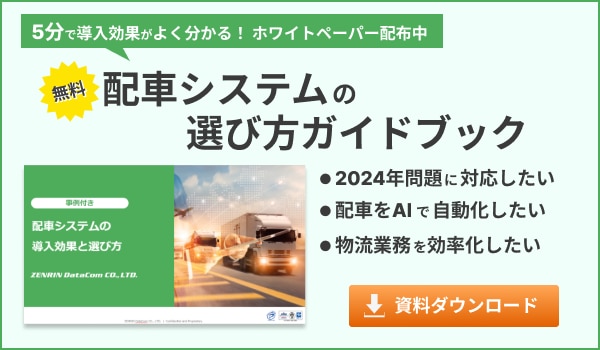過積載とは? 責任や罰則、防止するための対策案等を解説!
運送業務を行う際は、過積載に注意が必要です。
過積載は罰則の対象となり、未然に防ぐ対策案を講じておかなければなりません。
しかし「そもそも過積載とは?」「過積載の責任は誰にあるのか?」と、詳しい概要を知らない方もいるでしょう。
そこで、この記事では過積載について、責任や罰則等を詳しく解説します。
過積載を防止するための対策案もあわせて紹介しますので、最後まで読んで業務に役立ててください。
★荷量を考慮した配車計画、積載率の設定で過積載防止! |
目次[非表示]
- 1.過積載とは?
- 2.過積載にならない範囲とは?
- 2.1.過積載の許容範囲はある?
- 3.最大積載量の計算方法
- 4.過積載の危険性とは?
- 4.1.制動距離が長くなる
- 4.2.スピードの制御が難しくなる
- 4.3.荷崩れが起きやすくなる
- 5.過積載の責任は誰にある?
- 6.過積載の罰則
- 6.1.過積載が10割以上の罰則
- 6.2.過積載が5割以上10割未満の罰則
- 6.3.過積載が5割未満の罰則
- 7.過積載を防止するための対策案
- 7.1.自重計で積荷を計測する
- 7.2.目視で積載量を確認する
- 7.3.監督者を設ける
- 8.まとめ:過積載に許容範囲はないので徹底した対策が必要!
- 9.過積載を防止し、運送業を効率化するなら「ロジスティクスサービス」を利用しよう!
過積載とは?

過積載とは、道路運送車両法で定められた最大積載量を超えて荷物を運搬することです。
トラック等の貨物自動車に、最大積載量を超える荷物を乗せて走行した場合、罰則の対象となります。
運送業において、荷物の積載量は業務効率に関わるため、非常に重要です。
たしかに積載量が多いほうが、一度の走行で効率よく荷物を運べます。
しかし、過積載になってしまうとドライバーの安全にもかかわり、また荷主も罰則の対象となるため、運送業に携わる方は最大積載量に注意しなければなりません。
過積載の取り締まりは近年厳しくなっていますので、最大積載量を守って業務を遂行しましょう。
★積載率の設定で過積載を防止しませんか? |
過積載にならない範囲とは?

道路運送車両法を守って運送業務を遂行するために、過積載にならない範囲を理解しておきましょう。
次の車両で定められた積載量以内であれば、過積載にはならないと考えてよいでしょう。
貨物自動車の種類(通称) |
過積載にならない範囲 |
小型トラック(2トン〜3トントラック) |
最大積載量3.0トン以内 |
中型トラック(4トントラック) |
最大積載量3.0〜6.5トン ※免許の種類に準ずる |
大型トラック(10トントラック) |
最大積載量6.5トン以上 (トラックの形状によって変わる) |
小型ダンプカー ※メーカーや車種で異なる |
最大積載量2.0トン程度 |
中型ダンプカー ※メーカーや車種で異なる |
最大積載量3.5トン程度 |
大型ダンプカー ※メーカーや車種で異なる |
最大積載量9トン程度 |
なお、ダンプカーはメーカーや車種によって、最大積載量が異なります。そのため、最大積載量はあくまで目安として覚えておきましょう。
過積載の許容範囲はある?
「過積載に許容範囲があるのか?」もしくは、「数kg単位であれば、積載量を超えても走行できるのでは?」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、過積載に許容範囲はありません。
最大積載量を1kgでも超えると、過積載として判断されます。
最大積載量まで積んだトラックの運転は非常に危険であるため、余裕を持った積載量で業務を行うことが重要です。
「少しくらいなら積載量を超えても大丈夫」といった考えはやめましょう。
最大積載量の計算方法
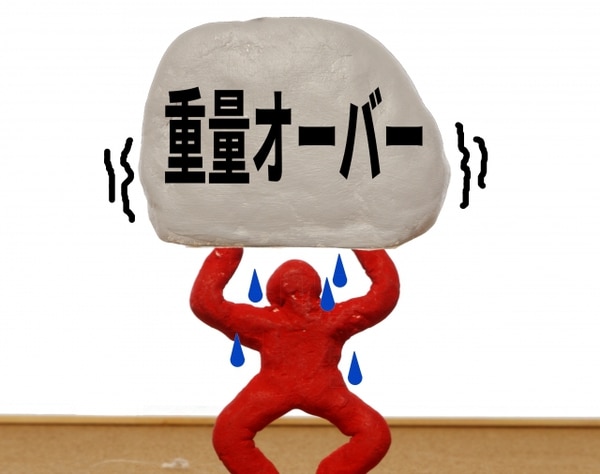
過積載にならない範囲で運送業務を行うために、最大積載量の計算方法は把握しておくことが大切です。
トラック等の貨物自動車を運転する際には、乗車人数や車両重量を差し引いた最大積載量を計算しておきましょう。
トラックを測定器にかけても、車両重量や乗員等積荷以外の重量があるため、正確な積載量は測れません。
最大積載量を計算する際には、以下の計算式を使用します。
車両総重量 - ( 車両重量 + 乗車定員 × 55kg ) = 最大積載量
車両の総重量から、車両重量と乗車定員の体重を差し引いて、最大積載量を求めます。
乗車定員の体重は、1人あたりを55kgだと想定して計算するので一律です。
運送業務を行う際には、車両ごとの最大積載量を計算して過積載に注意しましょう。
過積載の危険性とは?

過積載の取り締まりが厳しくなり法律で罰せられる理由は、最大積載量を超えて運転すると危険だからです。
最大積載量を超える過積載には、次のような危険性があります。
運送業の方は、過積載の危険性を理解して安全に業務を遂行してください。
制動距離が長くなる
過積載で運転をすると、制動距離が長くなります。
制動距離が長くなる理由は、積荷の重さによりトラックの進行方向にかかる力が大きくなるからです。
過積載で運転すると、通常よりも制動距離が長くなって予想外の事故に発展する可能性があるでしょう。
最大積載量未満で運転しているトラックより、過積載のトラックはブレーキを踏んでも車が止まるまでに長い距離が必要になります。
過積載は制動距離が長くなることで、事故を誘発する原因となるため注意してください。
スピードの制御が難しくなる
過積載で運転すると、スピードの制御が難しくなるため危険です。
積載量が多い分、位置エネルギーと運動エネルギーが大きくなり、走行スピードが上がります。
とくに下り坂では予想外のスピードが出てしまい、ブレーキを踏んでも間に合わない場合もあるでしょう。
過積載の車ではブレーキに負荷がかかり、熱によってブレーキが効かなくなる「フェード現象」にも注意が必要です。
スピードの制御が難しいと事故に発展するリスクが高まるため、過積載には十分注意してください。
荷崩れが起きやすくなる
過積載の状態で運転すると、荷崩れが起きる可能性があります。
最大積載量以上の積荷を乗せるためには、荷台や車両いっぱいに荷物を積み込まなければなりません。
無理な積み込みは荷台や車両に負荷がかかり、走行中に荷崩れが起きる危険性が増えるでしょう。
走行中に荷崩れが起きると、道路や他の車両に被害がおよび、甚大なる事故へ発展する可能性が高くなります。
荷崩れによる大きな事故を防ぐため、過積載は絶対にやめましょう。
過積載の責任は誰にある?

過積載が起きた際の責任は、誰にあるのか理解しておきましょう。
過積載のトラックを運転した運転手だけでなく、事業主と荷主にも責任があります。
運転手以外にも運送業務を命じた事業主と、積荷を引き渡した荷主は、過積載が起きた責任を負わなければなりません。
最大積載量を何割超えたかで罰則の内容は異なりますが、それぞれに課せられる責任・罰則は次の通りです。
過積載の責任 |
過積載の罰則例 |
運転手 |
重量測定受任義務・積み荷の現場取り下ろし・警察官による通行指示・違反点数・反則金・免許停止・懲役 |
事業者 |
公安委員会による指示・車両の使用制限処分・罰金・懲役・事業許可の取り消し処分・運行管理者資格の取り消し |
荷主 |
再発防止命令勧告・罰金・懲役・協力要請書、警告書、荷主勧告の発動 |
運送業務に携わる方は、自身の責任を果たすために過積載が起きないよう注意してください。
★安全な積載量で業務を効率化! |
過積載の罰則

過積載が起きた際の罰則は、積載量によって異なります。次の3パターン別に、過積載の罰則を紹介しますので、確認しておいてください。
過積載が10割以上の罰則
過積載が10割以上の際に課せられる罰則は、次の通りです。
違反内容 |
過積載の罰則 |
運転手(中型トラック、大型トラック) |
違反点数6点(免許停止・6か月以下の懲役または10万円以下の罰金) |
運転手(普通車) |
違反点数3点(反則金3万5,000円) |
事業者(初回違反) |
車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) |
車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) |
車両停止処分(200日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) |
車両停止処分(500日×違反車両数) |
過積載が10割以上の場合は、故意に違反をしたとみなされ運送業務も大変危険な状態です。
そのため、運転手には罰金と懲役刑が課せられ、事業者に対する車両停止処分は長い期間を課せられます。
過積載が5割以上10割未満の罰則
過積載が5割以上10割未満の際に課せられる罰則は、次の通りです。
違反内容 |
過積載の罰則 |
運転手(中型トラック、大型トラック) |
違反点数3点(反則金4万円) |
運転手(普通車) |
違反点数2点(反則金3万円) |
事業者(初回違反) |
車両停止処分(20日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) |
車両停止処分(50日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) |
車両停止処分(130日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) |
車両停止処分(330日×違反車両数) |
過積載が10割以上の罰則よりは軽い内容ですが、過積載を5割超えると反則金や車両停止処分が課せられます。
過積載が5割未満の罰則
過積載が5割未満の際に課せられる罰則は、次の通りです。
違反内容 |
過積載の罰則 |
運転手(中型トラック、大型トラック) |
違反点数2点(反則金3万円) |
運転手(普通車) |
違反点数1点(反則金2万5,000円) |
事業者(初回違反) |
車両停止処分(10日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) |
車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) |
車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) |
車両停止処分(200日×違反車両数) |
過積載は1kgでも超えると、罰則の対象です。
過積載が5割未満でも、反則金や車両停止処分が課せられるため、最大積載量を守って運送業務を行いましょう。
参考:過積載は、荷主にも罰則が適用されます!!
★過積載防止!荷量を考慮した安全且つ効率的な配車計画をAIで。 →ZENRINロジスティクスサービスの資料を見てみる |
過積載を防止するための対策案

過積載を防止するためには、対策案が必要です。
安全に運送業務を行うために、最大積載量を超えずに業務を遂行する対策案を講じましょう。
過積載を防止するための対策案として、以下の3つがおすすめです。
それぞれの対策案を解説しますので、過積載を防止する参考にしてください。
自重計で積荷を計測する
過積載を防止するために、自重計で積荷を計測しておきましょう。
自重計とは、荷台の下部に設置された積載量を測る装置のことを言います。
トラックが出発する前に、自重計で積載量を確認して、過積載が起きていないことを確認してください。
また、計測した積載量・日付・車両番号を記録しておけば、過積載が起きた際の対応も早くなります。
目視で積載量を確認する
自重計を導入しなくても、目視で積載量を確認する方法もあります。
目視での確認は自重計を使った計測より、確実性は低いですが計測の手間がかかりません。
また、自重計を購入するコストがかからないため、すぐにでも実践できます。
土砂を積む場合は荷台にすり切れいっぱいまで、アスファルトやコンクリートを積む場合は荷台枠から20cm盛り上がる程度までといった、事業者ごとに最大積載量の基準を定めるのも良いでしょうしょう。
目視で過積載を防止するためには、一度自重計で最大積載量を計測して、目安を見極めておくことが大切です。
監督者を設ける
トラックに積み込みが完了した後に、過積載になっていないかチェックする監督者を設けておくのもひとつの手段でしょう。
業務が遅延していたり積み込みに手こずったりと、タイムスケジュールに追われている場合、積載量のチェックが疎かになりがちです。
そこで、監督者を設けて積載量のチェックを徹底すれば、過積載を防止できます。
過積載を防止する責任者として監督者を設けて、安全にトラックが出発できる環境を整えましょう。
まとめ:過積載に許容範囲はないので徹底した対策が必要!
過積載は1kgでも超えると罰則の対象となります。過積載に許容範囲はないので、徹底した対策が必要です。
過積載のままトラックを運転すると、制動距離が長くなりスピードの制御が難しくなります。
また、荷崩れも起きやすくなるので、大きな事故へ発展する可能性が高くなるでしょう。
運送業務における危険性をなくすために、過積載が起きた際には運転手・事業主・荷主それぞれに責任が課せられます。
法律を順守して安全に業務を遂行するため、過積載を防止する対策を実施してください。
過積載を防止し、運送業を効率化するなら「ロジスティクスサービス」を利用しよう!
過積載が起きる原因は、業務効率を向上させようした場合の無理な積み込みが考えられます。
しかし、過積載は道路運送車両法で禁止された行為です。
そのため、安全な積載量で業務を効率化するなら「ロジスティクスサービス」をご検討ください。
ロジスティクスサービスの「AI自動配車」では、荷量を考慮した配車計画、積載率の設定が可能です。
適切な配車計画が立てられれば、運送業を効率化できるだけでなく、過積載も防止できます。
安全に業務を遂行するために、ゼンリンデータコムの「ロジスティクスサービス」の導入をご検討ください。
\ まずはお気軽に 資料ダウンロード/