
クラウド管理とは?導入するメリットや環境構築の方法を解説
クラウド管理は、サーバーや通信システムの高性能化・低価格化を背景として急速に発展しています。
従来までは外部にサーバーを持ち、クラウドでシステムを管理する会社は稀でしたが、現在では当たり前の選択肢となりました。
この記事では、クラウド管理が求められるようになった背景や、クラウド管理のメリットについて解説します。
■拠点情報をクラウドで一元管理しませんか?
情報登録・修正の手間削減、Googleビジネスプロフィールとの連携も!
⇒「Area Marker」の資料を見てみる
目次[非表示]
- 1.クラウド管理とは
- 1.1.クラウド管理の仕組み
- 1.2.クラウド管理が必要である理由
- 2.オンプレミス型やパッケージ型ツールとの違いとは?
- 2.1.クラウド型の特徴
- 2.2.オンプレミス型の特徴
- 2.3.パッケージ型の特徴
- 3.クラウド管理におけるサービスの形態は主に3種類
- 4.クラウド管理の5つのメリット
- 4.1.①低コストで導入できる
- 4.2.②操作性がよく使いやすい
- 4.3.③最新の技術を利用できる
- 4.4.④拡張性が高い
- 4.5.⑤セキュリティが高い
- 5.クラウド管理における3つの注意点
- 5.1.①カスタマイズ性が低い
- 5.2.②導入の手間がかかる
- 5.3.③サービス停止のリスクがある
- 6.クラウド環境の構築方法を3種類解説
- 6.1.プライベートクラウド
- 6.2.パブリッククラウド
- 6.3.ハイブリッドクラウド
- 7.まとめ:クラウド管理で業務を効率化しよう!
- 8.店舗・拠点情報管理システムを導入したい方は「Area Marker」のご検討を!
クラウド管理とは

最初に、クラウド管理について解説します。
に関してそれぞれみていきましょう。
クラウド管理の仕組み
クラウド(クラウドコンピューティング)とは、インターネット等のネットワークを経由して、サービスを提供する仕組みを指します。
iCloud(Apple)や、OneDrive(Microsoft)といったクラウドストレージ(データ保管)サービスを利用されたことがある方も多いでしょう。
クラウドストレージ上のデータは、同一ユーザーとして認証されることで、どの端末からでもデータを取り出せます。
これは、PCやスマートフォンの端末内にのみデータが保存されるのではなく、インターネットを経由した先にある外部ストレージにデータが格納されているためです。
このように、クラウドサービスは外部にサーバーやストレージを設置することで、そこからサービスや機能を利用できるようにしています。
クラウド管理が必要である理由
近年では、業務を行う上で多くのデータを保有し、管理・分析に活用されています。
そうなるとそのデータを保管するリソースが多く必要になり、その分コストもかかります。
またこれまでは、保管しているデバイスが違うと、アクセスできない等の問題もありました。
しかし、クラウド管理にすれば、比較的安価で業務に必要なデータを保管することができ、クラウドにアクセスできるユーザーであれば、どのデバイスからでもデータにアクセスできます。
また、クラウド管理サービスの多くは必要なリソース分のみの契約が可能なため、無駄なコストもかかりません。
このように、多くのデータを扱う近年において、どのデバイス・場所からでもアクセスでき、必要な分のリソースを確保できるクラウド管理が必要なのです。
オンプレミス型やパッケージ型ツールとの違いとは?

クラウドは現代の競争にマッチする優れたサービス形態ですが、常に正しい選択肢となるわけではありません。
クラウドをうまく使いこなすためには、他の選択肢のメリットも理解し、必要に応じて使い分けることが重要です。
以下では、クラウドサービスの特徴とそれ以外にどのような選択肢があり、どのような特徴があるのかを解説します。
クラウド型の特徴
多くのクラウド型の料金形態はサブスクリプションを基本とするため、初期費用が安く、最新の機能を常に利用できることが特徴です。
また、自社内にサーバーを置く必要がないため、自社内で管理する際の維持管理費が不要となります。
一方で、インターネットを経由しなければサービスを受けられないため、オフラインで利用できないという弱点もあります。
オンプレミス型の特徴
クラウド型と対照的に語られるのが、オンプレミス型です。
クラウドサービス登場以前のシステムは基本的にオンプレミス型だったのですが、クラウドが広く普及することで、対となるオンプレミスという言葉が生まれました。
オンプレミスとは、サーバーやソフトウェアを自社内に設置する形態を指します。
自社内に設置された情報システムはすべて自社の所有物であるため、構成の変更や増設が自由に行えます。
しかし、自社所有物であるからこそ、それらの設備を購入・敷設するための初期費用や維持管理費用が必要です。
この維持管理費用の中には、サーバー管理のために必要となる人件費も含まれます。
また、オンプレミスの大きな利点は、インターネット接続なしに利用できることです。
無線を飛ばせない状況や回線を引けない環境では、必然的に選択肢がオンプレミスのみに絞られます。
パッケージ型の特徴
パッケージ型とは、必要な機材やソフトウェア、場合によっては設置やメンテナンスまでのサービスを一括して販売する形態です。
クラウド型・オンプレミス型双方のパッケージが存在し、各社さまざまなオプションを付けて販売しています。
特徴は、サーバーの敷設や維持管理に関する知識が不要、ということです。
欲しいサービスとその周辺に関する業務のすべてを丸投げできるため、余計な業務に煩わされず、自社の中核事業に人材を集中できます。
ただし、割高な費用を請求されやすいことには注意が必要です。
クラウド管理におけるサービスの形態は主に3種類

クラウドサービスは初期費用や維持管理費が不要で、質の高いサービスを受けられることが魅力です。
その中でも「必要な機能のみを受ける」のか「自社機能の大部分をクラウドに置き換える」のかによって、適切なサービスの「規模」が変わってきます。
以下では、SaaS・Paas・IaaSという3つのクラウドサービス形態の規模の違いについて解説します。
①SaaS
SaaS(Software as a Service)とは、必要な機能を有したソフトウェアをインターネット経由で提供するクラウドサービスの形態を指します。
たとえば、「iCloud」や「Gmail」など、インターネット経由で提供されるソフトウェアやアプリケーションが該当します。
手軽に利用できるSaaSですが、機能を絞ってパッケージ化して提供されているため導入スピードは早いもののカスタマイズ性が低いため、要件にマッチしたSaaSを選択することが重要です。
②PaaS
PaaS(Platform as a Service)とは、求める機能を自由に取り付けできるPlatform(土台)を提供するサービス形態です。
ネットワークやOS、ストレージなどが提供範囲であり、SaaSよりカスタマイズ性が高いのが特徴です。
代表的なPaaSとして、Amazon Web Service(AWS)やMicrosoft Azureの中の複数サービスが該当しておりアプリケーションの構築に必要なプラットフォームを提供しています。
③IaaS
機能を絞って貸し出すのがSaaS、プラットフォームを貸し出すのがPaaSですが、IaaS(Infrastructure as a Service)はインフラの貸し出しです。
ここでいうインフラとは、コンピュータやサーバー、ストレージ、通信回線や通信機器を指します。
別の言い方をすると、IaaSとは「情報システム構築に必要なインフラリソースのレンタルサービス」のことです。
ただし、ソフトウェアとパッケージされたIaaSも多く存在するため、PaaSと厳密に区別するのは難しいのが現状です。
クラウド管理の5つのメリット
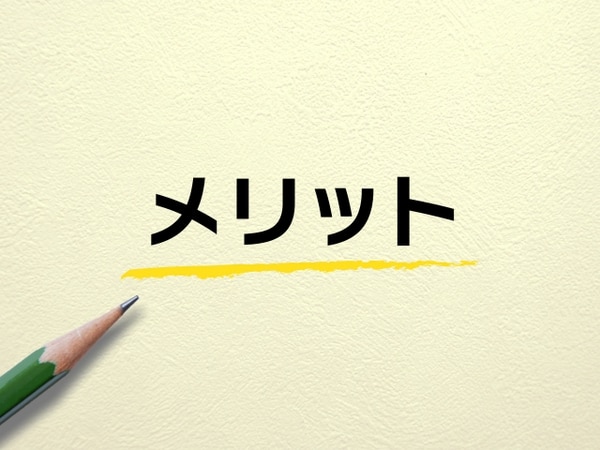
上記内容を踏まえ、クラウド上でシステムを管理するメリットをまとめます。
①低コストで導入できる
自社でサーバーを保有しなければならないオンプレミス型と異なり、クラウド管理システムは初期費用が安いため、低コストで導入が可能です。
そのため、自社ルールと導入システムがミスマッチだなと感じた際には、すぐに利用を取りやめ、別システムの導入を検討できます。
②操作性がよく使いやすい
クラウド管理システムは近年発展が著しく、さまざまな会社が多様なサービスを提供しているため、UIも洗練されています。
また、使いにくい部分は随時改善されるため、オンプレミス型と比べて操作性が優れていることが多いでしょう。
③最新の技術を利用できる
クラウドサービスは常にアップデートされます。
アップデートに関する費用は毎月の利用料金に含まれることが多いため、利用者は日々更新される最新バージョンを追加費用なしで利用可能です。
また、利用者自身でアップデートをする必要もないため、Web開発の知識を保有していなくても、常に最新のサービスを利用できます。
④拡張性が高い
オンプレミスの場合、新たな機能やストレージを追加しようとすれば、その度に購入費用や一定の時間が必要ですが、クラウドではそうした変更も簡単です。
機能の拡張が無料であることは稀ですが、本質的にレンタルサービスであるため、オンプレミスよりも安く機能の拡張が行えます。
⑤セキュリティが高い
従来、クラウド型の欠点はセキュリティ脆弱性だといわれてきましたが、クラウドサービスにおけるセキュリティ面の能力は年々強化されており、欠点とはいえなくなってきました。
たとえば、多層的にセキュリティ対策を行っているクラウドサービスがあります。
クラウド管理システム自体に脅威を侵入させないようにするためのセキュリティ対策や、侵入された場合の対策、情報の漏洩を外部に漏らさないようにするための対策等です。
これらのセキュリティ性は、これからも改善されていくと思われるため、セキュリティ性が高いこともメリットといえるでしょう。
自社システムエンジニアでセキュリティ専門のシステムエンジニアを雇っていないような場合では、下手にオンプレミスにするより、クラウドの方が高い信頼性を担保できます。
クラウド管理における3つの注意点
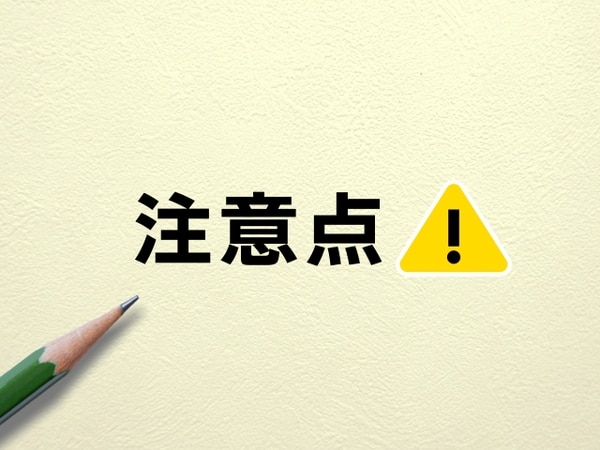
クラウドサービスは便利で強力な管理ツールですが、注意すべき点もあります。
①カスタマイズ性が低い
クラウドサービスは自社の所有物でないサーバーやストレージを借り受けて利用するため、自由に変更できる範囲に限度があります。
たとえば、システムのUIをユーザー側が変更することは不可能です。
そのような応用は効かないということは覚えておきましょう。
②導入の手間がかかる
クラウド管理システムは「即日利用可」や「導入簡単」と謳っているものが多くありますが、そうでない場合もあるということには注意が必要です。
中には事前にしっかりと導入の手順を踏み、ユーザーにあったカスタマイズを行ってくれるものもあります。
導入にどれだけの日数、工程が必要なのかも事前に調べておきましょう。
③サービス停止のリスクがある
クラウドサービスの欠点として、サービス停止の可能性があることもあげられるでしょう。
社内システム管理用のクラウドサービスが停止してしまえば、最悪の場合、社内での業務がすべて停止してしまいます。
クラウドサービスが終了する場合には事前に通知されることがほとんどですが、それも絶対とは言い切れません。
こうしたリスクを避けるためには、利用者が多く、信頼性の高いサービスを利用することが大切です。
クラウド環境の構築方法を3種類解説

ここまでは多様な利用者を想定した外部クラウドサービス(パブリッククラウド)を念頭において解説しましたが、クラウド環境の構築方法は他社サービス利用のみではありません。
一般的にクラウドサービスといえば拡張性に限界があると認識されますが、提供元としっかり連携を取れば、自社に合った、自社専用のクラウド環境(プライベートクラウド)の構築も可能です。
プライベートクラウド
プライベートクラウドとは、各ユーザーに向けてカスタマイズされた専用のクラウド環境です。
サービス提供元が他社の場合もあれば、自社システム管理部門が提供するものもあります。
プライベートクラウドは高い自由度や拡張性を持つことが特徴です。
一方、自社内でクラウド環境を構築する場合、オンプレミスの場合と同様に、サーバーの維持管理に初期費用や固定費用が発生します。
パブリッククラウド
多様なユーザーを想定して運用されるパブリッククラウドは、システムの運用やアップデートに多くのエンジニアが携わっています。
そのため、洗練されたUIや便利な機能が集約されますが、個々のユーザーのニーズすべてに対応することはできません。
自社特有の機能が求められる場合には、プライベートクラウドの利用を検討しましょう。
ハイブリッドクラウド
さまざまなクラウドサービスを使い分けて構築するクラウド環境を、ハイブリッドクラウドと呼びます。
クラウドサービスはコスト、信頼性、機能等さまざまな指標がありますが、常に最高の環境が求められるわけではありません。
場面によっては高い信頼性は不要であったり、機能は少なくても十分であったりします。
そこで複数のクラウドサービスを使い分けて環境を構築すれば、それら多様なニーズに応えつつ、コストを抑えることが可能です。
ただし、複数のサービスを使い分けることでシステム全体が複雑化したり、データの受け渡しが困難になったりすることを考慮して、システム設計が必要になります。
まとめ:クラウド管理で業務を効率化しよう!
人材不足や働き方改革、AI関連技術の発展等、さまざまな要因がクラウドでの情報管理を後押ししています。
今後、クラウド管理は「特別な理由がないなら当然導入するもの」に移り変わっていくでしょう。
今はその過渡期にあります。
社員の負担を軽減したい、業務効率を改善したい、とお考えの方は、あらためてクラウド管理システムの導入をご検討ください。
店舗・拠点情報管理システムを導入したい方は「Area Marker」のご検討を!
自社が保有する拠点情報をクラウドで一元管理したい方は、「Area Marker」の導入をご検討ください。
「Area Marker」は詳細な地図情報をベースとして、クラウド上で店舗・拠点情報を管理できるソリューションです。
Googleビジネスプロフィールと連携することで情報の更新を一度に行うことができるため、MEO対策を行いたい多店舗展開している企業の業務効率向上や修正の手間を省けます。
店舗・拠点情報管理システムを導入して業務効率を向上させたい方は「Area Marker」をぜひご検討ください。
\まずはお気軽に!資料ダウンロード/





